
「ARBって、なんかどれも似てる気がする…?」
薬剤師1年目のとき、降圧薬の棚を見ていて、ふとそんな疑問が浮かんだ人も多いのではないでしょうか。
バルサルタン、テルミサルタン、オルメサルタン…そしてロサルタン。
今や当たり前のように処方されるARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)ですが、最初にこのクラスの扉を開いたのが、実はロサルタンだったこと、知っていましたか?
今回は、「ARBの祖」ともいえるロサルタンがなぜ誕生し、どう使われるようになり、そして現在どのような役割を担っているのかを、やさしく、でもちゃんと振り返ってみます。
ACE阻害薬の「限界」が、新たな開発の起点に
ARB以前、高血圧の治療の中心にいたのはACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)でした。
この薬たちは、アンジオテンシンIIという血管収縮ホルモンの生成を抑えることで血圧を下げますが、副作用として有名な**乾いた咳(ドライコフ)**の頻度が高く、中には使い続けられない患者さんも…。
そこで研究者たちは、「それならアンジオテンシンIIの作用する場所そのものをブロックしてしまえばいいのでは?」と考えました。
この発想から生まれたのが、**ロサルタン(製品名:ニューロタン)**です。
世界初のARB ― ロサルタンの誕生
ロサルタンは1995年、日本では1997年に登場した世界初のARB。
“アンジオテンシンII受容体”を選択的にブロックすることで、ACE阻害薬と同じように血圧を下げつつ、咳といった副作用を回避できるという、新たな治療アプローチを切り拓いた薬です。
開発したのはアメリカのメルク社。この成功の裏には、当時急速に進化しつつあった分子モデリング技術、つまり構造ベース創薬の進展がありました。
ロサルタンの腎保護 ― RENAAL試験が残したもの
ロサルタンは降圧効果だけでなく、腎保護作用でも注目を集めました。
とくに有名なのが、2型糖尿病性腎症患者を対象としたRENAAL試験です。この試験では、ロサルタンが腎機能の悪化や透析導入のリスクを有意に減少させたことが示され、ARBという薬が単なる降圧薬を超えて、「臓器保護」という役割を担うことを世界に示したのです。
こうした実績から、ロサルタンは現在も腎疾患を合併した高血圧患者の治療において一定の存在感を保っています。
そして、ARBという選択肢が定着した
ロサルタンの登場を皮切りに、ARBは次々と登場しました。
バルサルタン、テルミサルタン、オルメサルタン、アジルサルタン…
それぞれに腎保護効果、血圧降下の強さ、作用時間、代謝経路などの違いがあり、医師は患者の背景に応じて使い分ける時代に。
現在、日本高血圧学会のガイドライン(JSH 2019)では、ARBはACE阻害薬と並んで第一選択薬として明記されており、一般的な高血圧だけでなく、糖尿病や腎疾患を伴うケースでも広く使用されています。
ちょっと小話:ロサルタンの「もうひとつの顔」
実はロサルタン、体内で**活性代謝物(EXP3174)**に変換されることで効果を発揮します。この活性体はロサルタン本体の10〜40倍の作用があるとも言われ、プロドラッグ的な性質を持っているのも特徴のひとつ。
また、ARBの中では珍しく尿酸排泄促進作用があるため、**高尿酸血症を伴う高血圧患者にとっては“隠れた推し”**とも言える存在です。
今の薬を知るには、「最初の薬」を知るべし。
ロサルタンは、単なる古株のARBではありません。
**「アンジオテンシンIIの受容体をブロックする」**という新たな治療戦略を切り拓き、ACE阻害薬に次ぐ柱を作った――まさに“はじまりの薬”。
「ARBはどれも似てる」かもしれない。
でも、その始まりがどうだったかを知ることで、“選ぶ”という行為の意味がちょっと深く見えてくるかもしれません。
まとめ
-
ロサルタンは世界初のARBとして登場
-
ACE阻害薬の副作用を回避する新たな戦略として開発
-
RENAAL試験により腎保護作用が注目される
-
現在も腎疾患合併例などで処方されることが多い
-
活性代謝物や尿酸排泄促進など独自の特徴もあり
-
ARBという選択肢の時代を切り拓いた“先駆者”

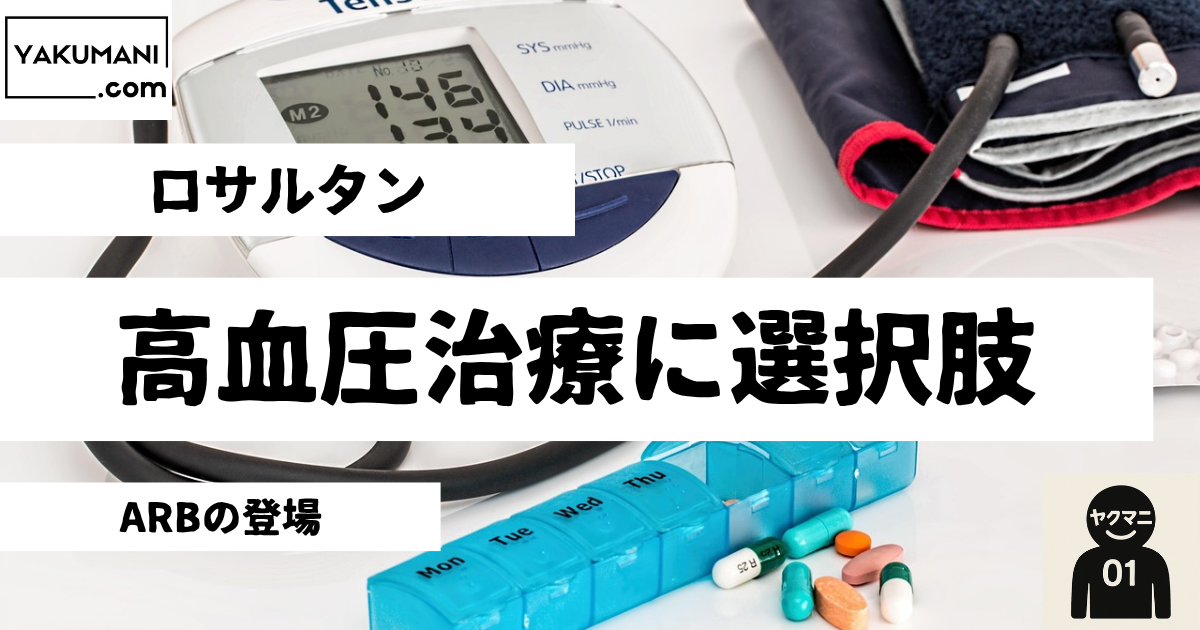
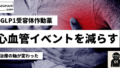
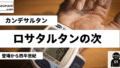
コメント