糖尿病治療に“アウトカム”という概念を持ち込んだGLP-1
CVOTの登場 ― 糖尿病薬に求められる新しい基準
かつて糖尿病治療薬の評価軸は「血糖値を下げる力」に尽きると言っても過言ではありませんでした。
しかし2000年代後半、その常識が揺らぐ出来事が起こります。
ある新薬(ロシグリタゾン)の心血管リスク増大疑惑が浮上し、米国FDAは 2008年に新規糖尿病治療薬に対し心血管安全性試験(CVOT)の実施を求めるガイダンス を打ち出しました 。
以降、糖尿病薬には「心血管イベントリスクを増やさないこと」を実証する大型試験 が義務付けられ、5000~15000人規模・数年間に及ぶCVOTが次々と実施されることになります 。
こうして登場したCVOTの目的は当初、「安全性の確認」、すなわち心筋梗塞や脳卒中など重大イベントを増やさないことの証明でした。
実際、2008年ガイダンス以降に行われたCVOTでは、どの薬剤も重大な心血管リスク増加を示さず、このハードルはクリアされました 。
しかし予想外だったのは、その先です。いくつかのCVOTにおいて**「イベントリスクの軽減」という嬉しい結果が報告され始めたのです 。
糖尿病薬が血糖を下げるだけでなく心血管アウトカムを改善しうる**──この発見は糖尿病治療のパラダイムを大きく転換させました。
特に注目すべきはGLP-1受容体作動薬(以下GLP-1RA)とSGLT2阻害薬という新しい2クラスです。
2015年にはSGLT2阻害薬エンパグリフロジンのEMPA-REG試験が心血管死の大幅減少を報告し、2016年にはGLP-1RAリラグルチドのLEADER試験が主要心血管イベント(MACE)の有意な減少を示しました。
このように、「血糖さえ下がればOK」から「心筋梗塞や脳卒中を減らせるか?」へと、糖尿病治療薬に求められる基準がシフトしたのです。
LEADER試験:リラグルチドの衝撃
2016年、公表されたLEADER試験の結果は糖尿病領域に大きな衝撃を与えました。
GLP-1RAの一種リラグルチド(商品名ビクトーザ®)を約3.8年間投与した群では、プラセボ群に比べて3点MACE(心血管死・非致死性心筋梗塞・非致死性脳卒中)の発生リスクが13%も有意に低下したのです。
さらに詳細をみると、心血管死および全死亡の明確な抑制までも示されました。
血糖降下薬の試験で死亡率低下が証明されたのは極めて画期的であり、これには多くの臨床医・研究者が驚嘆しました。
そもそもLEADER以前、GLP-1RAのCVOT第1報となったELIXA試験(リキシセナチド)では心血管リスク低減効果は認められず、安全性が確認されるに留まっていました。
そうした中で登場したLEADERのポジティブな結果は「血糖を下げるだけでなく心臓を守る抗糖尿病薬」の存在を示唆し、従来の治療戦略を再考させる大きな契機となったのです。
リラグルチド投与群とプラセボ群のHbA1c差は試験期間を通じて僅か~0.4%程度だったにも関わらずこの成果ですから、GLP-1RA自体の作用(体重減少や抗動脈硬化作用)がアウトカム改善に寄与した可能性が高いと考えられます。
臨床現場でもこの衝撃は大きく、日本でも「ビクトーザに心血管イベント抑制効果あり」という話題が広まりました。
ただし薬機法上の制約もあり、製剤添付文書で直接「心筋梗塞予防」を謳うことはできません。
それでも医療者はエビデンスとしてこの結果を共有し、**「糖尿病治療の目的の一つは心血管イベント予防である」**という認識が若い世代の薬剤師・医師にも浸透し始めたのです。
SUSTAIN-6・REWIND:セマグルチド、デュラグルチドの立ち位置
LEADERの成功を受け、「果たしてこれはGLP-1クラス全体の効果なのか?」という疑問が生まれました。
その答えを探るべく報告されたのが**SUSTAIN-6試験(セマグルチド)とREWIND試験(デュラグルチド)**です。
それぞれ作用時間の長い週1回製剤であるセマグルチド(オゼンピック®等)とデュラグルチド(トルリシティ®)について心血管アウトカムへの影響が検証されました。
SUSTAIN-6試験は平均2.1年という比較的短期の追跡期間ながら、驚くべきことにMACEの発生リスクを26%低減(HR 0.74, 95%CI 0.58–0.95)する結果を示しました 。
参加者の約83%が心血管疾患既往を有する高リスク群でしたが、それにしても短期間でこれだけの効果が得られたのは特筆すべき点です。
一方で同試験では網膜症悪化のリスク増加という思わぬ所見も報告されました(セマグルチド群で網膜症関連イベントが有意に多発)。
これは急激な血糖改善による一過性の現象と考察されていますが、GLP-1RA使用時には糖尿病網膜症のある患者では慎重な経過観察が必要であることが認識されました。
REWIND試験は5.4年もの長期にわたりデュラグルチドを検証した試験です。
特筆すべきは参加者約9900人中、心血管疾患の既往を持つ患者は31%に過ぎず、残り約7割は未発症ながらリスク因子を有する糖尿病患者だった点です 。
つまり一次予防目的でのGLP-1RA投与効果を世界で初めて大規模検証した試験と言えます。
その結果、MACEリスクは12%有意に低下(HR 0.88, 95%CI 0.79–0.99)し 、中でも脳卒中の発症抑制が顕著でした(脳卒中リスク17%低下)。
心血管死や心筋梗塞の抑制効果は統計学的有意に至りませんでしたが、全体としてデュラグルチドは低リスク層も含めて心血管イベントを減らしうることが示されたのです 。
SUSTAIN-6とREWINDの位置づけを整理すると、セマグルチドは短期間で高リスク患者に大きな効果を示す一方、デュラグルチドは幅広い患者層で緩やかに効果を示すといった違いがあります。
ただし両者とも「有意なMACE低減効果を持つGLP-1RA」という点では共通しており、もはやGLP-1RAクラス全体として動脈硬化性イベント抑制効果を持つと認識されるに至りました 。
なお、他のGLP-1RAにも目を向けると、週1回製剤エキセナチドのEXSCEL試験は惜しくも主要評価項目で優越性を示せず(HR 0.91, 95%CI 0.83–1.00) 、一方、既に市場撤退したアルビグルチドのHARMONY試験は有意なMACE低減を示すなど薬剤ごとに結果は様々でした 。
さらに2021年にはエフペグレナチドのAMPLITUDE-O試験が報告され、エキセナチド系(Exendin-4由来)の薬剤として初めて有意な心血管イベント抑制効果を示したことも付記しておきます。
総じて言えば、長時間作用型のGLP-1RAはクラス効果として心血管アウトカムを改善しうるものの、薬剤の構造や作用時間による若干の差異は存在する、というのが現時点での知見です。
SGLT2阻害薬との違い ― 心不全と動脈硬化性疾患の分担
心血管アウトカム改善効果を示した新薬として、GLP-1RAと双璧をなすのがSGLT2阻害薬です。
両者はしばしば同列に語られますが、その効果の現れ方には**「心不全 vs 動脈硬化性疾患」**という大きな違いがあります。
SGLT2阻害薬のCVOTでは、一貫して心不全による入院リスクの大幅低減が報告されてきました。
例えばエンパグリフロジンのEMPA-REG試験やカナグリフロジンのCANVAS試験では、主要な動脈硬化性イベント(MACE)を約14%減少させたのに加え、心不全入院を約30~35%も減少させています。
この「心臓のポンプ機能を守る」効果はクラス全体で共通しており、後発のDECLARE-TIMI58試験(ダパグリフロジン)でも高リスク群における心不全予防効果が確認されています。
さらにSGLT2阻害薬は腎臓保護効果も顕著で、CREDENCE試験では腎症を有する患者で心血管死・心筋梗塞・脳卒中の複合リスクや心不全入院リスクを20%低減するなど 、心臓と腎臓を守る薬としての地位を確立しました。
一方、GLP-1RAは心不全抑制効果が一定していない点が大きな相違です。
先述のCVOTを見る限り、リラグルチドやデュラグルチドでは心不全入院抑制は統計学的有意を示さず 、ハーモニー試験(アルビグルチド)のみが例外的に心不全リスク低減を報告しています。
ただしメタ解析レベルではGLP-1RA全体として心不全入院リスク11%減少とのデータもあり 、完全に効果が無いわけではありません。
現時点の解釈としては、「GLP-1RAの主戦場は動脈硬化性疾患予防、SGLT2阻害薬の主戦場は心不全予防」という役割分担が明確になってきていると言えるでしょう 。
動脈硬化性疾患(ASCVD)に対する効果を比較すると、GLP-1RAは脳卒中や心筋梗塞のリスクを幅広く低減するのに対し、SGLT2阻害薬は主に心筋梗塞や心血管死の抑制が中心で、脳卒中抑制効果は明確ではありません 。
実際、GLP-1RAのメタ解析では脳卒中リスク17%低減と報告される一方 、SGLT2阻害薬の主要試験では脳卒中発生率に有意差がないケースも多く見られました(EMPA-REGでは僅かな増加傾向すら指摘されています)。
この違いは両薬剤の作用機序の差に由来する可能性があります。GLP-1RAは体重減少や血管内皮機能改善、抗炎症作用など動脈硬化進展を抑制する作用を持つのに対し、SGLT2阻害薬は利尿・ナトリウム排泄効果による前負荷軽減や心肥大抑制などで心臓の負荷を減らす作用が際立つためです。
その結果、前者は虚血性心疾患・脳卒中の予防に、後者は心不全悪化の予防に、それぞれ強みを発揮すると考えられます。
もちろん一人の患者が両方のリスクを抱えることも多く、その場合はGLP-1RAとSGLT2阻害薬を併用して双方のメリットを享受するアプローチも取られます。
実臨床でも、例えば動脈硬化性心疾患の既往と慢性心不全を併せ持つ2型糖尿病患者には両薬剤の併用療法が検討されるようになってきました。
総じて、「糖尿病治療薬=血糖を下げる薬」から「合併症を防ぐ薬」へと治療の軸が変わり、それぞれの薬剤において得意分野を活かした使い分けが進んでいるのです。
日本のガイドラインではどう評価されているか?
グローバルなエビデンスを受けて、日本の糖尿病治療ガイドラインもアップデートが重ねられています。
直近の**『糖尿病診療ガイドライン2024』では、心血管アウトカムに関するエビデンスを反映し、GLP-1RAやSGLT2阻害薬の位置づけが明確に示されています。
具体的には、「GLP-1受容体作動薬は大血管症の進行抑制に有効であり推奨される(エビデンスレベルA、合意率100%)」とのステートメントが掲げられました 。
同様に「SGLT2阻害薬は動脈硬化性疾患の二次予防に推奨される(グレードA)」**とも明記され、心血管疾患既往のある2型糖尿病患者では積極的に使うよう推奨されています 。
日本人におけるCVOTのデータも蓄積されつつあります。
各国の試験をプールした解析によれば、GLP-1RAの心血管イベント抑制効果は白人よりアジア人で大きい可能性すら示唆されています(HR 0.68 vs 0.87)。
実際、日本人糖尿病患者は欧米人に比べて絶対的な心血管イベント発生率が低いものの 、GLP-1RAやSGLT2阻害薬投与による相対リスク低減効果は概ね一貫して確認されており、日本人でも十分な恩恵が期待できると考えられます。
この点、日本糖尿病学会と日本循環器学会の合同ステートメント(2020)でも、糖尿病患者の心血管予防に両薬剤の有用性が位置づけられており 、エビデンスとガイドラインのメッセージは一致しています。
治療アルゴリズムの観点では、日本でも**「心血管リスクの高い2型糖尿病患者には、メトホルミンに加えて優先的にSGLT2阻害薬またはGLP-1RAを考慮する」という流れが定着し始めました 。
従来は血糖コントロール優先で経口薬を漸次追加していくのが一般的でしたが、現在では合併症リスクに応じた薬剤選択**が重視されています。
特に肥満を伴う症例や動脈硬化性疾患の既往がある症例ではGLP-1RAを、心不全や腎症を合併する症例ではSGLT2阻害薬を、それぞれ早期から組み入れることが推奨されます。
若手薬剤師の皆さんも、患者さんの背景リスクを踏まえて「この方には心臓保護目的で○○を使う」という視点で処方提案や服薬指導を行う時代になってきていると言えるでしょう。
なお薬剤承認上の話を補足すると、日本では現時点でGLP-1RAやSGLT2阻害薬が「心血管イベント抑制」の効能で承認を受けているわけではありません。
しかしエビデンスに基づくガイドラインがそれを推奨している以上、実臨床では事実上その効果を期待して使用されます。
薬剤師としても、エビデンスと承認上の表現のギャップを理解しつつ、最新の知見に裏付けられた薬物療法の意義をしっかり把握しておく必要があります。
GLP-1は予防薬なのか?治療薬なのか?という問い
最後に、GLP-1RAがもたらした本質的な問いについて考えてみましょう。
それは**「GLP-1RAは糖尿病の治療薬なのか、それとも合併症予防の薬なのか?」という視点です。
従来、糖尿病治療薬は高血糖という「症状」を改善するためのものであり、いわば対症療法的な治療薬という位置づけでした。
一方、心血管イベント予防薬とはスタチンや抗血小板薬のように将来起こり得る病態を未然に防ぐ予防薬**です。GLP-1RAはこの両者の境界線上に立つ、極めてユニークな存在と言えます。
例えば、心血管疾患の既往がある2型糖尿病患者さんが現在HbA1c7%でコントロール良好だとしても、将来の再発予防目的でGLP-1RAを追加投与することが検討される時代になりました 。
これは「血糖値を下げる必要があるから薬を出す」という従来の考え方から逸脱しています。
すなわち、血糖値とは無関係に心臓を守るために薬を使うという発想であり、GLP-1RAが予防薬的な役割を担っていることを示しています。
この問いは糖尿病治療の哲学にも関わります。糖尿病の合併症には細小血管症(網膜症・腎症・神経障害)と大血管症(心筋梗塞・脳卒中など)があり、前者は主に血糖コントロールで予防し、後者は血糖以外のリスク管理(脂質異常や血圧管理、抗血栓療法)で予防するというのがこれまでの常識でした。
しかしGLP-1RAの登場で、血糖改善と大血管イベント予防が一つの薬で両立し得ることが示され、治療と予防の垣根が低くなったのです。
実際、最近公表されたSELECT試験は、糖尿病を有さない肥満患者に週1回セマグルチド2.4mg(高用量製剤)を投与し、心血管イベント発生を20%減少させたという衝撃的な結果を示しました 。
この研究はGLP-1RAが純粋な予防薬として機能し得ることを証明したと言えます。
肥満症治療薬としてのセマグルチドが、まさに将来の心筋梗塞や脳卒中を減らしたのです。
これは「肥満そのものが治療ターゲットであり、合併症予防につながる」という第1部のテーマ「肥満との闘い」にも通じる発想でしょう。
ではGLP-1RAは治療薬と予防薬のどちらと考えるべきなのでしょうか。
私の見解では、「糖尿病治療薬であり、かつ心血管予防薬でもある」という二面性こそがGLP-1RAの魅力であり、本質だと考えます。
日々の臨床では、高血糖是正という即時的な治療効果と、将来のイベント抑制という予防効果を一挙に提供できるわけですから、患者さんにその価値を伝える際も「この薬は血糖値を下げるだけでなく、心臓や血管を守ります」といった説明が可能です。
若手薬剤師の皆さんには、ぜひこのアウトカム志向の視点を持って患者さんや医療チームと接していただきたいと思います。
まとめ
GLP-1受容体作動薬は、糖尿病治療に「アウトカム重視」の新たな軸をもたらしました。
血糖コントロール薬から心血管イベント抑制薬へ──その二重の顔を理解することで、私たち医療者はより質の高い糖尿病診療を実践できるはずです。
治療と予防の垣根を越えたこの薬を上手に使いこなし、**「糖尿病=肥満との闘い、そして心血管リスクとの闘い」**に挑んでいきましょう。

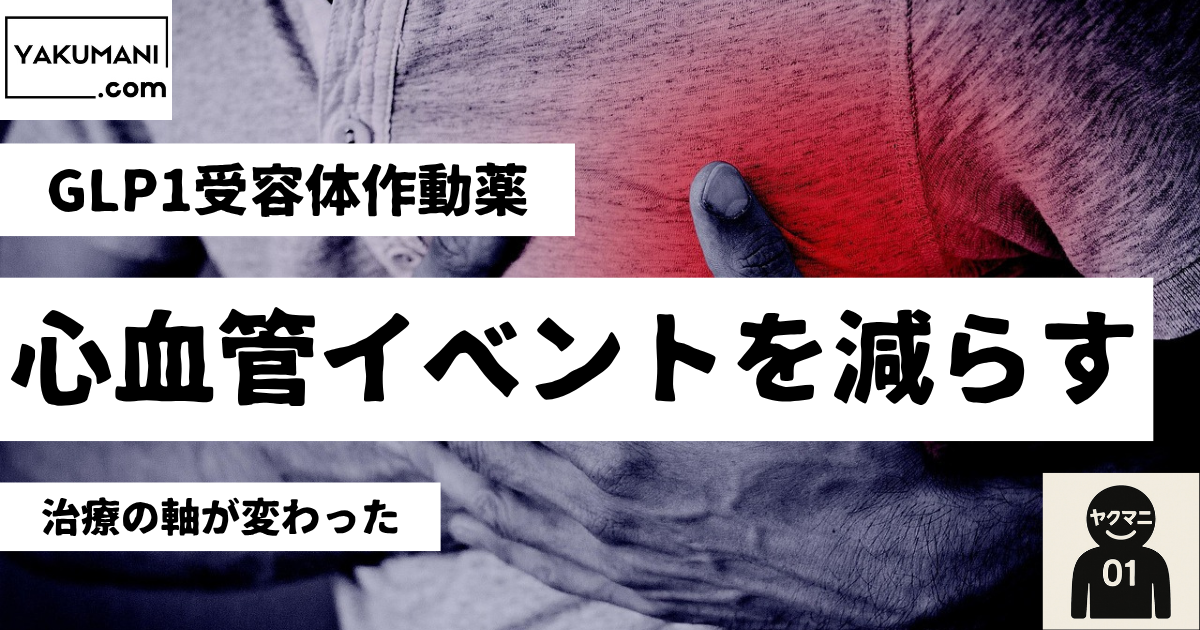
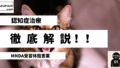
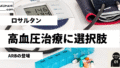
コメント