奇跡の薬の舞台裏
1980年代、それまで「賭け」とまで言われた臓器移植が徐々に日常的な治療へと変わっていきました。
その立役者となったのがシクロスポリンという一つの薬です。
シクロスポリンは、臓器移植後の拒絶反応を抑える強力な免疫抑制剤で、登場当初は「奇跡の薬」とまで呼ばれました。
しかし、この薬が製薬企業サンド社(現在のノバルティス)の研究所で発見・開発されるまでには、知られざるドラマと研究者たちの執念の物語がありました。
1960年代後半から70年代にかけて、医薬品開発の現場では何が起こっていたのか。
ここでは、シクロスポリン発見の舞台裏と、当時のサンド社の研究開発体制、その背景にある世界的な潮流について、薬剤師の皆さんにも読み物として楽しんでいただけるよう、詳しく紐解いていきます。
1970年代の製薬業界とサンド社の挑戦
1970年代当時、製薬業界では抗生物質ブームの流れが一段落しつつありました。
ペニシリン(1928年発見、1940年代実用化)やストレプトマイシン(1943年発見)に始まる抗菌薬の黄金時代を経て、多くの医薬企業が土壌菌やカビなど微生物から新たな抗生物質を探し出してきました。
1950~60年代にはテトラサイクリン、クロラムフェニコール、エリスロマイシンなど次々と発見され、市場には抗生物質があふれるほどになります。
そうした中で、「次の一手」として注目されたのが抗真菌薬や免疫抑制剤といった新たな分野でした。
当時、深在性真菌症(体内でのカビ感染)は有効な治療薬が乏しく、また臓器移植は拒絶反応との闘いで成功率が極めて低かったためです。
製薬各社は抗生物質に続く画期的新薬を求め、依然として「微生物が作る分子」に大きな期待を寄せていました。
スイスのサンド社も例外ではありません。
サンド社はもともと染料メーカーとして始まりましたが、1917年にアルバート・ホフマンらの尽力で天然物化学に基づく医薬品研究部門を設立し、エルゴタミン(麦角アルカロイド)製剤の「Gynergen®」を世に送り出した歴史があります。
さらに1930年代にはサンド社の研究者アルバート・ホフマンがLSDを合成・発見し、精神薬理学の扉を開いたことでも知られます。
こうした天然物由来の創薬に強みを持つサンド社は、1970年代には世界各地の土壌サンプルから微生物を分離し、有用な代謝産物を探索する戦略を積極的に展開していました。
当時は生物多様性に関する国際的な取り決めも緩く、企業の研究者が海外から土壌や微生物を自由に持ち帰って研究できる時代でした。
サンド社は自社の研究ネットワークを活かし、世界中の僻地から珍しい微生物を集めては、その産生物をスクリーニングする体制を整えていたのです。
「微生物から新薬」を探せ:抗生物質ブームの余波とスクリーニング戦略
サンド社内では、抗菌剤・抗真菌剤開発のための微生物スクリーニングプロジェクトが活発に行われていました。
当時、多くの製薬企業が土壌中の放線菌(Streptomyces属など)から抗生物質を発見してきた歴史があり、サンド社も同様の手法で新規化合物を探していたのです。
研究者たちは土壌や植物、海泥など様々な環境から微生物を分離し、その培養液から抽出した化合物ライブラリーを作成していました。
そしてそれらの化合物ライブラリーに対し、細菌やカビに対する抗菌活性試験のみならず、多岐にわたる薬理試験を行う「ゼネラルスクリーニング・プログラム」が組まれていました。
1970年、サンド社の薬理部門責任者K・ザーメリ(Kurt Saameli)博士は、およそ50種類にも及ぶ薬理試験系を各専門グループで実施する包括的スクリーニング体制を発足させました。
このプログラムには、鎮痛・抗炎症作用、降圧作用、代謝作用など様々な項目に加え、免疫抑制作用を検出する試験系も含まれていました。
当時免疫学分野は発展途上でしたが、サンド社では既に1960年代から**Ovalicin(オーバリシン)**という真菌代謝物の免疫抑制活性に着目しており、この分野の先駆的な研究を行っていたのです。
オーバリシンは1965年にPseudeurotium ovalisというカビから分離された化合物で、非常に強力な免疫反応抑制効果を示しましたが、副作用の問題で開発は中断されていました。
しかしその研究のおかげで、サンド社内には免疫抑制作用を検出する技術基盤(マウスに対する赤血球免疫応答を測定する系など)が整っており、研究者たちは「第二のオーバリシン」を見出す機会を窺っていました 。
ある夏の日、北欧の高原で:ハンス・ペーター・フライの土壌サンプル
1969年の夏、スイス・バーゼルにあるサンド社研究所の生物学者ハンス・ペーター・フライ(Hans Peter Frey)は、休暇で妻と共に北欧ノルウェーを訪れていました。
フライは自然を愛する探究心旺盛な科学者で、旅行先でもただ観光するだけでなく、有望な土壌サンプルを見つけては小瓶に採取することを習慣としていました。
ノルウェー南部から西海岸ベルゲンへ向かう道中、一行は雄大な山岳高原地帯ハダンゲルヴィッダに差し掛かります。
標高1000メートルを超えるツンドラの広がるこの地は、夏でも肌寒く、コケや地衣類が地表を覆う独特の環境でした。
フライは車を停め、目的地近くの**スキフテシェーン湖(Lake Skiftesjøen)**のほとりでいくつか土壌を採取しました。
彼にとっては家族旅行の一幕でしたが、この時集めた小さな土のサンプルが後に「黄金のニワトリ(Golden Hen)」とも呼ばれる価値を生むことになるのです 。
フライが持ち帰ったノルウェー産の土壌サンプルは、バーゼルのサンド社天然物研究部門に送られました。
その土壌中に含まれていた微生物を寒天培地で培養したところ、あるカビ(糸状菌)が分離されました 。
最初、このカビは形態的にトリコデルマ属(Trichoderma)の一種に似ていたため、社内では「Trichoderma polysporum の株」と誤って分類されました。
しかし1971年、オーストリアの著名な菌類学者ヴァルター・ガムス(Walter Gams)博士がこの分離株を精査し、既知のどの菌種とも異なる新種であることを突き止めます。
ガムスはこの新種にTolypocladium inflatum(トリポクラジウム・インフラタム)という学名を与えました。
このカビは高緯度の冷涼な土壌に生息する種類で、後に**セミノコガ(蝉の子菌)**とも呼ばれる昆虫寄生菌の一種であることが分かっています。
思いがけず未知のカビを発見したことに、研究者たちは胸を躍らせました。
新種のカビが生んだ化合物:サイクロスポリンとの出会い
サンド社の研究チームは、このTolypocladium inflatum株の培養液から抽出物を得て、さっそく生物活性の評価を開始しました。
担当したのは微生物由来化合物の探索に長けたミヒャエル・ドレイフス(Michael Dreyfuss)博士らのグループでした。
彼らは得られた抽出物を分画し、主要な活性成分として環状ペプチド構造の化合物を単離します。
後にサイクロスポリンA(英語綴り: Cyclosporine A)と命名されるこの化合物は11個のアミノ酸からなる環状の分子でした (名称は「サイクロ=環状」「スポリン=胞子由来」の意)。
また類縁体としてサイクロスポリンCなど複数の類縁ペプチドも得られました。
まず期待されたのは抗真菌活性です。
抽出物がカビ由来であったことから、ペニシリンのような抗生物質的効果を期待していたのです。
ドレイフス博士らはサイクロスポリンAおよびCの抗菌スペクトルを調べましたが、結果は芳しいものではありませんでした。
サイクロスポリンは一部のカビに対してのみ弱い増殖阻害効果を示すにとどまり、細菌に対しては全く効果がありませんでした。
ごく限られた真菌種(たとえばカンジダ属など)にしか効かず、他の多くの微生物には無力だったのです。
この狭い抗真菌スペクトルから、ドレイフスらはサイクロスポリンの作用機序として真菌細胞壁(キチン)合成阻害を疑いました。
実際、日本で発見されていた抗真菌抗生物質ポリオキシンが似たように限定的なスペクトルを持ち、キチン合成阻害剤であることが知られていたからです。
しかしサイクロスポリンの活性はポリオキシンよりも弱く、臨床応用できる抗真菌薬と呼ぶには力不足でした。
ドレイフスらは一定の検討を行った後、「この化合物に抗生物質としての将来性はない」と判断し、抗真菌剤開発のラインからは撤退する決断を下します。
せっかく見つけた新種のカビでしたが、その産物は「使えない抗生物質」に過ぎないのか──研究チームには失望感が漂いました。
ところが、この段階でサンド社の包括的なゼネラルスクリーニング戦略が功を奏します。
抗菌用途で行き詰まったサイクロスポリン抽出物(社内コード24-556と呼ばれていました)は、研究者の一人A. リューガー(A. Rüegger)博士の提案で、先述の50種類の薬理試験プログラムに回されることになりました。
1971年のことです。
サンド社では、抗生物質候補が期待外れに終わった場合でも、何らかの有用な生理活性が隠れていないか多角的に調べる習慣があったのです。
24-556試料は各グループに配られ、鎮痛作用から血圧への影響まで様々な試験が行われました。その結果、たった一つ、明確な陽性反応を示す項目がありました。
マウスの免疫抑制効果です。
動物実験グループでは、マウスに外来抗原(ヒツジの赤血球)を投与して抗体産生させるモデルを用い、並行して候補化合物を投与することで免疫応答の抑制を測定していました。
サイクロスポリンを含む抽出物24-556を腹腔内投与したマウスでは、対照群と比べて血中の抗体価(溶血反応)が劇的に低下していたのです。
なんと、抗体価が1024分の1にまで減少するという強力な効果が観察されました。
さらに驚くべきことに、そのマウスでは骨髄抑制などの副作用徴候はほとんど見られませんでした。
この結果に研究陣は色めき立ちます。
担当免疫学者だった**ジャン=フランソワ・ボレル(Jean-François Borel)**博士は、まさに「これは…臓器移植の拒絶反応を抑えられるかもしれない」と直感したに違いありません。
事実、サイクロスポリンこそが長年移植医療の難題だった拒絶反応制御の鍵を握る物質だったのです。
ボレルとスタエリン:免疫抑制作用の発見と開発チーム
免疫抑制作用の発見後、サンド社内でこの研究を率いたのが前述のボレル博士と、薬理部門の部長**ハルトマン・スタエリン(Hartmann Stähelin)**博士でした。
ボレルは1933年にスイスで生まれ、美術家志望から一転して微生物学者・免疫学者となった異色の経歴の持ち主です。
1970年にサンド社に入社し、免疫学研究グループで働き始めた彼は、まさにシクロスポリン開発チームの中心人物となりました。
一方、スタエリン博士は1925年生まれのスイス人薬理学者で、サンド社で長年基礎研究と創薬を牽引してきたベテランでした。
スタエリンはすでに植物アルカロイド由来の抗がん剤エトポシド(VP-16)の開発にも関与しており、社内で高名な存在でした。
1972年当時、スタエリンはサンド社薬理部門全体の責任者として免疫研究も統括しており、ボレルら若い研究者の指導者的立場にありました 。
ボレルとスタエリンのチームは、サイクロスポリンの免疫抑制効果を慎重かつ詳細に評価し始めました。
まず投与経路や製剤条件による効果の再現性を確認する必要がありました。
最初に強力な効果が出た実験では腹腔内投与でしたが、別ロットのサンプルで試行したところ効果が弱いという事態も起こりました。
これはサイクロスポリンが水に不溶で吸収されにくい性質によるもので、溶解補助剤の違いで生体内利用率が変動したのです。
一歩間違えば「再現できないアヤシイ現象」として開発中止になりかねないところでしたが、チームは培養上清からより純度の高い**純粋サイクロスポリン(社内コード27-400)**を単離し、種々の投与条件で効果を安定的に引き出す方法を検討しました。
サイクロスポリン分子自体の単離精製と構造決定も進められ、1975年頃までにその化学構造が明らかになりました。
それは11個のアミノ酸から成る環状ペプチドで、うち1つはこれまで知られていなかった特殊なアミノ酸(4-[(E)-2-ブテニル]-4-N-メチル-L-スレオニン)であることが判明しました。
創薬化学者たちは全合成にも成功し、十分な量のサイクロスポリンが供給可能となっていきます。
一方、薬理チームはサイクロスポリンの免疫学的作用プロファイルを動物モデルで次々に実証していきました。
ボレルらの報告によれば、サイクロスポリンAはT細胞に選択的に作用し、B細胞や他の細胞増殖には影響を与えないという驚くべき特性を示しました。
マウスの皮膚移植モデルでは、サイクロスポリン投与群で移植片の生着期間が大幅に延長し、ラットの同種骨髄移植でも拒絶が抑えられました。
自己免疫疾患モデルでも効果は顕著で、ラットにおける実験的アレルギー性脳炎(多発性硬化症モデル)では麻痺症状の発現を防ぎ、フロイント完全アジュバント誘発関節炎(関節リウマチモデル)では発症予防だけでなく既に発症した関節炎の症状改善すら示したのです。
ステロイドや細胞毒性抗がん剤以外にこのような選択的免疫抑制効果を持つ物質は前例がなく、まさに画期的な作用機序でした。
ボレルはこの結果に「それは美しすぎて現実とは思えないほどだった(It was almost too beautiful to be true)」と興奮を語っています 。
開発の危機:社内の懐疑と研究者の執念
順風満帆に見えたシクロスポリン開発ですが、1970年代前半の社内情勢は一筋縄ではいきませんでした。
サンド社経営陣は、免疫抑制剤という新領域の市場性に懐疑的だったのです。
1973年頃、社内では「免疫学分野は研究投資に見合うリターンが少ない」という判断がなされつつありました。
当時、臓器移植は主に腎移植が細々と行われている程度で、市場規模は小さく、既存の免疫抑制療法(アザチオプリンやステロイド)も安価でした。
さらに、先に挑戦したオーバリシンが結局臨床試験で失敗したという苦い経験も経営層の慎重姿勢に拍車をかけました。
新薬開発には巨額の投資が必要ですが、シクロスポリンを米国で承認まで持っていくには推定**2億5千万ドル(当時)**もの費用がかかると見積もられたのです。
こうした理由から、経営陣はシクロスポリン開発継続に難色を示し、一時はプロジェクト中止の危機すらありました。
しかし、ボレルとスタエリンをはじめとする研究者チームは簡単には諦めませんでした。
彼らは経営陣を説得すべく、シクロスポリンの適応可能性の再検討を行います。
臓器移植のニーズは限定的でも、自己免疫疾患や慢性炎症疾患への応用ならば市場は大きいはずだ、と考えたのです。
例えば、難治性の重症乾癬や関節リウマチ、ネフローゼ症候群などへの適用可能性を示唆し、さらに実験的アレルギー性脳炎モデル(多発性硬化症のモデル)の結果が非常に良好であったことから、「難治の自己免疫疾患治療薬」として開発を進める大義名分を打ち出しました。
一説には、スタエリン博士はラットの脳炎モデルで麻痺を防げる点を強調し、ボレル博士は関節炎モデルでの効果を訴えるなど、あらゆるデータを動員してプレゼンしたとも言われます。
こうして社内プロジェクトとしての正式な開発継続許可が辛うじて下りたのです。
開発継続が決まると、研究者たちはますます一致団結してシクロスポリンの実用化に邁進しました。
その熱意は凄まじく、ボレルもスタエリンも自ら人体実験の被験者になるほどでした。
シクロスポリンは経口吸収が不安定なため製剤改良が必要でしたが、種々の処方を比較検討する社内試験において、ボレルとスタエリン自身が被験者となり、それぞれの処方での血中濃度推移をモニターしたのです。
研究リーダー自らが身体を張ってデータを集めたことで、最適な galenical 製剤(製剤学的工夫)の方向性が掴まれ、後に開発される経口製剤(Sandimmun®カプセル)の基礎が築かれました。
また血中濃度を測定する分析法の確立にもボレルとスタエリンは深く関与し、治験や臨床応用に不可欠な薬物モニタリング技術が確立されました。
こうした多角的な努力により、1972年の免疫抑制効果発見からわずか4年後の1976年には臨床試験へのゴーサインが出るまでに至ったのです。
このスピード開発は、社内の研究組織がシクロスポリンに大きな期待を抱いていたことの表れでもあります(実際、当時の社内予測では1989年時点で年間売上2500万スイスフラン程度と控えめなものだったにもかかわらず、研究陣の熱意で計画が前倒しされた面もありました)。
世界への発表:移植医療のゲームチェンジャー誕生
シクロスポリン開発の成果がついに公の場で披露される時が来ました。
1976年4月、ロンドンで開催された英国免疫学会の春季会議にて、ボレル博士はシクロスポリンの画期的なデータを発表しました。
この発表は大きな反響を呼び、出席していた多くの科学者や臨床医が耳を疑ったと言います。
中でも強い関心を示したのが、ケンブリッジ大学の移植外科医**ロイ・カルン卿(Roy Yorke Calne)**でした。
カルンは以前から新しい免疫抑制剤を求めており、ボレルの発表を聞くやいなやサンド社にコンタクトを取り、自身の患者で試したいと申し出たのです。
1977年、カルン卿のチームはシクロスポリンを用いた世界初の臨床臓器移植試験を行いました。
結果は驚くべきもので、シクロスポリン投与により移植腎の生着率が飛躍的に向上したのです。
続いて米国でも移植医の巨匠トーマス・スタルツル(Thomas Starzl)らがシクロスポリンを用いた臨床試験を実施し、その有効性を次々と報告しました。
臨床段階での成功を受け、サンド社は迅速に製品化を進め、1982年にシクロスポリン製剤**「サンディミュン® (Sandimmune)」を発売しました。
シクロスポリンの登場により、臓器移植医療は文字通り革命が起こりました。
それまで移植後数年以内に多くの臓器が拒絶で失われていたのが、シクロスポリン使用により拒絶反応がコントロール可能となり、移植片の長期生存率が飛躍的に改善したのです。
例えば心臓移植では4年生存率が70%を超えるようになり、腎移植では1年後の腎生着率が95%に達したとの報告もあります。
かつては「奇跡」と言われた肝移植や膵移植も現実的な治療選択肢となりました。
まさにゲームチェンジャー**として、シクロスポリンは移植医療の地平を開いたのです。
またシクロスポリンは移植以外にも、重症乾癬、類天疱瘡、ベーチェット病、ネフローゼ症候群といった自己免疫疾患の治療にも応用され、多くの難病患者の症状を改善しました。
初の本格的な免疫選択的抑制薬として、後に登場するタクロリムス(FK506)など次世代の免疫抑制剤の道を拓いたこともその功績と言えるでしょう。
シクロスポリンは現在では臓器移植後の第一選択薬の座こそ譲ったものの、依然として医療現場で「元祖」免疫抑制剤として静かに使われ続けています。
自然からの贈り物とサンド社の遺産
こうして生まれたシクロスポリンは、サンド社(現在のノバルティス)にとっても大きな転機となりました。
シクロスポリン開発を通じて培われた免疫学の知見は、同社を免疫疾患治療のリーディングカンパニーへと押し上げます。
サンド社はシクロスポリン成功後も、微生物由来の免疫調節物質の探索を継続しました。
その成果の一つがラパマイシン(シロリムス)です。
ラパマイシン自体は1970年代にカナダの研究者がイースター島の土壌から発見した抗真菌物質ですが、その強力な免疫抑制作用が判明すると、サンド社は誘導体のエベロリムスなど改良型薬剤の開発に乗り出しました。
またタクロリムス系統のアスコマイシン誘導体(例えばピメクロリムス)や、真菌由来のミコフェノール酸誘導体(ミコフェノール酸モフェチル等)なども手がけ、次々と製品化しています。
これらはいずれも「天然物×免疫学」の融合から生まれた薬であり、シクロスポリンから始まるサンド社の研究開発の遺産と言えます。
振り返れば、シクロスポリンの発見はまさに自然からの贈り物でした。
偶然手にした北欧の土壌が、新薬の宝庫となり、人類に恩恵をもたらす──まるで冒険小説のような展開ですが、それを現実のものにしたのはサンド社の研究者たちの情熱と努力でした。
ハンス・ペーター・フライの好奇心、ジャン=フランソワ・ボレルの洞察力、ハルトマン・スタエリンの指導力、そしてチームの執念がなければ、あの小さなカビはただの「珍しい菌株」として忘れ去られていたかもしれません。
薬剤師である私たちにとっても、この物語は多くの示唆を与えてくれます。
薬一つひとつの背後には、科学者たちの試行錯誤やドラマが存在し、その積み重ねが患者さんの命を救う結果に繋がっています。
シクロスポリンという薬剤は、単なる免疫抑制剤ではなく、研究者たちの探究心と信念の結晶と言えるでしょう。
自然から偶然生まれた一滴の化合物が、世界中の移植患者に新たな命を吹き込んだ――その事実に思いを馳せるとき、私たちは改めて創薬の醍醐味と尊さを感じずにはいられません。

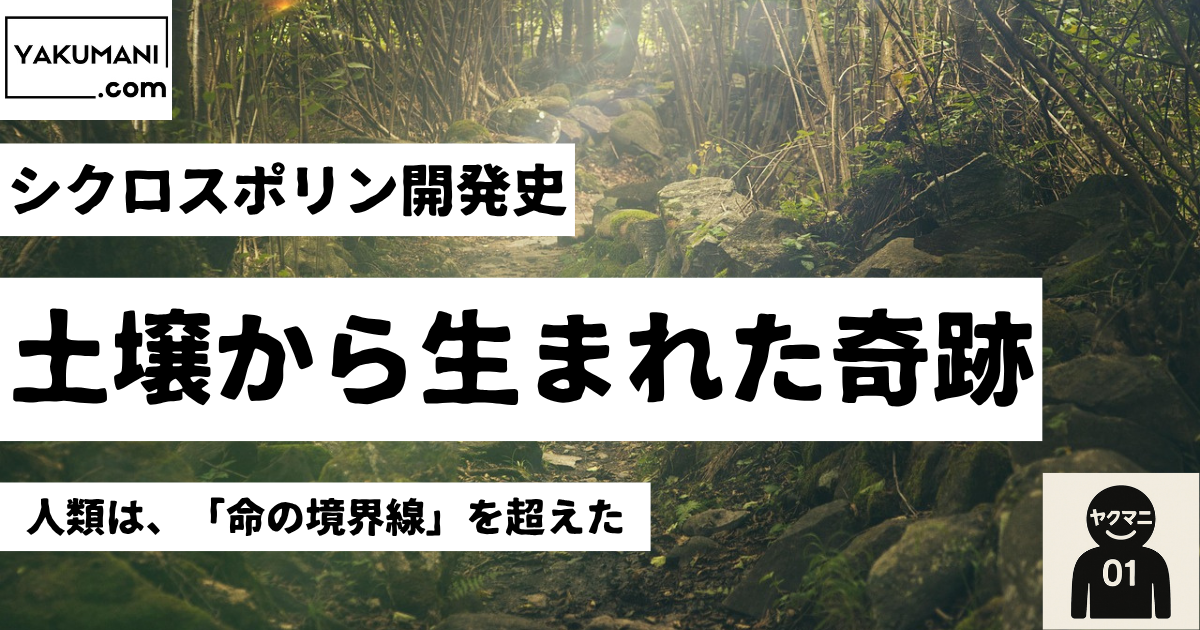
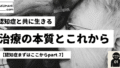
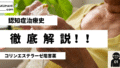
コメント