治療のゴールは「記憶を取り戻すこと」ではないのかもしれません。
本回では、認知症のQOL支援、予防、地域共生といった“これから”の治療観を探ります。
認知症治療の本質的な目的と今後の展望
ここまで認知症治療の歴史を辿ってきましたが、最後に改めて「何のために治療するのか」を考えてみましょう。
認知症は依然として完治困難な疾患であり、治療の目的は進行を少しでも緩やかにし、患者の生活の質(QOL)をできる限り高く維持することにあります。
忘れてはならないのは、その人らしさや尊厳を守り、人生の最後まで人間らしい喜びや役割を感じてもらうことです。
医学的には認知機能テストの点数やMRI所見で治療効果を測りがちですが、それらはあくまで代用目標に過ぎません 。本当の成功指標(true endpoint)は、**「家庭や社会の中で何らかの役割を担い、生きがいを感じられること」「自分の力で何かを成し遂げたという達成感・幸福感を持てること」「無気力にならず興味関心を持ち続けられること」**といった本人の主観的充実感に他なりません。
治療者・介護者はこの真の目標を常に念頭に置き、それぞれの専門性を活かして患者本人と家族を支えていく必要があります。
その上で、今後の展望についていくつか述べます。
認知症治療は今まさに転換期にあり、新たな治療アプローチが続々と模索されています。
抗アミロイド薬に続くものとしては、抗タウ蛋白薬(タウはアミロイド同様にアルツハイマー病の脳内に異常蓄積するもう一つのタンパク質)や、脳内炎症を抑える抗炎症薬、さらには再生医療的アプローチまで、世界中で研究開発が進行中です。
将来的には複数の作用機序を組み合わせた「カクテル療法」も現実味を帯びています。
実際、アルツハイマー病モデルマウスではアミロイドとタウの両方を標的とする併用療法で相乗効果が得られたとの報告もあり、人間でも「コリンエステラーゼ阻害薬+抗体薬+抗タウ薬」といった多面的治療が検討されるでしょう。
これはがん治療の多剤併用や高血圧・糖尿病の包括的治療に似た発想で、認知症も一つの薬では押さえ込めない複雑な病態である以上、今後の主流になる可能性があります。
また、発症予防や悪化予防の重要性も増しています。
2020年のLancet委員会報告では、全世界の認知症の約40%は生活習慣の改善等で予防可能とも試算されています。
特に中年期の難聴、喫煙、糖尿病、うつ、高血圧、社会的孤立といった危険因子をコントロールすることが認知症予防に繋がると示唆されました 。
今後、認知症治療と言えば薬物治療だけでなく生活習慣介入や地域づくりも含めた包括戦略を指すようになるでしょう。
実際、日本でも認知症予防に力を入れる自治体が増え、認知症カフェ、運動プログラム、フレイル予防など多角的取り組みがなされています。
薬剤師も地域で高齢者の健康相談に乗ったり、ポリファーマシー是正で認知機能低下リスクを減らす活動に関わったりと、「薬の専門家」から一歩踏み出した貢献が期待されています。
技術革新も追い風です。
認知症の早期発見には脳画像やバイオマーカー検査が鍵ですが、近年は血液検査でアルツハイマー病のリスクを判定できるような技術開発も進みつつあります。
将来、簡易な採血で脳内アミロイドの蓄積度がわかるようになれば、発症前からの介入(ライフスタイル改善や予防薬投与など)も現実になるかもしれません。
さらにはAI技術を活用した認知機能モニタリングや、IoT機器による見守り支援の発達も、患者の安全とQOL向上に資するでしょう。
認知症は克服すべき厄介な病である一方で、誰もが歳を重ねれば当事者または介護者となり得る**「共に生きるべき存在」**でもあります。
今後の医療・介護は、認知症の人が地域で当たり前に暮らせる共生社会を目指し、治療とケアを統合した包括的アプローチを発展させていく必要があるでしょう。
最後に強調したいのは、認知症治療の本質は「人生を支えること」だという点です。
薬剤で症状を抑えることも大事ですが、それ以上に大切なのは患者さん一人ひとりが持つ物語を理解し、その人らしい人生をできる限り継続できるよう支援することです。
医療はその手段の一つに過ぎません。
認知症治療の歴史を振り返るとき、私たちは科学の進歩だけでなく、ケアの哲学や社会の意識変革といった人間的な進歩にも目を向けるべきでしょう。
これからの未来、画期的な治療法が現れることに期待しつつも、最終的に患者を支えるのは人の温かさと理解であることを忘れずにいたいものです。
シリーズをご覧いただきありがとうございました。
認知症とその治療の歴史を通して見えてきたのは、私たち自身の生き方や社会のあり方そのものでした。
今後もヤクマニドットコムでは、薬の歴史と未来を“知的に楽しむ”コンテンツを発信していきます。


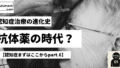
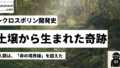
コメント