アルツハイマー型認知症の治療といえば「記憶物質」であるアセチルコリンを増やす――長らくそれが常識でした。
ところが2000年代に入って登場したメマンチンは、その常識を覆す“変化球”でした。
メマンチン(商品名メマリー®)は脳内で過剰に働くグルタミン酸神経にブレーキをかける薬で、いわば**「興奮」に立ち向かう異色の存在**です。これまでの治療薬と一味違うアプローチに、当初は戸惑った医療者もいたでしょう。
しかし、この異端児メマンチンは今や認知症治療に欠かせない一員となっています。
ここでは、メマンチンの登場背景から作用機序、臨床での使い分けや効果、そして薬剤師として知っておきたいトリビアまで、知的エンタメ要素を交えつつ詳しく解説します。
舞台はコリン仮説 ― アリセプト時代の常識
アルツハイマー病(AD)の患者では脳内のアセチルコリンが顕著に減少することが知られています。
1970年代に提唱された「コリン仮説」によれば、この神経伝達物質の不足こそが記憶障害を招く主要因と考えられました。
そこで開発されたのがコリンエステラーゼ阻害薬です。
初のAD治療薬タクリン(1990年代半ば)に続き、1990年代末から2000年代初頭に**ドネペジル(アリセプト®)が世界中で普及し、日本でも1999年に発売されました 。
さらにリバスチグミン(イクセロン®パッチ)やガランタミン(レミニール®)といった薬も登場し、「認知症にはまずアリセプト」**という時代が続きます。
コリンエステラーゼ阻害薬は脳内のアセチルコリン分解酵素を阻害し、不足するアセチルコリンを増やすことで記憶障害の症状を一時的に緩和します。
確かにドネペジル等は軽度~中等度AD患者の認知機能をわずかに改善し、日常生活動作を支える効果を示しました 。
しかしその効果は「劇的な回復」とは程遠く、症状の進行を数ヶ月~1年程度遅らせるに留まります。
しかも胃腸障害(吐き気・嘔吐・下痢)や徐脈などの副作用もあり、一部の患者では十分量を継続できません 。それでも当時は他に選択肢もなく、「アリセプト至上主義」とも言える状況だったのです。
メマンチン誕生 ― 記憶じゃなくて“興奮毒性”を狙え
そんなコリン仮説一辺倒の舞台に、新たな仮説が静かに注目を集めていました。
アルツハイマー病の脳ではアセチルコリン低下だけでなく、グルタミン酸による神経細胞の興奮毒性が関与している可能性が指摘されたのです。
グルタミン酸は脳の主要な興奮性神経伝達物質ですが、過剰になると神経細胞を傷つけてしまいます。
この“興奮毒性”こそがADの神経変性を加速させているのでは?という視点です。
実はメマンチンは1960年代に米国で糖尿病治療薬候補として合成された経緯がありますが効果はなく、その後グルタミン酸受容体作用に注目されました。
ドイツの製薬会社メルツ社が1970年代に中枢作用を見出し、1989年にはドイツで認知症治療薬として承認されています。
欧州全域で2002年、米国でも2003年に承認され、遅れて日本でも2011年に「メマリー®」として発売されました 。
まさに**「記憶ではなく興奮毒性を狙え」**という発想から生まれた異端の新薬だったのです。
当初、メマンチンの登場は臨床現場に少なからず驚きをもって迎えられました。
というのも、メマンチンは認知症の中核症状である記憶障害そのものを直接改善する薬ではないからです。
コリン阻害薬が記憶の不足を“底上げ”するのに対し、メマンチンは脳神経を守ることで症状の悪化スピードを緩やかにすることを狙っています。
言い換えれば、「攻め」のアリセプトに対し「守り」のメマリーとも表現できるでしょう。
そのユニークな作用点ゆえ、「本当に効くのか?」「現場でどう使うべきか?」と手探りの状態からのスタートでした。
しかし、後述するように臨床試験で一定の有効性が示され、メマンチンは中等度~高度ADに対する標準治療の一つとして地位を確立していきます 。
メマンチンの作用機序 ― 興奮のブレーキ
メマンチンは脳内のNMDA型グルタミン酸受容体に作用する拮抗薬です。
NMDA受容体は記憶形成に関与する重要な受容体ですが、アルツハイマー病では慢性的なグルタミン酸過剰によりこの受容体が過度に刺激されっぱなしになり、神経細胞が興奮し疲弊してしまうと考えられます(興奮毒性)。
メマンチンはこのNMDA受容体チャネルに結合し、過剰なカルシウム流入(興奮シグナル)を抑制することで神経細胞を保護します。
いわばアクセルを踏みすぎている神経にブレーキを掛け、暴走を防ぐイメージです。
メマンチンのユニークな点は、NMDA受容体に電位依存的かつ非競合的に作用することです。
平常時、NMDA受容体はマグネシウムイオンによるブロックで過剰な活性が抑えられています。
しかしADでは持続的な軽度興奮でそのブロックが外れっぱなしになり、低濃度のグルタミン酸でも受容体が延々と開口してカルシウムが流入、神経を傷つけます 。
メマンチンはこの病的な受容体チャネルにのみ入り込み、必要以上のカルシウム流入を防ぐのです 。
しかも、その結合は弱~中程度ですぐ受容体から離れやすいため(fast off-rate)、正常な一過性のシグナル伝達は妨げません 。
言い換えれば、**「必要時以外はブレーキを離し、神経伝達の自然な流れは維持する」**賢い仕組みなのです。
さらに興味深いのは、メマンチンが主にシナプス“外”のNMDA受容体を抑制する点です。
ADではシナプス外のNMDA受容体活性化が学習障害や細胞死に関与するとの報告があり、メマンチンはそこを選択的にブロックして記憶機能の改善と神経保護効果を発揮すると考えられています 。
一方で、メマンチンはセロトニン5-HT₃受容体やニコチン性アセチルコリン受容体も遮断する作用を持ちますが、この作用の臨床的意義は明確でありません 。
いずれにせよ、過剰な興奮にだけブレーキをかけ正常な信号は逃がすという絶妙な作用機序こそ、メマンチン最大の特徴です。
臨床試験と実地での使い分け
エビデンスの観点から、メマンチンは中等度~高度ADにおいて穏やかな有効性を示しています。
軽度ADでは有意な効果が確認できず適応外ですが、中等度以上では認知機能・行動・ADL(日常生活動作)の指標でプラセボ群よりもわずかながら良好な結果が得られています 。
例えば海外第III相試験では、中等度~高度AD患者にメマンチンを投与すると1年間で認知機能スコア低下が緩やかになり、日常生活動作の維持に寄与したとの報告があります 。
効果量は決して大きくありませんが、**「わずかでも進行を遅らせたい」**中等度以降のステージでは意義ある成果です。
コリンエステラーゼ阻害薬との併用療法についても検証されています。
ドネペジルなどで治療中の中等度~高度AD患者にメマンチンを追加した試験では、認知機能と日常生活の指標でプラセボ追加群より僅かな改善が見られました 。
ただしメマンチン併用がドネペジル単独を明確に上回る効果は示されず、統計的有意差がつかなかったアウトカムもあります 。
この結果から、「ドネペジルは続けた方がよいが、メマンチン追加のメリットは限定的」と解釈されました。
一方、より長期の観察では併用群の方が要介護度の進行が遅いとの報告もあり、症状緩和以外の側面(例えば周辺症状や介護負担)では併用メリットがある可能性も議論されています 。
英国NICEは2018年に中等度以降ではドネペジルとメマンチン併用を検討すべきとするガイダンスを出しており 、現実の臨床でも二刀流が増えてきています。
では実地ではどう使い分けるべきでしょうか?
まず軽度ADには従来通りコリンエステラーゼ阻害薬が第一選択です 。
中等度ADに進行した段階でメマンチンを追加する、あるいは何らかの理由でコリン阻害薬が使えない場合にはメマンチン単独に切り替える選択肢があります。
ガイドラインでは中等度では最も選択肢が多く、患者の状態に応じてコリン薬+メマンチン併用や単独療法を柔軟に組み合わせることが推奨されています 。
特に感情不安定や易刺激性(いらいら、興奮など)のBPSDが目立つ場合は、まずメマンチンを優先投与して落ち着かせ、後からコリン薬を併用する方法が推奨されています 。
逆に無気力(自発性低下)が強い場合はコリン薬を先行し、十分量まで増量後にメマンチン追加を検討します 。
このように、患者ごとの症状プロファイルや副作用リスクを見極めて**「興奮を抑えるメマンチン」と「記憶を補うコリン薬」を使い分ける**ことが重要です。
高度(重度)ADでは適応を持つ薬剤自体がドネペジル10mgとメマンチン20mgのみになります 。
従って基本的にはドネペジル最大量とメマンチンを併用するのが標準的です 。
もっとも重度になるとコリン薬の効果も頭打ちになりがちで、副作用(食欲不振や徐脈など)により減量せざるを得ないケースも多くなります 。
その点メマンチンは副作用プロファイルが比較的穏やかで、最後まで継続しやすい利点があります。
めまい(約7%)、頭痛(6%)、混乱(6%)、便秘(5%)といった副作用は報告されていますが、頻度は概ね軽微で多くは一過性です 。
実際、臨床試験でもメマンチン群とプラセボ群で有害事象発現率は大差なく、忍容性は高い薬です 。
胃腸障害の多いコリン阻害薬と異なり、眠気やめまいに注意すれば重篤な副作用はまれです。
ただし痙攣発作や一過性意識消失、**一部の精神症状(錯乱や幻覚など)**が重篤な副作用として添付文書に記載されていますので 、こうした症状が出現した際は速やかな受診を指導する必要があります。
メマンチンはどんなときに使うのか?
以上を踏まえ、薬剤師として**「この患者さんにはメマンチンを使うべきか?」**を判断するポイントを整理してみましょう。
ステージが中等度以上に進行したとき
これはまず第一のポイントです。
メマンチンは中等度~高度ADの症状進行抑制を目的に処方されます 。
MMSEやADASなど認知機能検査のスコアが悪化し、中等度に差しかかったらメマンチン導入のタイミングと考えます。
軽度では効果がないため使いません 。
適切な時期に治療を追加することで薬効を最大化できるとされています 。
コリンエステラーゼ阻害薬が使えない・効果不十分なとき
たとえば心臓の徐脈や房室ブロックがありコリン薬が禁忌・中止になった場合、中等度以上であればメマンチン単独療法を検討します。
実際、**「AChEI不耐容または禁忌の中等度~重度ADにはメマンチンを用いる」**という推奨もあります 。
またコリン薬で治療中でも、明らかな臨床悪化が進む場合にはメマンチン追加でブレーキをかける価値があります。
周辺症状(BPSD)が目立つとき
不穏・興奮・攻撃性・被害妄想など行動心理症状が顕著なAD患者には、メマンチンが有用なケースがあります。
特にいらいらや攻撃的行動が中等度ADで出現した場合、メマンチンが情動安定に効果を示すことが報告されています 。
コリン薬にはこうしたBPSD改善効果は乏しいため、BPSD対策としてメマンチンを先行投与し、落ち着いてからコリン薬で記憶面をフォローする戦略が考えられます 。
併用による相乗効果を狙うとき
中等度~高度ではドネペジル+メマンチン併用が選択肢です。
併用自体は基本的に安全で、薬理学的にも作用機序が異なるためお互いの効果を補完できます 。
実際の効果は先述の通り限定的ではあるものの、**「できることは何でもしたい」**という患者・家族の希望や、臨床医の経験的判断で併用されることも多いです。
特に高度ではこの2剤しかないため併用が標準です 。
以上のように、メマンチンは「いつ使うか」より「誰に使うか」の見極めが大切です。
中等度以上で進行を遅らせたい場合、あるいは興奮症状を鎮めたい場合に、メマンチンという選択肢が浮上します。
開始にあたっては5mgから週ごとに5mgずつ漸増し、4週かけて20mg/日の維持量に到達するスケジュールが標準です 。
この漸増は副作用を抑える目的で必須です 。なお重度の腎障害(クレアチニンクリアランス30未満)では維持量10mg/日が上限なので注意しましょう 。
処方提案時には腎機能データも確認し、減量が必要なら医師に進言することが望まれます。
異端が必要とされる理由
アルツハイマー病治療の歴史を振り返ると、メマンチンのような「異端」が求められる理由が見えてきます。
コリン仮説に基づく従来薬は確かに認知症治療の礎となりましたが、疾患の進行そのものを食い止めるには力不足でした 。
症状緩和に留まる治療しかない状況で、患者や家族が求めたのは「少しでも長く現状を維持したい」という願いです。
そこで登場したメマンチンは、異なる作用機序で神経細胞死にブレーキをかけうる点で大いに期待されました。
「異端が必要とされる理由」とはすなわち、多面的なアプローチなしにADという難敵には挑めないからに他なりません。
実際、メマンチンとコリン阻害薬の組み合わせは、記憶システムと神経保護を同時に狙う合理的戦略です。
一つの仮説に固執せず、別の角度から攻めることで治療全体の底上げを図る——これが異端者メマンチンが存在感を示した理由でしょう。
さらに現在では、抗アミロイド抗体など新たな作用機序の薬も開発されつつあります。
アルツハイマー病という複雑な病態に対し、多様な“球種”を持つことが重要であり、メマンチンはその先駆け的存在だったとも言えます。
もちろんメマンチン自体に病態修飾効果(疾患の根本進行を止める効果)は確認されていないのが現状です 。
フランスでは2012年に薬効評価が再検証され、メマンチンの有用性評価が「高い」から「低い」へと引き下げられた経緯もあります 。
しかし、その後も世界中で本薬が使われ続けている事実は、たとえ効果が小さくとも患者・家族にとって意味のある改善であることを物語っています。
「塵も積もれば山となる」ではありませんが、数ヶ月のADL維持や周辺症状軽減は患者の人生に大きな差を生みます。
メマンチンという異端の存在が受け入れられた理由は、そうした積み重ねの価値に他ならないでしょう。
薬剤師がメマンチンを語るとき
メマンチン登場から約20年、臨床現場でも本薬の位置づけは定着しました。
薬剤師がメマンチンを説明するときには、ぜひ**「興奮を抑えて脳を守る薬です」といったわかりやすい表現を添えてください。
記憶を直接良くする薬ではないものの、「症状の進行を遅らせる効果が期待できる」**と前向きに伝えることが重要です 。
特に中等度以降の段階では患者本人よりも家族が薬の意義を問うことが多いでしょう。
その際、「アリセプトだけではカバーしきれない部分を補う薬です」と補足すれば、併用療法の意義も伝わりやすくなります。
また、副作用プロファイルが比較的穏やかな点もメマンチンの利点です。
眠気やめまいに注意しつつ、転倒予防のアドバイス(急な立ち上がりを避ける等)を行いましょう。
便秘がちであれば食物繊維摂取や水分補給を促すなど、生活面でのフォローも大切です。コリン阻害薬と異なり胃腸障害は少ないため、「飲みやすい薬」という印象を与えることも患者の安心感につながります。
さらに薬剤師として押さえておきたいのは適正な漸増と服薬継続の支援です。5mg開始から20mg維持量までの1ヶ月間、つまずきなく増量できるよう副作用の聞き取りを丁寧に行いましょう 。一度20mgに達すれば1日1回の服用で安定しますが、飲み忘れが続くと効果減退につながります。服薬アドヒアランスの確保も我々の腕の見せ所です。
最後になりますが、メマンチンは決して派手さはないものの**「縁の下の力持ち」**として認知症ケアを支える薬です。薬剤師がその価値を正しく理解し、患者・家族に寄り添った情報提供を行うことで、メマンチンの真価は最大限発揮されるでしょう。アリセプト全盛の時代にあえて放たれたこの変化球は、これからも認知症治療のゲームを支える重要な一投となり続けるはずです。
おまけ:知ってた?メマンチンTrivia
- 元々は糖尿病薬?! – メマンチンは1960年代に米イーライリリー社で抗糖尿病薬候補として合成・特許取得されました。しかし血糖降下作用はなく、その後中枢作用に活路を見出されたというユニークな歴史があります 。
- アマンタジンと“いとこ”の関係 – メマンチンの分子構造はアマンタジン(パーキンソン病薬・抗インフルエンザ薬)によく似たアダマンタン誘導体です 。どちらもNMDA受容体を阻害しますが、メマンチンの方が作用が穏やかで長続きするため認知症向きに最適化されています。ちなみにパーキンソン病に対する効果も一部で検討され、低用量メマンチンが振戦・寡動を軽減したとの報告もあります 。
- 放射線から脳を守る – メマンチンは認知症以外にも、全脳放射線照射後の認知機能低下予防に使われることがあります。脳転移などで全脳照射を行う患者にメマンチンを併用すると、その後の記憶力低下を抑えられるとのエビデンスがあり、ガイドラインでも使用が推奨されています 。グルタミン酸神経保護作用を活かした意外な応用例です。
- 実はドパミンにも? – 試験管レベルでは、メマンチンがドーパミンD₂受容体のアゴニスト(刺激薬)としても作用しうると報告されています 。もっとも臨床量での親和性は低く、実際にパーキンソン症状へ影響するほどではないようです。それでも、こうした多面的作用はメマンチンの奥深さを感じさせます。
- 乱用の心配は少ない – 同じNMDA受容体遮断薬のケタミンやフェンサイクリジン(PCP)は幻覚・依存性が問題となりますが、メマンチンは低親和性でゆっくり離れる特性のおかげでそうした中枢副作用を起こしにくいです 。海外ではごく一部でレクリエーション目的の服用例も報告されましたが、「多幸感や陶酔を生じない」ため広まっていません 。長い半減期(60~100時間)も乱用を抑えているのでしょう 。患者さんには「安心して長く使えるお薬です」と説明できますね。
以上、メマンチンという薬の魅力と実力を余すところなくお伝えしました。記憶というストレート一本槍ではなく、“興奮”にカーブを投げるこの変化球が、これからも認知症医療の支えとなってくれることでしょう。

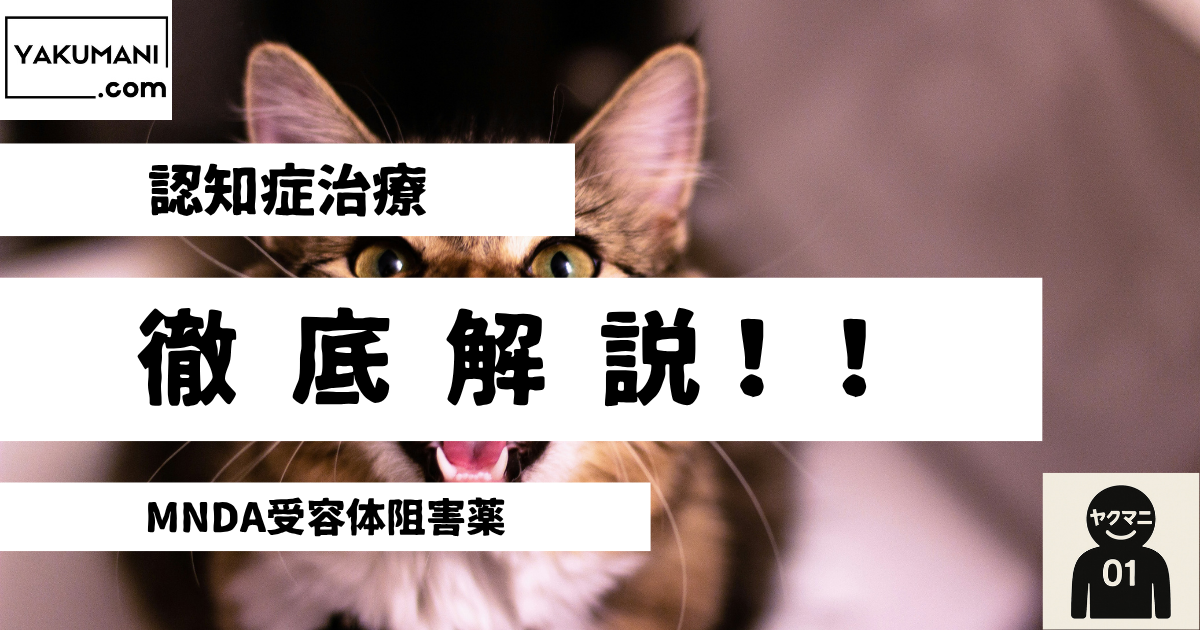
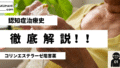
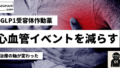
コメント