鎮痛薬から心臓の薬へ?
アスピリン(アセチルサリチル酸)は1897年にドイツ・バイエル社の化学者フェリックス・ホフマンによって合成され、当初は解熱鎮痛剤として世に送り出されました 。その後約1世紀にわたり、頭痛や発熱、痛みに効く手頃な薬として世界中で使用され、家庭常備薬の王様ともいえる存在になっています 。20世紀半ばまで、アスピリンは「熱や痛みを和らげる薬」という位置付けでした。しかし同じ頃、人々の健康上の関心は心筋梗塞や脳卒中といった血栓による循環器病にも向けられ始めます。心臓や脳の血管にできる血栓(血の塊)が重大な疾患を引き起こすことが分かり、血栓を予防する薬への期待が高まっていきました。実はこのとき、ありふれた鎮痛薬アスピリンに血栓予防の力があるかもしれないという着想が、ある偶然の観察から生まれたのです。
偶然のきっかけ:血小板凝集抑制のヒント
1940年代後半、アメリカ・カリフォルニアの開業医ローレンス・クラベン(Lawrence Craven)博士は、アスピリンが血液に及ぼす“思いがけない作用”に気付きました。彼は扁桃腺摘出術や抜歯を行った患者の痛み止めにアスピリンを用いていましたが、その手術後に出血が増えることに注目したのです 。さらに、毎日アスピリン入りのチューインガムを噛む習慣のあった約400人の患者を2年間追跡したところ、心筋梗塞を発症した人が一人もいなかったことも報告しました 。この偶然の観察から、クラベン博士は「アスピリンには血を固まりにくくする作用があり、それによって心臓発作を防げるのではないか」と考えたのです 。彼は1950年にこの仮説と臨床経験を学会誌に発表しましたが、地方誌であったことも影響し、この驚くべき提案は当時大きな注目を集めるには至りませんでした 。
しかし**“アスピリンで血がサラサラになる”というヒントは、徐々に研究者たちの興味を引くことになります。1960年代に入ると、血栓形成に重要な役割を果たす血小板に着目した研究が進み始めました。血小板は傷ができたときに互いに凝集して血を固める細胞成分ですが、1967年、アメリカのハーベイ・ワイス博士とイギリスのジョン・オブライエン博士らが、アスピリンに血小板の凝集を抑制する作用があることを実験で示したのです 。これは、クラベンの臨床的観察を裏付ける科学的証拠と言えます。アスピリンが血小板の働きを妨げるというこの発見により、「痛み止めの薬」が将来心筋梗塞や脳卒中を予防する薬**になる可能性が現実味を帯びてきました。ただし当時は、なぜアスピリンにそんな作用があるのか、その詳しい仕組みはまだ解明されていませんでした。
運命の発見:トロンボキサンA2の抑制
1970年代初頭、その謎を解き明かす決定的な発見がなされます。1971年、イギリスの薬理学者ジョン・ロバート・ヴェイン卿(John R. Vane)は画期的な実験を行い、アスピリンの作用機序を突き止めました。それは「アスピリンはプロスタグランジンという生理活性物質の産生を阻害する」という発見でした 。プロスタグランジンは体内で炎症や発熱、痛みの発生に関与する物質ですが、同時に血小板の凝集や血管収縮を引き起こす種類のプロスタグランジンも存在します。ヴェイン卿の実験により、アスピリンがこれらの物質を作る酵素(シクロオキシゲナーゼ、COX)を少量で阻害できることが示され、痛みや熱が和らぐ理由とともに、血栓ができにくくなるメカニズムも説明できるのではないかと期待されました 。この功績によりヴェイン卿は1982年にノーベル生理学・医学賞を受賞し、アスピリン研究の新たな幕が開いたのです 。
ヴェイン卿の発見を起点として、血小板凝集抑制の具体的な仕組みが次々と明らかになっていきました。1975年、ヴェイン卿の部下であったサルバドール・モンカダ博士らの研究チームは、血小板内でプロスタグランジンからトロンボキサンA2という強力な血小板凝集物質を生成する酵素(トロンボキサン合成酵素)を発見しました。また同時に、血管の内側の細胞(血管内皮細胞)がプロスタサイクリン(PGI2)という物質を産生しており、こちらは逆に血小板凝集を抑制し血管を拡張する作用を持つことも突き止めました 。つまりアスピリンは、血小板中のCOX-1酵素をアセチル化して不可逆的に失活させ、トロンボキサンA2の産生を抑えることで血小板の働きを妨げることが分かったのです 。一方でアスピリンは血管内皮細胞のCOXも阻害するため、血小板凝集を防ぐプロスタサイクリンの産生も減少させてしまいます 。しかし 血小板には核がなく新たな酵素合成ができないのに対し、血管内皮細胞は新たに酵素を補充できるという違いがあります 。このため、アスピリンを少量(例えば1日75〜100mg程度)用いることで血小板のCOX-1だけを選択的に阻害し、プロスタサイクリンへの影響を最小限にしつつ血栓を抑制できることが判明しました 。逆に高用量を投与すると血管内皮のプロスタサイクリン産生まで抑えてしまい、抗血栓効果が弱まるどころか血小板凝集が促進されうることも分かったのです 。このジレンマは後に「アスピリン・ジレンマ」と呼ばれ、アスピリンは低用量で用いるのが理想的だとする現在のコンセプトにつながりました。
こうした作用機序の解明は、アスピリンが他のNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)とは一線を画す薬剤であることも示しています。多くのNSAIDs(例えばイブプロフェンやインドメタシン)はCOX酵素を一時的(可逆的)に阻害するため鎮痛・消炎作用を発揮しますが、血小板機能への持続的な影響は残しません。一方アスピリンは不可逆的に酵素を不活化するため、血小板は一度作用を受けるとその寿命(7~10日)の間ずっと凝集能が低下します 。このユニークな作用ゆえに、アスピリンはNSAIDsでありながら抗血小板薬としての地位を確立したのです。ただし、近年の研究ではアスピリンと他のNSAIDsを併用する際の注意点も指摘されています。例えばイブプロフェンを日常的に服用している患者がそのタイミングを誤ると、イブプロフェンが血小板のCOX酵素活性部位に先に結合してしまい、あとから服用したアスピリンが効果を発揮できなくなることが報告されています 。2001年の研究では、低用量アスピリン服用者が2時間前にイブプロフェンを飲むとアスピリンの抗血小板作用が抑制され、逆に順番を入れ替えればその抑制は見られなかったとされています 。これは、鎮痛目的のNSAIDを服用する患者において、アスピリンは他のNSAIDより先に飲む(もしくは作用の干渉しないアセトアミノフェンなどを用いる)よう指導すべきことを示唆しており、薬剤師にとっても実践的に重要な知識と言えるでしょう。
臨床試験での証明
作用機序の解明と並行して、「では実際にアスピリンは心筋梗塞や脳卒中を防げるのか?」という問いに答えるための臨床試験が世界各地で行われました。1970年代から80年代にかけて、アスピリンの抗血栓効果を検証する大規模試験が次々と実施され、その成果は医学界に大きなインパクトを与えます。
まず脳卒中領域でエポックメイキングだったのが、イギリスで行われたUK-TIA試験(英国一過性脳虚血発作試験)です。一過性脳虚血発作(TIA)とは脳の一時的な血流障害で、将来の脳梗塞発症リスクが高いことが知られます。1970年代後半から進められたUK-TIA試験では、TIAまたは軽度の脳卒中を起こした患者にアスピリン投与群とプラセボ群を比較する無作為化試験が行われました。その結果、アスピリンを長期投与された群では、脳卒中や心筋梗塞など重大な血管イベントの発生率がプラセボ群より有意に低下することが報告されました 。リスク低減の程度は15%前後とされていますが、この試験により**「脳卒中の再発予防にアスピリン有効」**というエビデンスが初めて確立したのです。さらにその後も、脳卒中患者を対象に世界各国で複数の試験が実施され、総じてアスピリンの有用性が示されたため、現在では脳梗塞既往患者の二次予防における標準治療の一つとして位置付けられています。
心筋梗塞(MI)に対するアスピリンの効果を示した代表的研究が、1988年に報告された大規模臨床試験ISIS-2(第二次心筋梗塞生存率国際研究)です。ISIS-2は急性心筋梗塞患者17,000例以上を対象に、①血栓溶解薬(ストレプトキナーゼ)静注、②経口アスピリン投与(1日162.5mg程度)、③両方併用、④いずれも非投与、という4群に無作為割付して比較した画期的な試験でした。その結果、アスピリン単独投与群ではプラセボ群に比べ5週間の血管死亡率が有意に低下し(死亡率:アスピリン群9.4%、プラセボ群11.8%、オッズ減少約23%) 、再梗塞(再度の心筋梗塞)や脳卒中の発生率もおよそ半減しました 。またストレプトキナーゼ(血栓溶解療法)との併用では、両者を用いない群に比べて死亡率が約半分になるという劇的な効果が示され、両治療の効果が加算的であることが示唆されました 。このISIS-2の明快な結果により、「急性心筋梗塞の現場で患者にアスピリンを投与する」ことが治療ガイドラインとして世界標準となったのです。救急医療の場面で、自宅にあった常備薬のアスピリンが患者の命を救う一助になるという事実は、多くの医療者と患者に衝撃を与えました。
その後もアスピリンの臨床的有用性を裏付ける研究結果は蓄積し続けました。2002年には抗血栓療法トライアリスツ・コラボレーション(ATT)による大規模メタ解析が報告され、延べ20万例以上・287件に及ぶ無作為化試験のデータをまとめた結果、動脈硬化性疾患の二次予防において抗血小板薬(主にアスピリン)は明らかに有益であるとの結論が示されています 。例えば心筋梗塞や脳卒中を経験した患者がアスピリンを服用すると、再発や心血管死のリスクが有意に減少し、長期予後(生存率)の改善が認められました。こうしたエビデンスに基づき、1980年代以降アスピリンは「二次予防の切り札」として定着しました。ただし、後述するようにリスク(副作用)も伴うため、一次予防(まだ発症していない人への予防)的投与)については慎重な議論が続けられています。いずれにせよ、鎮痛剤として世に出たアスピリンが臨床試験という厳密な検証を経て、“人類の命を守る薬”へと昇華した意義は極めて大きいと言えます。
栄光と課題
こうした一連の発見と検証により、アスピリンは科学的にも社会的にも大きな“栄光”を手にしました。前述の通り、1982年にはヴェイン卿らにノーベル賞が授与され、アスピリンの作用機序解明は20世紀後半の薬理学最大の業績の一つとして評価されました 。また臨床現場では、心血管イベント既往患者への低用量アスピリン投与が急速に普及し、ガイドラインにも組み込まれていきます。行政当局の承認という面でも、1985年には米国FDAが「既往心筋梗塞患者における再発予防策」としてアスピリンの適応を正式承認し 、アスピリンは**「心臓の薬」として公的なお墨付きを得ました。一方、日本では承認がやや遅れ、2000年になってようやく厚生省(当時)によりアスピリンが「抗血小板薬」として虚血性心疾患や脳梗塞の再発予防適応で承認されています 。それ以前は我が国では医師の判断によるいわゆるオフラベル使用**で対応していたことになり、薬機法上も制約がある中で臨床ニーズに応えてきた歴史がありました。古くから市販されてきた平凡な鎮痛薬が、発売から100年を経て新たな効能で承認を取得する――これは極めて異例の出来事であり、アスピリンという薬の特別さを物語るエピソードと言えるでしょう。
一方、アスピリンがその恩恵(ベネフィット)を発揮する裏には、無視できない課題(リスク)も存在します。最たるものが出血性の副作用です。血小板の働きを抑える以上、多少なりとも出血傾向が高まるのは避けられず 、アスピリンを長期服用する患者では消化管出血(胃潰瘍・十二指腸潰瘍からの出血)や鼻出血、皮下出血(あざ)などが通常より起こりやすくなります。特に上部消化管(胃・十二指腸)の出血リスクは臨床上重大な問題であり、低用量アスピリンであっても無視できません 。実際、低用量アスピリン療法中の患者では、服用していない人に比べて消化管出血のリスクがおおむね2倍程度になると報告されています。このため、胃潰瘍の既往がある患者や高齢者など高リスク患者には、胃粘膜保護のためプロトンポンプ阻害薬(PPI)を併用したり、そもそもアスピリン投与自体を慎重に検討したりすることが推奨されています。また、血をサラサラにする作用は脳出血など出血性脳卒中のリスクもわずかながら高めます。エビデンスを踏まえ「利益がリスクを上回る場合に使う」ことが大原則ですが、「抗血栓療法に出血リスクはつきもの」であり 、投与にあたっては患者ごとのリスク評価が欠かせません。薬剤師としても、アスピリン服用中の患者から黒色便や吐血・貧血症状などのサインが聞かれた場合には注意喚起し、必要に応じて医師に情報提供することが重要です。
さらに、小児への使用制限もアスピリンの課題の一つです。アスピリンをインフルエンザや水痘などウイルス感染症の発熱時に小児へ投与すると、ライ症候群と呼ばれる重篤な急性脳症を引き起こす恐れがあることが判明し、1970年代以降問題になりました 。ライ症候群は嘔吐やけいれん、意識障害を伴い、死亡率の高い危険な合併症です。そのため現在では16歳未満の小児・小児科領域でのアスピリン使用は原則禁忌とされており 、解熱鎮痛目的にはアセトアミノフェンなどの代替薬が用いられます。幸い、川崎病(血管炎の一種)など一部の疾患を除き小児がアスピリンを必要とするケースは多くありませんが、薬剤師としては市販薬を含め小児に安易にサリチル酸系薬剤を使用しないよう保護者に伝えるなど、適正使用の啓発に努める必要があります。
こうした副作用上の課題にもかかわらず、総合的なリスク対ベネフィット評価においてアスピリンは現在でも価値の高い薬剤です。特に心筋梗塞や脳梗塞を起こしたことがある患者にとって、アスピリンは再発予防に欠かせない標準治療として位置付けられており、その有用性は世界中の臨床試験で確立されています。ただし近年は、一次予防目的でのアスピリン投与については慎重さが増しています。糖尿病などリスク因子を抱える未発症の人でも、副作用リスクを上回る効果が得られるかどうかを厳密に見極める必要があるとの認識が広がり、国内外のガイドラインでも「一次予防におけるルーチン投与は推奨されないが、高リスク例では個別判断で考慮」という形に変わりつつあります。薬剤師としても、患者それぞれの背景を踏まえ、医師と協議しながら最適なアスピリン療法をサポートしていくことが求められます。
結び:アスピリンの“二つの顔”
柳の樹皮から見つかった鎮痛成分に端を発し、20世紀には「痛み止めの王様」として君臨したアスピリンは、やがて21世紀を目前に**「もう一つの顔」を確立しました。それは、心血管疾患から命を守る薬という顔です。現在のアスピリンは、一方で解熱鎮痛薬として日常的に使われ続けながら、他方で抗血小板薬として心筋梗塞・脳梗塞の二次予防になくてはならない存在になっています 。このように一つの薬剤が二つの異なる役割を果たす例は極めて珍しく、アスピリンがいかに特別な薬かがわかります。実際、開発から100年以上経った今でもこれほど全世界で使用され、家庭薬として浸透し重宝されている薬は他に例がありません 。アスピリンのたどった軌跡は、臨床の偶然の観察(クラベン博士の気付き)と基礎研究による機序解明**(ヴェイン卿の発見)、そして大規模臨床試験によるエビデンスの確立が折り重なって生み出された医療のイノベーションでした。これは「古い薬に新しい命を吹き込んだ」成功例とも言え、我々医療者・薬剤師に多くの示唆を与えてくれます。
薬剤師の立場から振り返ると、アスピリンの歴史は薬の適応拡大や安全対策について考えさせられる点が多々あります。当初は鎮痛目的で市販された薬が、後になって命に関わる予防薬となるケースはそう多くありません。我々は常に最新のエビデンスに目を配り、昔からある薬でも新たな有効性やリスクが見出されれば適宜情報提供し、患者にとって最良の選択をサポートする責務があります。また、アスピリンは有益である一方リスクも伴う薬の代表例です。出血など副作用への十分な注意喚起を行いつつ、その恩恵を最大限引き出せるよう服薬指導することが、薬剤師に求められる重要な実務と言えるでしょう。
古希を優に超えた今もなお、アスピリンは世界中で日々人々の痛みを和らげ、そして命を支えている薬です。**「二つの顔」**を持つこの薬の歩みは、医学と薬学の発展における貴重な物語であり、今後も語り継がれていくことでしょう。そして私たち薬剤師も、この物語に学びながら、科学的根拠に基づいた正確な知識と適切な判断で、患者さんに寄り添っていきたいものです。

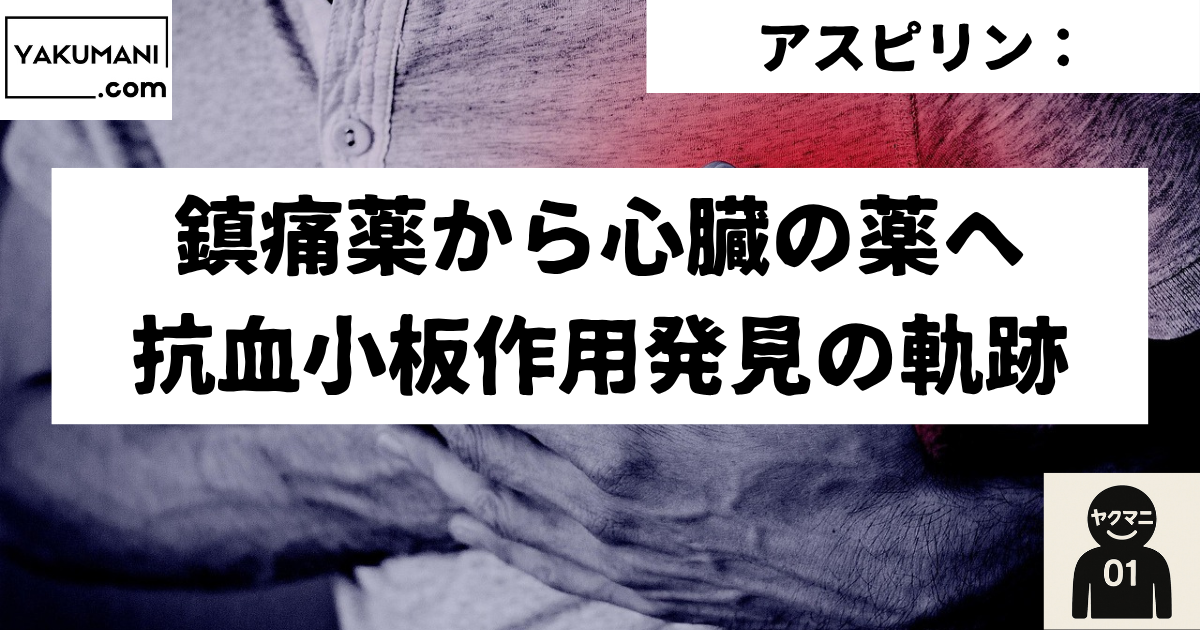
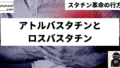

コメント