記憶の鍵を握る神経 ― コリン仮説という出発点
アルツハイマー型認知症(AD)は高齢者に最も多い認知症であり、その病態には脳内コリン作動性ニューロンの脱落(コリン作動性神経細胞の減少)が関与していると考えられています。
1980年代に提唱されたコリン仮説(アセチルコリン不足が認知障害に関与するという仮説)に基づき、認知症の薬物治療の一つの方向性として脳内アセチルコリン量を増やす戦略が模索されてきました。
その結果開発されたのが**コリンエステラーゼ阻害薬(ChE阻害薬)**であり、**アセチルコリンエステラーゼ(AChE)**などの分解酵素を阻害することでシナプス間隙のアセチルコリン濃度を高め、低下したコリン作動性神経伝達を補う作用が期待されています。
これらの薬剤は根本的な治療ではなく症状の緩和・進行抑制を目的とした対症療法ですが、1990年代以降、認知症薬物療法の第一選択として広く用いられるようになりました 。
歴史的には、1993年に米国でタクリン(Cognex)が世界初のAD治療薬として承認されましたが、肝障害の副作用のため臨床使用は限定的でした 。
その後、より安全性に優れる新規薬の開発が進み、1997年に米国でエーザイの**ドネペジル(Aricept)が承認され、日本でも1999年10月にアルツハイマー型認知症治療薬として初めて承認されました 。
続いて2000年前後にガランタミン(Reminyl)とリバスチグミン(Exelon)**が海外で実用化され、これら3剤が現在主に用いられるコリンエステラーゼ阻害薬です。
日本ではドネペジルに遅れること約10年、2011年にガランタミンとリバスチグミンが相次いで承認され、認知症薬の選択肢が広がりました 。
この記事では、それぞれの薬剤の歴史的背景や開発経緯、薬理作用機序、主要臨床試験における有効性評価(ADAS-cog、CDR、CIBIC-plusなど評価指標)、剤形上の特長と服薬アドヒアランスへの応用、副作用プロファイル、そして実臨床での使い分けのポイントについて、最新のエビデンスに基づき解説します。
歴史的背景と開発経緯
ドネペジル(Aricept)の誕生
ドネペジルは、日本の製薬企業エーザイが開発した画期的なコリンエステラーゼ阻害薬です。
開発リーダーを務めた杉本八郎博士は、自身の母親が認知症を患い息子である自分を認識できなくなった経験から、「治療法のない認知症に新薬を創り出すのが自分の使命だ」と強く決意したと語っています 。
研究は1983年に筑波研究所で開始され、当時有力だったアセチルコリン仮説(AD患者では脳内のアセチルコリンが不足し、それが記憶障害に繋がるという仮説)を信じてプロジェクトが推進されました。
先行薬タクリンのような既存化合物の改良ではなく、まったく新しい構造を持つ化合物を目指し、大規模なスクリーニングが行われました。
その中で偶然の発見からシード化合物が見出されます。
元々別の目的で合成されていた化合物に強力なAChE阻害活性があることが判明し、それが開発への道を開くことになりました。
さらに化学修飾を重ね、1985年には初期リード化合物を得ましたが、薬物動態(低い経口利用率)に課題がありました 。
そこで構造最適化を続けた結果、1986年頃にE2020と呼ばれる有望な候補化合物の合成に成功し、1987年に開発候補として正式採択されました 。
こうして開発開始から約15年の年月を経て完成したのがドネペジル塩酸塩であり、1996年にFDA承認(1997年発売)、1999年に日本承認に至りました。
ドネペジルは当初軽度~中等度ADが適応でしたが、その後の試験で重度ADにも有用性が示唆され、現在では重度ADまで含めた幅広い病期に使用可能となっています。
さらに日本では、2014年9月に**レビー小体型認知症(DLB)**に対しても「認知症症状の進行抑制」の効能追加が承認されており、これは世界初の快挙でした 。
この背景には、日本人DLB患者を対象とした臨床試験でドネペジル5~10mg投与により認知機能だけでなく幻視など行動・心理症状の改善も示されたことがあります。
ドネペジルの開発物語には、「家族のために」という研究者の情熱と、偶然の発見を活かした創薬の妙があり、知的好奇心をくすぐるエピソードと言えるでしょう。
ガランタミン(Reminyl)の開発と由来
ガランタミンは、その起源が非常にユニークな薬剤です。
元々はスノードロップ(マツユキソウ)などヒガンバナ科の植物に含まれるアルカロイド成分として1940年代にソ連で単離され、その後1950年代にブルガリアの化学者ディミタール・パスコフによって抽出法が確立された天然由来化合物でした 。
東欧ではこのガランタミンをポリオ後遺症や神経疾患に用いる試みがありましたが、ADへの本格的な適用はコリン仮説が注目され始めた1980~90年代になってからです。
当時、西側諸国でもAD治療薬の開発競争が激化し、ヤンセン・ファーマ(Janssen)社がガランタミンに着目しました。
ガランタミンは既存のAChE阻害薬とは構造が異なる三環性のアルカロイドで、適度なAChE阻害活性に加え、後述する独自の薬理作用を持つことが特徴でした。
臨床開発は1990年代後半に進み、欧米では2000年頃にAD治療薬として承認(米国FDA承認は2001年)されています。
日本では少し遅れて2011年1月に承認・同年3月発売となり 、商品名レミニール®として提供が開始されました。
ガランタミン開発の歴史は「民間薬・天然物から生まれた認知症治療薬」というユニークな側面があり、植物アルカロイドから医薬品への**リポジショニング(新用途開拓)**の成功例と言えます。
リバスチグミン(Exelon)の開発経緯
リバスチグミンは第三世代のコリンエステラーゼ阻害薬とも呼ばれ、イスラエルのエルサレム大学のマルタ・ワインストック=ローシン博士らによって開発されました。
元々、天然のAChE阻害薬であるフィゾスチグミン(カラバルマメ由来)はAD治療への可能性が示されていましたが、半減期が短く血中濃度の維持が難しい問題がありました。
ワインストック博士らはフィゾスチグミンを改良した半合成誘導体を設計し、得られたフェニルカルバマート化合物「ENA-713」がリバスチグミンです 。
リバスチグミンは1997年にノバルティス社へ導出され、国際共同治験を経て欧州で1998年、米国で2000年にそれぞれ承認されました。
日本では他の薬剤に遅れ、ガランタミンと同じ2011年にようやく承認されています(開発コードONO-2540として小野薬品とノバルティスが共同開発)。
リバスチグミンの開発にはユニークな galantamine と同様、既存分子の改良というアプローチがあり、「失敗作を成功作に変える」工夫が凝らされています。
またリバスチグミンは経口カプセル剤のほかに経皮パッチ製剤が開発されたことも特筆すべき歴史的事項です。
2007年に米国・EUで世界初の認知症治療用パッチ(商品名エクセロンパッチ®)として承認され、日本でも2011年4月に国内初の認知症パッチ療法として承認・発売されました。
パッチ製剤の登場は、後述するように服薬アドヒアランスや副作用プロファイルの点で大きな利点をもたらし、認知症ケアの現場に新たな選択肢を提供しました。
作用機序と薬理学的特徴
コリンエステラーゼ阻害薬はいずれも基本的にはアセチルコリンエステラーゼ(AChE)という酵素を阻害し、神経終末から放出されたアセチルコリン(ACh)の分解を遅らせることでシナプス間のACh量を増やし、コリン作動性神経伝達を増強する作用を持ちます 。
AD患者では脳の記憶や学習に関与する海馬や前脳基底部のマイネルト核のコリン作動性神経が高度に脱落しており、AChが著減しています。
このためAChE阻害によるACh濃度上昇で**「不足分を補う」ことができれば、記憶障害などの症状改善が期待されるわけです。
ただしこれら薬剤は根本的な神経変性の進行を止めるものではなく、あくまで症状の修飾的改善に留まる**点には注意が必要です 。
3剤はいずれもAChE阻害という点で共通しますが、作用機序や薬理学的特性に微妙な違いがあります。ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミンの特徴を順に見ていきましょう。
ドネペジル
ドネペジル塩酸塩はピペリジン骨格を有する可逆的AChE阻害薬です。
中枢選択性が高く、AChEに対して選択的に作用し、末梢のブチリルコリンエステラーゼ(BuChE)にはほとんど作用しません 。
AChEの活性部位に強力に結合して可逆的に阻害することでACh濃度を高めます。
薬力学的には非競合的阻害とも言われ、AChEの活性中心と周辺部位双方に結合することで酵素を阻害するとの研究もあります。
また、in vitroデータではドネペジルは脳AChEに対してかなり選択的で、構造的にもタクリンやフィゾスチグミンとは非関連の新規骨格でした 。
さらに近年の研究では、ドネペジルがコルチコイドのニコチン性受容体のアップレギュレーションや、電位依存性Naチャネル・Kチャネルの弱い阻害、さらには神経炎症の抑制作用など非コリン作動性の作用も示唆されています。
これらの副次的作用の臨床意義は明確ではないものの、神経保護的な効果への寄与が期待され研究が続けられています。
薬物動態的には経口吸収が良好(生体利用率ほぼ100%)で血中半減期が約70時間と長く、一日一回投与で安定した効果を発揮します 。
主要代謝は肝臓のCYP2D6および3A4で行われます。
ドネペジルは速やかに血液脳関門を通過して中枢に移行し、効果発現まで数週を要しますが、逆に中止後もしばらく作用が持続します。
以上よりドネペジルは中枢志向性が高く作用持続時間が長いAChE阻害薬として特徴付けられます。
ガランタミン
ガランタミンは三環性のテルペノイドアルカロイドで、可逆的・競合的なAChE阻害薬です。
作用機序上のユニークな点は、AChE阻害作用に加えてニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)のアロステリック部位に結合し感受性を高める作用、いわゆる**「アロステリック増強作用」を併せ持つことです 。
具体的には、ガランタミン分子がnACh受容体のサブユニット間の調節サイトに結合すると受容体のAchに対する反応性が増大し、ニコチン性受容体を介したACh放出促進やシグナル増強が起こるとされています 。
この二重の作用機序(デュアルモード)はガランタミンならではの特徴で、単にACh濃度を上げるだけでなくシナプス前膜からのACh遊離も高めることでシナプス伝達を増幅しうると考えられています 。
薬力学的にはドネペジル等に比べAChE阻害作用そのものはややマイルドですが、ニコチン受容体増強作用との相乗で臨床効果を発揮します。
薬物動態では経口吸収後の半減期が約7~8時間と中程度で、一日2回投与が基本です。
主に肝代謝(CYP2D6, 3A4)を受けます。
他のChE阻害薬に比べると作用発現が穏やかで緩徐とも言われますが、その分忍容性(tolerability)が良好との報告もあります。
なおガランタミンはフィゾスチグミン等と異なりカルバメート構造を持たないため、後述のリバスチグミンのような「非可逆的阻害」は起こしません。
総じてガランタミンはデュアル機序と穏やかな薬効**を特徴とする薬剤です。
リバスチグミン
リバスチグミンはカルバメート系のコリンエステラーゼ阻害薬で、アセチルコリンエステラーゼとブチリルコリンエステラーゼの両方を阻害する点が大きな特徴です 。
ドネペジルやガランタミンが主に中枢AChEを標的とするのに対し、リバスチグミンは中枢・抹消の両方でAChEおよびBuChE活性を抑制します。
ADが進行すると脳内のBuChE活性が相対的に上昇するという報告もあり、両酵素を阻害することの意義が示唆されています。
またリバスチグミンはカルバメート基によって酵素と一時的に共有結合し、酵素をカルバモイル化して**「擬似不可逆的」に阻害する性質があります。
実際には酵素-薬剤複合体は数時間かけて徐々に分解されるため不可逆ではありませんが、作用持続時間は酵素再合成までの時間にも依存し、結果として阻害効果は長めに持続します。
このため血中半減期自体は1.5時間程度と短いものの、薬効は投与中止後も数時間維持されるという特徴があります。
リバスチグミンの代謝はユニークで、主にコリンエステラーゼ自身によって分解(加水分解)されるため肝のP450酵素にはほとんど影響を受けません 。
このことは薬物相互作用の少なさにつながり、他剤併用の多い高齢者でも使いやすいメリットとされています 。
薬物動態的には経口投与では速やかに吸収され1時間程度でC_maxに達しますが、高用量では非線形動態を示し血中濃度が急峻に上昇しがちです 。
そこで開発された経皮パッチ製剤では、24時間一定速度で皮膚から吸収させることで血中濃度プロファイルのピークを低減し、経口12mg/日と同等の作用を9.5mg/24hパッチで実現しています。
パッチにより血中濃度変動が穏やかになることで、後述する消化器系副作用の軽減にもつながっています 。
以上のようにリバスチグミンは二重のコリンエステラーゼ阻害と独特の薬物動態(酵素分解型&パッチ製剤)**を持つ点で他の2剤と一線を画します。
主な臨床試験と有効性評価
コリンエステラーゼ阻害薬の有効性は、世界各国で多数の臨床試験が行われ評価されてきました。
評価指標としてはADAS-cog(アルツハイマー病評価スケール-認知部分)やMMSE(ミニメンタルステート検査)などの認知機能スコア、CIBIC-plus(臨床医による全般的改善度評価+介護者情報)やCDR(臨床的認知症評価)などの全般症状・重症度スケール、さらにADL(日常生活動作)スコアや行動・心理症状(BPSD)の評価などが用いられています。
総じて言えることは、**これら薬剤による改善効果は一貫して「統計学的に有意だが臨床的には中等度(modest)なもの」**と評価される点です 。
以下に主要エビデンスを概観します。
認知機能への効果
代表的尺度であるADAS-cog(スコア範囲0~70点、点数が高いほど障害重度)の変化量で見ると、プラセボでは半年でスコアが悪化するのに対し、ChEI治療群では平均2~3ポイント程度スコアが良好に維持されるか改善することが示されています 。
例えば13件のRCTを統合解析した報告では、6か月時点のADAS-cogスコア変化量は治療群がプラセボ群より2.7ポイント改善し、有意差が認められました。
MMSEでも平均1~2点程度の差で治療群が良好でした 。
一般にADAS-cogで2~4点の差がつけば臨床症状の遅れとして6か月~1年程度の進行遅延に相当するとの指摘もあり 、ChEIには認知機能低下の進行を数か月単位で遅らせる効果が期待されます。
ただし改善幅は個人差が大きく、「劇的に認知症状が消失する」ようなことはありません。効果判定には通常3~6か月程度の投与が必要であり、その時点で明らかな有用性が認められない場合でも、急に中止するとさらに認知機能が低下する症例も報告されています。
そのため治療継続の判断は慎重に行うべきとするガイドラインもあります 。
全般症状・重症度への効果
臨床医が総合的に評価するCIBIC-plus(7段階評価)では、プラセボ群に比べてChEI群で**「改善」と判定される割合が有意に高い**ことが多くの試験で示されています 。
例えばある24週試験では「有効」(改善もしくは大きく改善)と判断された患者割合がドネペジル10mg群で約40%、プラセボ群で20%弱と報告されています。
CDR(Clinical Dementia Rating)という重症度評価に関しては、2年間の長期試験でドネペジルとリバスチグミンを比較した結果、疾患進行抑制効果に両薬で有意差はなく、いずれもCDRによる重症度の進行を完全には止められないものの若干遅延させる可能性が示唆されました 。
また、ChEI治療が患者の介護施設入所までの時間を延長するかについては結論が分かれています。
一部には「わずかながら自宅での生活期間を延ばす可能性がある」との報告もありますが、他方で医療費や介護期間への影響は明確でないとの指摘もあり 、寿命や施設入所時期といった長期アウトカムへの寄与は限定的と考えられます。
ADL(日常生活動作)への効果
ChEIは記憶や見当識など認知面への効果が中心ですが、間接的にADL機能の維持にも寄与します。
臨床試験ではADLスコア(例えばDADやADCS-ADL)で有意差が出ることも報告されており、例えば国内のリバスチグミンパッチ試験ではADLの悪化抑制効果がプラセボより良好でした 。
3剤の総括的なメタ解析でもADLスコア低下を緩和する効果が認められています 。
もっとも、その効果量は認知機能指標と同様に「小さい(small)」と評価され、日常生活動作が劇的に改善する訳ではありません 。
しかし「食事や着替えに介助が必要になるまでの期間を少し延ばせる」「要介護度の進行を遅らせうる」といった意味ではADL維持効果も重要であり、患者・介護者のQOL向上につながる可能性があります。
BPSD(行動・心理症状)への効果
ADでは徘徊、興奮、幻覚、鬱症状など様々なBPSDが現れ、介護者の負担となります。
ChEIがBPSDに与える影響についても検討されてきました。
全般的なNPIスコア(Neuropsychiatric Inventory:行動心理症状の総合評価)の解析では、ChEI投与群でプラセボ群に比べ統計学的に有意なスコア低下、すなわちBPSD軽減が認められたとのメタ解析結果があります 。
ただしその効果量(例えばNPIスコアで平均1~2点程度の改善)から判断すると臨床的意義は限定的であり、実際の症状マネジメントに及ぼすインパクトは大きくないと考えられています。
個別の症状では無関心(アパシー)や幻視に対する改善報告が散見され、特にレビー小体型認知症やパーキンソン病認知症ではChEIが幻視・妄想を和らげるとのエビデンスがあります。
ドネペジルについてはDLBの臨床試験で幻視や認知機能の改善が認められました 。
しかし著しい興奮や攻撃性などには抗精神病薬の併用が必要となる場合も多く、ChEIのみですべてのBPSDを制御できるわけではありません。
そのためBPSDに対する位置づけとしては、「中核症状の改善に伴い二次的に周辺症状も緩和されうる」程度の位置づけで、第一選択はあくまで非薬物的アプローチや環境調整とされます。
ただしChEIは抗精神病薬と異なり錐体外路症状を悪化させる心配がないため、パーキンソン関連の幻視にはリバスチグミン(海外ではパーキンソン病認知症に適応)やドネペジルなどが積極的に用いられるケースもあります。
以上より、コリンエステラーゼ阻害薬の有効性をまとめると、「認知機能・グローバル指標・ADL・BPSDの各面でプラセボより有意に優れるが、その効果はマイルド」ということになります 。
なお3剤間の有効性差については、多くの比較研究やメタ解析で「有意な差は認められない」と結論づけられています。
すなわちドネペジルが特に優れている、あるいはガランタミンが劣る、といった明確な優劣は示されておらず、効果の面では3剤ともほぼ同程度と考えて差し支えありません。
一方、副作用プロファイルについては若干の差異が報告されています(後述)。
剤形の特長と服薬アドヒアランスへの応用
認知症の薬物治療では、患者本人の内服管理能力の低下や嚥下障害、拒薬などの問題から服薬アドヒアランスの確保がしばしば課題となります。各コリンエステラーゼ阻害薬には剤形や投与設計に工夫が凝らされており、これを上手く活用することで服薬継続を支援できます。
ドネペジルの剤形
ドネペジルは一日1回投与が基本で、朝または就寝前に服用します(副作用の悪心対策として就寝前投与とすることが多いですが、不眠が出る場合は朝に変更します)。
剤形は錠剤の他にOD錠(口腔内崩壊錠)があり、水なしでも服用可能です。
嚥下障害や錠剤を嫌がる患者にOD錠は有用で、介護者が口腔内で溶かしてあげることで確実に投与できる利点があります。貼付型のドネペジル経皮パッチも承認されています。
ドネペジルは血中半減期が長く血中濃度変動も小さいため、多少の飲み忘れがあっても急激な血中濃度低下が起きにくいという利点があります。ただし効果安定のため決められた服用時間に毎日継続することが重要なのは言うまでもありません。
ガランタミンの剤形
ガランタミンは一日2回投与(朝夕)です。日本ではレミニール錠が利用可能で、開始時は4mg×2回から漸増し維持量16~24mg/日とします 。
剤形は錠剤の他にOD錠(口腔内崩壊錠)があり、水なしでも服用可能です。
またガランタミンは休薬期間が3日以上空くと再投与時に副作用が出やすいため、その場合は初期用量から再漸増することが推奨されています 。この点からも継続的な服薬のフォローが重要です。
リバスチグミンの剤形
リバスチグミンは日本では経口カプセル剤より経皮パッチ製剤が主に使用されています。
リバスチグミンパッチ(商品名リバスタッチ®パッチ/エクセロン®パッチ)は1日1回皮膚に貼付し24時間作用します。貼付部位は背中、上腕、胸部などで、毎日部位を変える必要があります。
パッチの利点はまず服薬管理が視覚的にできることです。
介護者は貼付の有無を確認でき、患者さんが薬を飲み忘れていないか一目瞭然です 。
また経口に比べて消化管を通さないため初回通過効果がなく、血中濃度の急峻な上昇を避けられることで、副作用で多い吐き気・嘔吐など消化器症状が出にくいというメリットがあります 。
国内第III相試験でもリバスチグミンパッチはプラセボに比べ認知機能悪化を有意に抑制し、さらにADLの維持にも効果を示しました 。
そして副作用の吐き気・嘔吐は経口投与に比べ著しく低減しています 。
こうしたことから、日本ではリバスチグミン=パッチという位置づけになっており、介護者による投薬管理負担の軽減や嚥下困難な患者への対応に大きく貢献しています。
「貼り薬なら薬を拒否しづらい」という現場の声もあり、服薬コンプライアンス向上にも一役買っています 。
なおパッチは4.5mg/日から開始し、4週間ごとに9mg→13.5mg→最大18mg/日へと段階的に増量します。
この漸増も患者・家族には分かりやすく、シールのサイズ(濃度)が大きくなることで視覚的にも認識できます。
以上のように、各薬剤の剤形上の工夫を活かすことで「飲み忘れ」「飲み渋り」への対策が可能です。加えて、認知症患者では服薬アドヒアランス向上の工夫として以下のようなポイントも有用です。
- 服薬カレンダーやピルケースを用いた管理、家族や訪問看護師による見守り。
- ドネペジルOD錠のように水なしで服用できる剤形や、粉砕調剤・ゼリー剤(※国内ではドネペジルの経口ゼリー製剤も市販)を活用し、嚥下障害に対応する。
- 患者が嫌がる場合はアイスやヨーグルトに混ぜて服用させるなど工夫(薬機法上、医師・薬剤師の指導のもと対応)。
- パッチ剤は入浴前後でも使用可能だが、入浴時に剥がれてしまう例もあるため、貼付部位の選択に注意する。剥がした後の廃棄も安全に行い、誤食防止する。
服薬アドヒアランスの維持・向上は治療効果を最大化する上で極めて重要であり、剤形選択と投与設計の工夫によってかなり改善できる点を押さえておきましょう。
副作用プロファイルと安全性
コリンエステラーゼ阻害薬は全身のコリン作動性を高める作用機序上、どうしてもコリン作動性副作用が発現しやすくなります。主な副作用は以下の通りです。
消化器症状
悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、腹痛などがもっとも多く報告されます 。
特に開始初期や用量増量期に吐き気が出やすく、重症例では嘔吐に伴う脱水や体重減少に至ることもあります 。
実際、ドネペジル23mg(高用量)投与試験では5mg投与群に比べ悪心・嘔吐の発現率が数倍高く、23mg群の約3%が嘔吐のため中止せざるを得なかったとの報告があります 。
こうした消化器症状は投与継続で1~3週間程度で慣れる場合もありますが 、高齢者では重篤化しやすいため注意深いモニタリングが必要です。
対策としては低用量から開始し、ゆっくり漸増することが基本です。
また、食後服用や就寝前服用とする、PPIや胃粘膜保護剤を併用する(ただし根本対策にはならない)といった工夫もされます。
リバスチグミンでは前述の通りパッチ剤の利用で消化器症状を大幅に低減できます 。
いずれにせよ、消化器系の副作用が持続する場合は無理に増量しない、症状が強ければ減量や休薬を検討するなど柔軟に対応します。
心臓・循環器系
コリン作動性の亢進により徐脈(脈拍低下)が生じることがあります。
洞結節や房室結節に対する迷走神経刺激が強まるためで、重症例では失神や房室ブロックに至るリスクもあります 。
実際、ドネペジル投与中の洞徐脈や失神発作が報告されており、FDAも**「コリンエステラーゼ阻害薬使用中は徐脈・房室ブロックに注意」との警告を発しています 。
したがって、徐脈傾向のある患者、心臓の伝導系に既往のある患者(洞不全症候群やAVブロックなど)には慎重投与が原則です。
必要に応じて心電図モニターを行い、脈拍<50/分程度に下がるようであれば減量・中止を検討します。
また、迷走神経刺激により失神だけでなくQT延長**のリスク増加も指摘されており注意が必要です 。
加えて、コリンエステラーゼ阻害により末梢血管抵抗が減少するため軽度の血圧低下が起こる場合もあります。起立性低血圧がみられれば転倒リスクになるため注意しましょう。
中枢神経系
不眠(入眠障害、悪夢を見る)や興奮、頭痛、めまいなどが報告されています。
特にドネペジルは中枢への移行が良いためか、睡眠障害が出現しやすい印象があります。
悪夢を見るとの訴えがある場合、就寝前→朝食後の服用に変更することで改善することがあります。
またコリン作動性過剰はけいれん発作を誘発する可能性も理論上指摘されています (もっともAD自体がけいれんを起こしやすい疾患であり、因果関係の評価は難しいところです)。
いずれにせよ神経学的な副作用が出現した場合は無理せず減量・休薬し、症状の推移を見ます。
呼吸器系
コリン作動薬は気道分泌や気管支収縮を促すため、COPDや喘息を悪化させるおそれがあります 。
重度の喘息患者などにはChEIは相対禁忌とされる場合もあり、少なくともコントロール不良の喘息・肺疾患患者では慎重な評価が必要です。
泌尿器系
コリン作動性により膀胱収縮が促進されるため、尿失禁や尿意切迫が悪化する可能性があります。
実際、ドネペジル開始後に尿失禁が増悪したとの報告もあります 。
排尿障害(前立腺肥大による閉尿など)がある場合にはコリンエステラーゼ阻害薬が膀胱出口部の括約筋弛緩を誘発し得るため注意が必要です 。
消化性潰瘍
コリン作動性は胃酸分泌を高めるため、消化性潰瘍や消化管出血のリスクになります 。
NSAIDs併用中の患者や潰瘍の既往がある患者では、投与中は消化器症状の訴えに注意し、必要に応じて胃保護剤を併用します。
体重減少
前述のように食欲低下が続くと体重減少につながります。
特に日本人を含むアジア人高齢者はやせ型の方が多く、ChEI投与でさらに体重が減って虚弱が進行する恐れがあります。
米国で23mgドネペジル投与試験を行った際、10mg群と比べ体重が7%以上減少した患者の割合が有意に高かったとのデータがあります 。
実臨床でも、ChEI投与開始後に「なんとなく食が細くなった」「数か月で数kg痩せた」というケースは珍しくありません。定期的な体重測定を行い、著明な減少が見られた場合は投与継続の是非を慎重に判断すべきです。
以上が主な副作用ですが、他にも筋肉痛・筋けいれん(筋線維に対するAch作用)、流涎(よだれ)や発汗過多(副交感亢進)、発疹・皮膚症状(特にパッチでは接触性皮膚炎に注意)など様々な副反応が報告されています。
総合すると副作用発現率はChEI全体でプラセボの約1.5倍にのぼり 、投与群の約3割が何らかの副作用を経験し、そのうち数%は中止に至るとされています 。
各薬剤間の忍容性を比較した試験では、リバスチグミン経口剤はドネペジルより中止率が高い(副作用が多い)ことが示唆されており 、これはリバスチグミンの消化器症状発現率の高さによるものと考えられます。
ただし先述のようにリバスチグミンではパッチ製剤への切り替えで忍容性が改善するため、このデータをそのまま現在のパッチ主体の臨床に当てはめることはできません。
ガランタミンはドネペジルよりやや嘔気発現が多いとの報告もありますが、大差はないとの見方が一般的です 。
ドネペジルは忍容性良好とされますが、それでも日本人では開始用量3mgから慎重に漸増する処方設計がとられることがあります。
最終的には患者個々人の感受性差が大きいため、「合う薬」を見極めることが重要です。
一剤で副作用が強く出た場合、別のChEIなら問題なく使えるケースもしばしば経験されます。
例えばドネペジルで嘔気が強かった高齢女性が、ガランタミンに変更したところ副作用なく継続できた、といった報告もあります。
エビデンス上明確な推奨はありませんが、実臨床では他剤へのスイッチも有効な手段となりえます 。いずれにせよ、副作用モニターとマネジメントは薬剤師を含む医療チームの腕の見せ所であり、少しの工夫で治療を継続できるケースも多いことを覚えておきましょう。
実臨床での使い分けの考察
最後に、現場薬剤師の視点から3剤の使い分けや留意点について整理します。上述の通り有効性に大きな差はないため、患者個々の状況や副作用プロファイルを考慮して選択・調整することになります。
副作用プロファイルによる選択
患者の体質や合併症によって、適する薬剤が異なります。
例えば消化器症状を絶対避けたい場合は、初期からリバスチグミンパッチを選択するのも一案です(経口より胃腸障害が少ないため) 。
逆に徐脈・失神リスクが懸念される心疾患患者では、回避すべき明確なエビデンスはないものの念のためChEI全般慎重投与となります。
どうしても投与するなら短時間型で調節しやすいガランタミンを選ぶ、という考え方もあります。
体重減少しやすい方では、ドネペジルやリバスチグミンは食欲低下を招きやすいので注意が必要です。
また皮膚が敏感な方ではパッチでかぶれが出る可能性があるため、その場合は経口剤への変更を検討します。
投与回数・剤形による選択
服薬管理が難しい一人暮らしの患者や、介護者の負担軽減を図りたい場合は投与回数が少ない剤が望ましいです。
ドネペジルは1日1回で済み、さらにOD錠で服薬補助しやすいという利点があります。
リバスチグミンパッチは貼り替えが1日1回必要ですが、経口内服が不要な点で嚥下困難例などに絶大なメリットがあります。
また服薬への抵抗(拒否)が強い認知症患者には、こっそり食事に混ぜられるドネペジルのゼリー剤や、貼付剤であるリバスチグミンが有用でしょう。
逆に皮膚トラブルがある場合には無理にパッチを使わず経口剤を選びます。剤形の選択は患者と介護者の希望も踏まえて柔軟に行います。
臨床症状・合併疾患による使い分け
前述のようにLewy小体型認知症(DLB)ではドネペジルが有効性を示しており、日本では適応も取得しています 。
DLB患者では幻視や認知機能の改善目的でドネペジルが第一選択となります。
またパーキンソン病認知症(PDD)では海外でリバスチグミンが適応承認されており、実臨床でも運動症状を悪化させず認知機能を改善できる薬剤としてリバスチグミンが選ばれる傾向があります(日本ではPDD適応はありませんがOff-labelで使われることもあります)。
血管性認知症に対するエビデンスは限られますが、ガランタミンやドネペジルが注意・実行機能面を多少改善するとの報告もあり、一部で使用されています (ただし適応外使用となります)。
このように認知症のタイプにより使い分けるシナリオもあります。
一方、重度アルツハイマー病ではコリンエステラーゼ阻害薬単独では効果が限定的なため、通常はNMDA受容体拮抗薬メマンチンとの併用療法が考慮されます 。
ドネペジルは重度ADにも適応拡大されていますが、実臨床では中等度以上になればメマンチン併用が一般的です。
コリンエステラーゼ阻害薬同士の併用は禁忌(作用重複による副作用増強のみでメリットなし)なので、どれか1剤を選択する必要があります。
先発医薬品と後発医薬品の使い分けについては、現在3剤ともジェネリックが入手可能であり、薬価面の負担軽減も踏まえて適宜ジェネリックの使用も問題ありません。
特に高齢者では薬剤費負担がQOLに影響する場合もあるため、患者や家族の希望に沿った形で処方提案を行います。
スイッチング(変更)のタイミング
あるChEIで十分な効果が得られない、あるいは副作用で増量できない場合、別のChEIに変更することがあります 。
例えばドネペジル10mgまで増量したが効果実感に乏しいケースで、ガランタミンに変えたところADL面で改善が見られた、といった報告もあります。
また副作用面でも、ドネペジルでどうしても悪心が引かない患者がガランタミンでは平気だったり、その逆もありえます。
これは薬理学的に明確な理由づけは難しいですが、各薬剤のわずかな作用差や薬物動態差が患者ごとに影響するためと思われます。
従って**「ひとつ合わなくても他が合う可能性がある」**ことは念頭に置き、必要なら主治医に薬剤変更を提案するのも薬剤師の役割です。
変更時は洗い替え(一方を中止し翌日から他剤開始)が多いですが、場合により漸減・漸増をオーバーラップさせることもあります。いずれにせよ変更後は改めて数週間~ヶ月スケールで効果判定を行います。
以上のように、コリンエステラーゼ阻害薬の使い分けは**「患者ごとにオーダーメイド」**と言えるほど多岐にわたります。表に簡単に各薬剤の特徴をまとめます。
薬剤選択に正解はありませんが、このようなポイントを踏まえチーム医療で最適解を探っていくことが現場では大切です。
薬剤師は各薬剤の特性を理解し、患者・家族の状況を把握した上で処方医に有益な提案や副作用対策の助言を行う役割が期待されています。
まとめ
コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)は、アセチルコリン仮説にもとづき開発されたアルツハイマー病治療の第一選択薬であり、その登場は認知症医療に新たな光をもたらしました。
各薬剤の開発には、偶然の発見や植物由来物質の応用など興味深い経緯があり、薬理作用もそれぞれ特徴的です。
臨床試験のエビデンスからは認知機能・ADL・BPSDの進行を緩やかにしうることが示唆されており 、患者のQOL維持・介護負担軽減に一定の貢献が期待されます。
ただし効果は決して劇的ではないため、過度な期待は禁物であり、「現時点で利用可能なベストではあるが万能薬ではない」というスタンスで臨むことが肝要です。
また薬機法の観点からも、エビデンスに基づきつつ効果を誇張しない適正な情報提供が求められます。
副作用については消化器症状を筆頭に様々なコリン性副作用が出現しうるものの、適切な用量管理や剤形の工夫によって多くは対処可能です 。
薬剤師は副作用モニタリングと患者・家族へのアドヒアランス支援で重要な役割を担っています。
また3剤間に有効性の有意差はなく 、患者ごとの状態に応じたオーダーメイドの使い分けが実践されています。
新たに認知症治療薬が開発された場合も、これまで蓄積したChEI使用の知見は必ず役立つでしょう。
近年ではコリンエステラーゼ阻害薬に加えて、NMDA受容体拮抗薬メマンチンとの二重療法が中等度以降のADで標準的となりつつあります。
またADの根本治療を目指す抗アミロイドβ抗体など新薬も登場し始めています。
しかし、軽度~中等度AD患者の中核症状・周辺症状に幅広く作用し、生活期を支える薬剤として、コリンエステラーゼ阻害薬が果たす役割は今なお大きいものがあります。
認知症治療ガイドラインでも依然として第一選択薬として位置付けられており、その適正使用とケアへの活用は我々医療従事者に課せられた使命と言えます 。
この記事が、現場で日々奮闘されている薬剤師の皆さまの知的好奇心を刺激し、コリンエステラーゼ阻害薬について更なる理解を深める一助となれば幸いです。
そして得られた知識を生かして、患者さんとご家族に寄り添った薬物療法の支援に役立てていただければと思います。
「過去の知見を踏まえ、今できる最善を提供する」——認知症治療におけるコリンエステラーゼ阻害薬の活用が、これからもエビデンスと経験に基づき適切に発展していくことを期待しています。

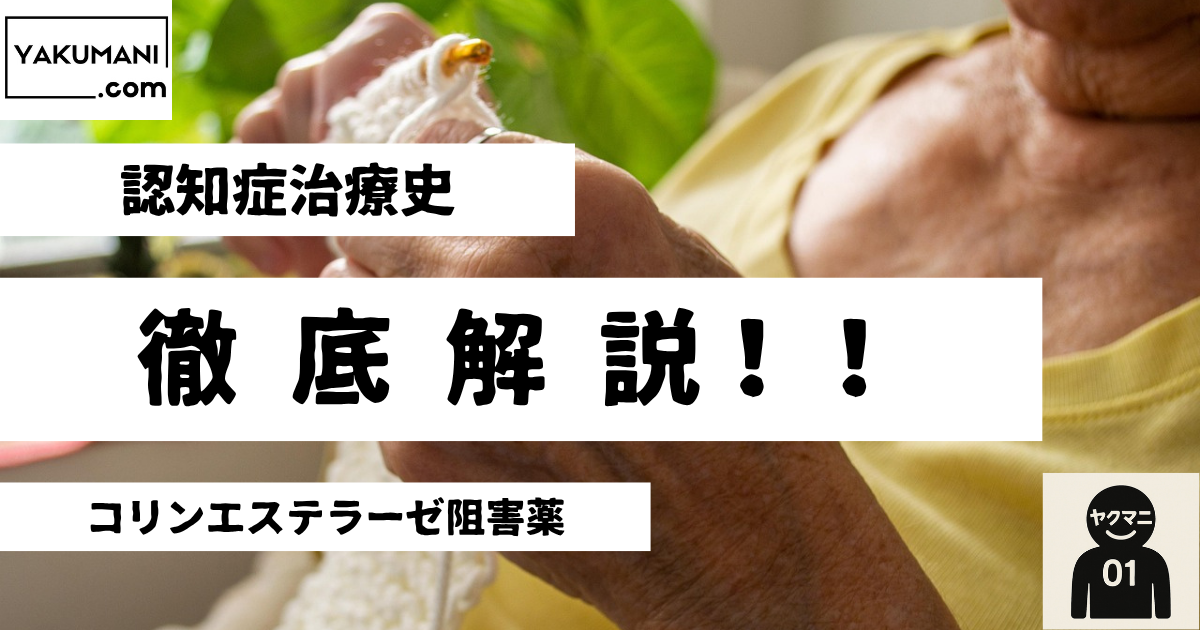
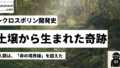
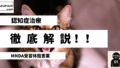
コメント