「母が自分を忘れた」──その想いが、認知症治療の転機をもたらしました。
本回では、アセチルコリン仮説の誕生と、ドネペジルなどの治療薬開発の舞台裏を紹介します。
アセチルコリン仮説とコリンエステラーゼ阻害薬の登場(ドネペジル、リバスチグミンなど)
1990年代、中核症状に挑む初めての薬が誕生します。
アルツハイマー病の病態研究が進む中で注目されたのが「アセチルコリン仮説」です。
脳内の神経伝達物質アセチルコリンは記憶や学習に深く関与しますが、アルツハイマー型認知症ではこのアセチルコリンを作る神経細胞が著しく減少していました。
そこで「残存するアセチルコリンを増やせば認知機能低下を改善できるのではないか?」と考えられたのです。
この仮説のもと1980年代に世界中で創薬研究が本格化し、脳内のアセチルコリン分解酵素(コリンエステラーゼ)を阻害することでアセチルコリン量を増やす薬が模索されました。
研究当初は失敗も多く、「老年期認知症に効く薬など開発不可能」との声もありました。
しかし日本のエーザイなど粘り強い開発チームの努力により、有効な化合物が見出されていきます。
エーザイの杉本八郎博士は、自身の母親が認知症を患い自分のことすら認識できなくなった経験から「なんとしても効く薬を作る」との使命感に燃え、この仮説を信じ抜いて研究を続けたといいます。
こうして1993年、米国で世界初のコリンエステラーゼ阻害薬**「タクリン」(商品名コグネックス)が承認されました。
タクリンは認知症による記憶・思考障害を標的とした初の薬でしたが、肝障害など副作用も多く、普及は限定的でした。
しかしその後を追うように改良型の薬が次々と登場します。
1996年には「ドネペジル」(商品名アリセプト)が米FDAに承認され、日本でも1999年に認可されました。
ドネペジルは国内製薬企業が開発した初の認知症治療薬として社会的にも大きな注目を集め、軽度から重度まで幅広いアルツハイマー病患者に適応を持つ薬へと成長します。
続いて1998年にリバスチグミン(エクセロン)、2000年にガランタミン(レミニール)が欧米で承認され、それぞれ日本でも2000年代前半に使えるようになりました。
これら3つのコリンエステラーゼ阻害薬は作用機序こそ似通っていますが、肝臓代謝か腎排泄かといった薬物動態や、錠剤・パッチ剤など剤形の違いがあります。
いずれも症状の進行を一時的に緩和する「対症療法薬」であり、病気自体を治すものではありませんが 、「認知症に効く薬がある」**という事実は患者・家族に希望をもたらしました。
臨床的な効果は**「穏やかな覚醒」とも評されます。
例えばドネペジルの場合、投与から数週間で多少物忘れが改善し会話に積極性が出る患者がいる一方、全く効かない人もいます。
作用は一時的で、半年~1年ほどで再び緩徐な悪化が進行してしまいます 。
それでも当時としては画期的であり、欧米では1990年代後半から2000年代初頭にかけてこれら4種類の薬が相次いで承認されました。
日本でも2000年代に入りこれらが出揃い、認知症診療の在り方が一変します。
「認知症だけど薬で良くなるかもしれない」**という期待が医療者・介護者に共有され、早期診断・早期治療の機運が高まりました。
実際、ドネペジル発売後は物忘れ外来に受診する高齢者が増え、診断率の向上にも繋がったとされています。
もっとも、コリンエステラーゼ阻害薬は根本治療ではないため**「効き目がはっきりしない」「いつまで続けるべきか判断に迷う」といった悩みもつきまといます。
それでも「何もできないよりはマシ」という当事者・家族の心理もあり、現在に至るまで認知症治療の第一選択薬として定着しています。
なお、日本発のドネペジルは全世界で使用されるベストセラー薬となり、発売元のエーザイ社にとっても大きな飛躍となりました。
その開発秘話として、杉本博士らチームの「執念」と「家族への想い」は語り草となっています。
このように、コリンエステラーゼ阻害薬の登場は認知症治療における画期であり、「認知症は治療可能である」という時代の幕開け**となったのです。
“記憶を取り戻す薬”が登場した一方で、新たな病態に目を向けた研究も進んでいました。
次回は、“興奮毒性”という異なるメカニズムに挑んだメマンチンの歴史をたどります。

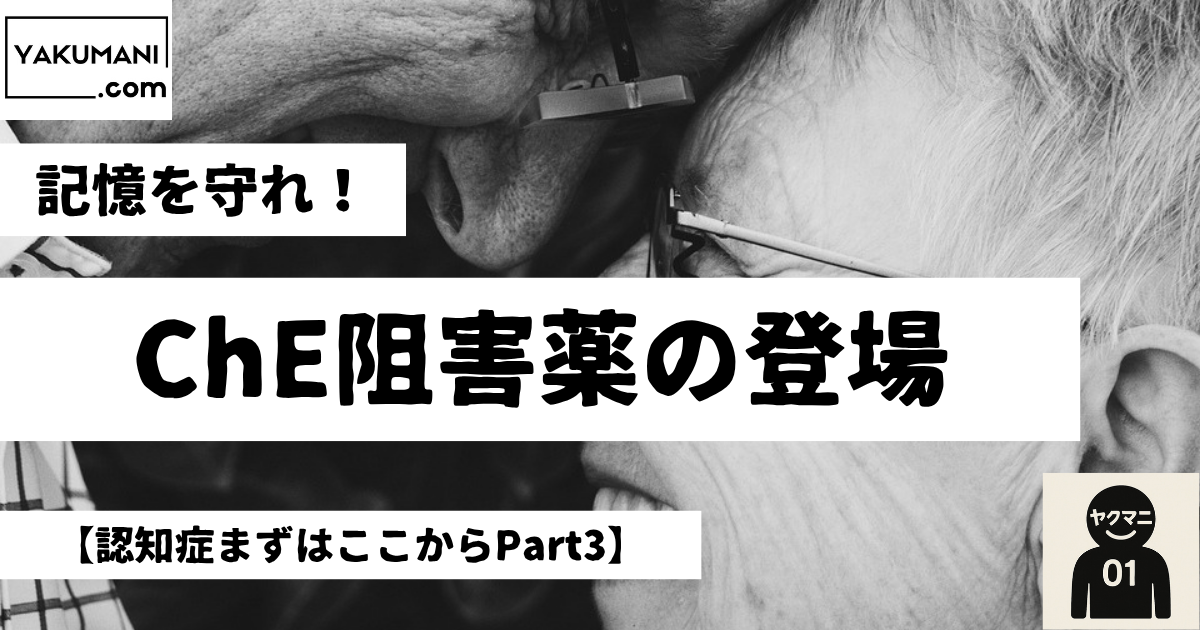
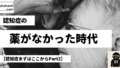
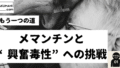
コメント