暴走する神経を鎮める“脳のブレーキ役”──メマンチン。
本記事では、グルタミン酸とNMDA受容体をめぐる仮説と、メマンチン開発の意外なルーツに迫ります。
メマンチンとNMDA受容体の関係
第2の認知症治療薬として登場したのが「メマンチン」です。コリンエステラーゼ阻害薬が軽~中等度のアルツハイマー病向けであるのに対し、メマンチンは中等度~重度アルツハイマー病に適応を持つ薬剤です。その作用機序の鍵となるのが脳内のNMDA受容体という分子です。アルツハイマー病の脳ではグルタミン酸という興奮性伝達物質が過剰に放出され、神経細胞が慢性的に刺激され続ける**「興奮中毒(エキソトキシシティ)」の状態に陥っていることがあります。この過剰興奮は細胞死を招き、認知機能悪化の一因になると考えられました。NMDA受容体はグルタミン酸の主要な受容体であり、メマンチンはこのNMDA受容体に結合して過剰な刺激をブロックする作用を持ちます。いわば「脳のブレーキ役」**として働き、神経細胞を興奮毒性から守るのです。
メマンチンの歴史は古く、最初の合成は1960年代(1963年)にまで遡ります。当初は糖尿病治療薬として開発されたものの効果がなく、その後中枢神経に作用する物質であることが1970年代に判明しました。ドイツの製薬会社メルツ社がこの物質に着目し、脳卒中後の脳障害や認知症への応用研究を進め、1989年にはドイツで認知症治療薬として承認を取得します 。欧州全域で承認されたのは2002年、米国FDA承認は2003年と、2000年代前半になってようやく世界的に認知症治療薬として広まりました 。日本でも2004年にメマンチン(商品名メマリー)が発売され、コリンエステラーゼ阻害薬に次ぐ第2の作用機序を持つ認知症治療薬として注目を集めました。
臨床効果の特徴は「症状安定化」です。中等度以上に進行したアルツハイマー病患者にメマンチンを投与すると、問題行動や日常生活動作の悪化スピードが遅くなることが示されています。具体的には、興奮・攻撃性の軽減や、食事や着替えなど基本的ADLの維持においてプラセボ群より良好な経過を辿るというデータがあります。ただし効果の程度は「控えめ(modest)な改善」と表現され、劇的な回復をもたらすものではありません。軽症の段階では有効性が確認されておらず、効果は中等度~重度に限られる点も重要です。副作用は比較的少ないものの、眠気やめまいが出現することがあり、高用量では一時的に認知機能が悪化する例も報告されています。これはメマンチンのNMDA受容体遮断作用が一時的に正常な神経伝達も妨げるためと考えられますが、適切な量であればすぐ耐性ができ問題ないとも言われます。
メマンチンはコリンエステラーゼ阻害薬との併用もしばしば行われます。作用機序が異なるため相乗効果が期待され、実際、ドネペジルとの併用療法は単剤より若干良好との報告もあります。一方で軽症例には無効なことから、**「ある程度進んだらコリン薬に代えてメマンチン」**という使い分けもなされています。いずれにせよメマンチンの登場により、認知症治療薬の選択肢は広がりました。コリンエステラーゼ阻害薬と合わせ、約20年近くにわたり認知症薬はこの2カテゴリーに留まっていたことになります。
メマンチンの登場で、認知症治療は「重度」にもアプローチ可能となりました。
次回は、ケア現場の最大の課題、BPSD(周辺症状)との闘いの歴史をひも解きます。

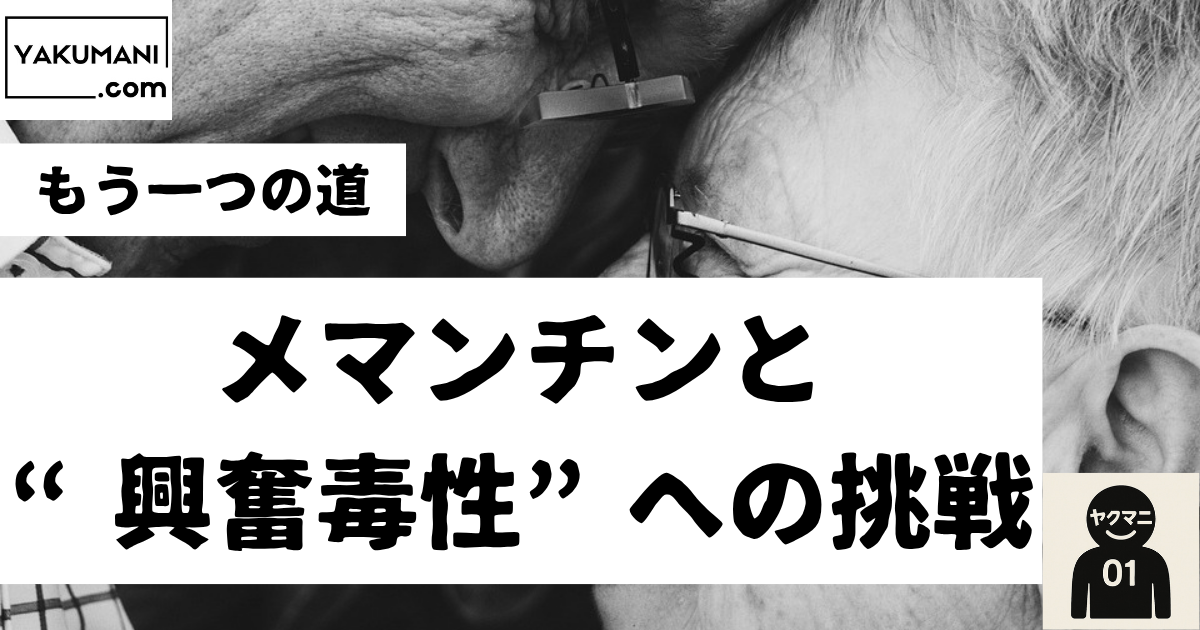
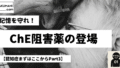
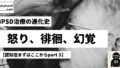
コメント