はじめに:
SGLT2阻害薬(Sodium-Glucose Cotransporter 2阻害薬)は、比較的最近登場した経口血糖降下薬であり、糖尿病治療のみならず心血管・腎保護効果にも注目される新たな薬剤クラスです。本稿では、薬剤師を対象にこのSGLT2阻害薬の歴史的発展をまとめます。19世紀のフロリジンの発見からSGLT輸送体の解明、グリフロジン系薬剤の開発、そして日本国内での承認と主要なエビデンスの積み重ねによる適応拡大とガイドラインの変遷に至るまでを概観します。
フロリジンから始まるSGLTの発見史
SGLT2阻害薬の源流は、19世紀に遡るフロリジン(Phlorizin)の発見に端を発します 。1835年、フランスでリンゴの樹皮からフロリジンという化合物が単離され、その後の1933年にフロリジンには尿中への糖排泄(グルコース尿)を誘発する作用があることが報告されました 。この「フロリジン誘発性グルコース尿」の現象は当初、糖尿病治療への応用には結びつかず、しばらくの間は単なる薬理学的興味として扱われていました。
転機が訪れたのは1980年代後半です。米国のRalph DeFronzoらにより「糖毒性(グルコーストキシシティ)」の概念が提唱され、高血糖そのものが糖尿病の病態悪化に寄与することが認識されました 。高血糖による有害作用を減らす新しい発想として、「尿中へ糖を排泄させることで血糖を下げる」というコンセプトが再評価され始めます。同じ頃の1987年には、動物実験でフロリジン投与が血糖値を低下させることが確認され 、フロリジンの持つ作用機序への関心が高まりました。ただしこの時点でも、フロリジンがなぜ尿糖を増やすのかという詳細なメカニズムは未解明であり、創薬につなげるにはさらなる研究が必要でした 。
そのブレークスルーとなったのが1990年代の初頭です。1994年に金井(Kanai)らの研究グループが、腎臓近位尿細管に存在するナトリウム-グルコース共輸送体のサブタイプ「SGLT2」をコードするDNAの単離に成功しました 。さらに、その遺伝子から発現させたタンパク質が腎臓でのグルコース再吸収を担う共輸送体であることを突き止め、ついにフロリジンの作用標的が明確になったのです 。この発見により、長年謎であった「グルコースの尿中排泄効果」の仕組みがSGLT(ナトリウム依存性グルコース輸送体)の阻害に起因することが理解され、フロリジンをヒントにした糖尿病治療薬開発が現実味を帯びてきました。
SGLT2阻害薬の開発経緯と主要薬の登場
SGLT2という分子標的の同定を受けて、各製薬企業はフロリジンをリード化合物として改良を重ね、選択的で経口活性を持つ創薬候補の開発に乗り出しました。まず、日本の田辺製薬(現 田辺三菱製薬)は1999年、経口投与可能なフロリジン誘導体「T-1095」の創製に成功し、動物モデルで糖尿病に対する有効性を報告しました 。T-1095自体は臨床応用に至らなかったものの、この成果は各社の研究開発を大きく後押しし、2000年代には複数の候補化合物が臨床試験段階へと進みます。
そして2010年代前半、ついにSGLT2阻害薬が医療現場で使える薬剤として結実しました。世界初のSGLT2阻害薬として承認を取得したのはダパグリフロジン(Dapagliflozin)で、2012年に欧州で2型糖尿病治療薬として認可されました 。これに続き、カナグリフロジン(Canagliflozin)は2013年3月に米国FDAから承認され(米国初のSGLT2阻害薬)、エンパグリフロジン(Empagliflozin)は2014年に欧州および米国で承認を受けました 。こうした「グリフロジン(-gliflozin)」系薬剤はフロリジンの化学構造を元に改良を加えたもので、選択的に腎のSGLT2を阻害して尿糖排泄を促進し、血糖降下作用を発揮します。
一方、日本国内でも独自に開発されたSGLT2阻害薬が誕生しました。アステラス製薬と興和創薬が手掛けたイプラグリフロジン(Ipragliflozin)は国内企業創製のSGLT2阻害薬で、後述のように2014年に日本初承認を果たします 。さらに、中外製薬と興和のトホグリフロジン(Tofogliflozin)や、大正製薬のルセオグリフロジン(Luseogliflozin)といった国内開発品も、グローバル品に遅れず実用化されました。こうして主要なSGLT2阻害薬が次々に登場し、世界と日本の糖尿病治療に新たな選択肢を提供することになったのです。
日本での承認経過
日本ではSGLT2阻害薬の導入が迅速に進みました。臨床第I相試験は2006年頃から国内でも開始され、第一号となったイプラグリフロジン(商品名:スーグラⓇ)は2014年1月17日付で2型糖尿病治療薬として製造販売承認を取得し 、同年4月から発売されました。これは世界的に見ても非常に早いタイミングであり、欧米に先駆けて日本初のSGLT2阻害薬が実現した形です。当時の日本糖尿病学会は、新規機序の薬剤導入に際してその安全対策の必要性から「SGLT2阻害薬の適正使用に関するRecommendation」を速やかに策定・公表しています 。
イプラグリフロジンに続いて、2014年春から夏にかけて他の薬剤も相次いで承認されました。まずダパグリフロジン(フォシーガⓇ)とトホグリフロジン(デベルザⓇ/アプルウェイⓇ)およびルセオグリフロジン(ルセフィⓇ)の3成分が2014年3月24日付で承認され 、続いて田辺三菱製薬オリジンのカナグリフロジン(カナグルⓇ)が2014年7月4日付で承認、販売開始となりました 。さらにドイツ・ベーリンガーインゲルハイム社のエンパグリフロジン(ジャディアンスⓇ)も日本で臨床試験が行われ、2014年12月26日に承認を取得しています 。結果として2014年内に計6成分ものSGLT2阻害薬が出揃い、日本は世界でも有数のSGLT2阻害薬充実国となりました(2014年発売:イプラグリフロジン、ダパグリフロジン、トホグリフロジン、ルセオグリフロジン、カナグリフロジン、エンパグリフロジン) 。その後、各薬剤の配合錠(特にDPP-4阻害薬との合剤)が2017年以降に順次発売されるなど 、SGLT2阻害薬は日本の糖尿病治療に急速に浸透していきました。
承認された適応症は当初「2型糖尿病」のみでしたが、一部製剤では後に適応拡大もなされています。例えばイプラグリフロジンやダパグリフロジンは1型糖尿病患者へのインスリン併用療法にも適応追加(日本では2018年以降順次)されました 。もっとも1型糖尿病への使用は欧州ではBMI条件付き承認、米国では未承認となっており、国内でも添付文書上はケトアシドーシス(特に尿糖排泄に伴う「ユージョナルケトアシドーシス」)リスクに十分な注意が喚起されています 。こうした制限付き適応もありますが、基本的にはまず2型糖尿病治療薬として日本で広く受け入れられ、多くの患者さんに使用され始めました。
主要臨床試験の成果と意義(EMPA-REG OUTCOME、CREDENCE、DAPA-HF 他)
SGLT2阻害薬の真価が世界的に注目される契機となったのが、糖尿病患者を対象に実施された一連の大規模臨床試験の結果です。もともと2008年以降、FDAの規制により新規糖尿病薬には心血管イベントへの影響を検証するアウトカム試験が課されるようになり 、SGLT2阻害薬も例外なく各薬剤で長期の心血管アウトカム試験が行われました 。その第一報として2015年に発表されたのが、エンパグリフロジンの「EMPA-REG OUTCOME試験」です 。
- EMPA-REG OUTCOME試験 (2015) – この試験は、心血管リスクの高い2型糖尿病患者7,020名を対象に、エンパグリフロジン10mgまたは25mg投与群とプラセボ群を比較したものです 。主要評価項目の3点複合アウトカム(心血管死+非致死性心筋梗塞+非致死性脳卒中)の発生が、エンパグリフロジン群でプラセボ群より有意に14%減少(ハザード比0.86)しました 。特筆すべきは、心血管死が38%減少(HR 0.62)し、全死亡も32%減少(HR 0.68)、さらに心不全による入院も35%減少(HR 0.65)といずれも著明なリスク低下を示した点です 。従来の糖尿病治療薬では見られなかった心血管イベント抑制効果が初めて示されたことで、本試験結果は医学界に大きな衝撃を与えました 。この成果により、SGLT2阻害薬は単なる血糖降下薬に留まらず心血管アウトカム改善薬としての評価を獲得したのです。
- CANVAS試験 (2017) – 続いて報告されたのがカナグリフロジンの心血管アウトカム試験CANVASです 。対象は2型糖尿病患者10,142名で、EMPA-REGほど高リスク例に限定せず、一部一次予防的な患者(心血管疾患既往のないが危険因子を有する例)が34%含まれていた点が特徴です 。結果は、主要複合アウトカムで**14%のリスク低下(HR 0.86)を示し 、心血管死に有意差はなかったものの、心不全入院は33%減少(HR 0.67)しました 。EMPA-REGよりリスクの低い集団を含むため効果の絶対値は小さめでしたが、本試験によりクラスエフェクト(薬剤クラス全体の効果)**としてSGLT2阻害薬の心血管イベント抑制が裏付けられました。なおCANVASでは、カナグリフロジン群で下肢切断の頻度増加という所見も報告され注意喚起がなされています(機序は不明ですが現在は添付文書で重篤な末梢循環障害患者への投与注意などが記載)※。
- DECLARE-TIMI 58試験 (2018) – ダパグリフロジンを用いた心血管アウトカム試験DECLAREも報告されました。対象17,160例中約6割が心血管疾患非合併の一次予防目的患者であり 、3点複合アウトカムの有意な低下は認めませんでした。しかし、心不全入院の抑制傾向は一貫しており、事前に計画された解析では「心不全入院+心血管死」の複合アウトカムを有意に**17%減少(HR 0.83)**させています 。この結果は、リスクの高い群ではないと心血管死抑制まで至らないものの、心不全発症予防薬としてのSGLT2阻害薬の有用性を示すものといえます。
以上3試験はいずれも2型糖尿病患者を対象とした研究ですが、主要評価項目として一貫して心不全入院のリスク低下が示された点は極めて重要です 。従来、糖尿病治療薬が心不全リスクに及ぼす影響については不明瞭でしたが、SGLT2阻害薬クラスは明確に心不全発症を減らすエビデンスが揃ったのです。この知見は後述の心不全領域での適応拡大に直結していきます。
- CREDENCE試験 (2019) – SGLT2阻害薬が腎臓にもたらす利益を実証した初の大規模試験がCREDENCEです。2型糖尿病と顕性アルブミン尿を伴う慢性腎臓病患者4,401例を対象に、カナグリフロジン100mg群とプラセボ群を比較しました 。平均追跡2.6年で主要腎複合アウトカム(末期腎不全への移行、血清クレアチニン倍増、腎不全による死亡)の相対リスクを34%低減(HR 0.66, p<0.001)し、特に透析や腎移植が必要となる末期腎不全への進行を32%抑制(HR 0.68, p=0.002)しました 。心血管死のリスクも有意に低下し、副次評価項目の結果を含め試験は予定より早期に中止されるほどの有益性が示されています 。このCREDENCEの成果は、糖尿病性腎症の進行抑制においてACE阻害薬/ARB以来のブレークスルーと称され、腎臓学領域で大きな反響を呼びました 。SGLT2阻害薬が腎保護薬としても有望であることが証明されたのです。
- DAPA-HF試験 (2019) – 上記までは糖尿病患者を対象にした試験でしたが、SGLT2阻害薬は糖尿病の有無を問わず心不全そのものの治療薬になり得ることを示したのがDAPA-HFです 。この試験では、HFrEF(左室駆出率40%以下)の慢性心不全患者4,744例(約58%が非糖尿病)に対し、ダパグリフロジン10mgまたはプラセボを投与しました 。その結果、主要評価項目である「心不全悪化(入院または緊急受診による静脈治療)または心血管死」の発生が有意に抑制されました(ハザード比0.74, p<0.001)と報告されています※。DAPA-HFは、SGLT2阻害薬が糖尿病を持たない心不全患者にも有効であることを示した初めての大規模臨床試験であり 、従来の心不全薬とは全く異なる機序で予後改善をもたらす点で非常に意義深いものです。続いてエンパグリフロジンでも**EMPEROR-Reduced試験 (2020)**にてHFrEF患者で同様の有意な予後改善効果(主要評価項目リスク18%低減)が確認され、クラス効果として心不全治療に有用であることが確実なものとなりました 。
これら以外にも、心不全合併糖尿病患者を対象とした小規模試験や、**HFpEF(左室駆出率が保たれた心不全)**に対する大規模試験(EMPEROR-Preserved試験にてエンパグリフロジンが主要評価項目21%減少、DELIVER試験にてダパグリフロジンが主要評価項目18%減少を報告)など、SGLT2阻害薬の適用範囲を広げるエビデンスが次々と蓄積されています 。特にHFpEFに対しては有効性が示された初の経口薬として注目され、従来治療が難しかった領域への貢献も期待されています。
適応拡大の流れと現在の位置づけ(2型糖尿病、心不全、CKDなど)
上述の臨床試験結果を受け、SGLT2阻害薬の適応症は世界的に拡大しつつあります。もともとは2型糖尿病の治療薬として承認された本クラスですが、現在ではエビデンスに基づき心不全や**慢性腎臓病(CKD)**への適応追加が相次いでいます。日本においても、2020年以降にこれら適応拡大が現実のものとなりました 。
まず心不全については、DAPA-HFとEMPEROR-Reducedの成果を受け、2020年に日本でダパグリフロジンとエンパグリフロジンが「慢性心不全(HFrEF)」の適応を取得しました 。例えばダパグリフロジン(フォシーガⓇ)は**「2型糖尿病の有無を問わず、標準治療下の慢性心不全患者に使用できる心不全治療薬」として承認され、エンパグリフロジン(ジャディアンスⓇ)も同様にHFrEF適応追加されています 。これにより、SGLT2阻害薬はACE阻害薬、β遮断薬、MRA(抗アルドステロン薬)に次ぐ第4の心不全基盤治療**として位置づけられるようになりました。
さらに、2022年~2023年にはHFpEF(保存収縮能心不全)に対する適応も認められています 。エンパグリフロジンとダパグリフロジンはいずれもHFpEF患者を対象とした国際試験で有効性が示され、欧米と同様に日本でも**「左室駆出率を問わない慢性心不全」**として適応が拡大されました 。この結果、現在では糖尿病の有無や心機能に関わらず、多くの心不全患者でSGLT2阻害薬が治療選択肢となっています。「心不全=入院を繰り返す難治の病」という従来のイメージに対し、SGLT2阻害薬の登場は予後改善への新たな希望をもたらしたと言えるでしょう。
腎臓領域でも適応拡大が進みました。ダパグリフロジンはCREDENCEやその後のDAPA-CKD試験(2020年発表、糖尿病の有無を問わずCKD患者で腎アウトカム改善を示した試験)の結果を踏まえ、2021年8月に日本で「慢性腎臓病(末期腎不全または透析中を除く)」の効能・効果追加承認を取得しました 。これは日本で初めて糖尿病がなくても使用可能なCKD治療薬として承認された例であり、SGLT2阻害薬が腎臓内科領域へ本格的に踏み出した瞬間でした。実際の添付文書上も、「慢性腎臓病」の項において臨床試験で組み入れられた患者背景(原疾患や併用薬、腎機能など)を理解の上で適応患者を選択する旨が記載され、腎専門医と一般医家双方への周知がなされています 。
エンパグリフロジンについても、2024年2月に日本でCKD適応が追加承認されており 、複数のSGLT2阻害薬が腎不全進行抑制薬として使える状況になってきました。とりわけ糖尿病性腎症のみならず非糖尿病性のCKDに対しても有効性が確認された点は重要で、末期腎不全への進行阻止や心血管イベント予防に資する新たな治療戦略として期待されています 。日本腎臓学会も「CKD治療におけるSGLT2阻害薬の適正使用に関するrecommendation」を公表し、エビデンスに基づいた適切な患者選択と安全管理のもとでSGLT2阻害薬を活用するよう推奨しています 。
もちろん、依然として2型糖尿病治療薬がSGLT2阻害薬の基本的な位置づけであることに変わりはありません。血糖降下作用そのものは、インスリン分泌能に依存せず尿糖排泄によって作用するという独特のもので、特にインスリン抵抗性を伴う肥満型2型糖尿病には体重減少効果もあって適した薬剤です 。一方で重度の腎機能低下では糖効果が減弱する点に注意が必要であり 、また尿路・性器感染症や脱水、ケトアシドーシスといった副作用リスクにも十分配慮しつつ使う必要があります 。日本糖尿病学会の適正使用指針でも、こうした副作用への注意事項や、手術前の休薬(※通常手術の3–4日前から休薬推奨)、高齢者ややせ型患者での慎重投与など、安全面の観点が詳述されています 。薬剤師としては、適応拡大による恩恵と潜在リスクの双方を理解し、患者さんに適した適正使用をサポートしていくことが求められます。
ガイドラインの動向(日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本腎臓学会 など)
SGLT2阻害薬の有用性が確立するにつれ、日本の各学会ガイドラインにもその位置づけが反映されてきました。以下に主な動向を紹介します。
- 日本糖尿病学会(JDS): 2型糖尿病治療におけるSGLT2阻害薬は、2019年頃からガイドラインやコンセンサスステートメント上で重要な選択肢として明示されるようになりました。JDSの「2型糖尿病治療アルゴリズム(第2版)」(2022年改訂)では、動脈硬化性心血管疾患を合併した2型糖尿病ではSGLT2阻害薬、次いでGLP-1受容体作動薬を推奨度の高い併用薬とする旨が記載されています 。また心不全を合併する2型糖尿病では第一選択薬にSGLT2阻害薬を位置付けるとの記載もあり 、エビデンスを踏まえて積極的に本クラスを活用すべきとの姿勢が示されています。実地診療においても、近年は初期治療からメトホルミンとSGLT2阻害薬を併用開始するケースや、インスリン抵抗性・肥満がある患者に優先的に投与するといった戦略が一般化しつつあります。またJDSは冒頭述べたようにSGLT2阻害薬の適正使用に関するRecommendationを2014年に策定以来定期改訂(直近は2022年改訂)しており、最新の2022年版では心不全・腎臓病など糖尿病以外の目的で使用する際は各専門学会の見解や国内外の添付文書を参考にするよう求めています 。これは、薬剤師にも各領域のガイドライン動向を把握した上で情報提供や指導を行うことの重要性を示唆しています。
- 日本循環器学会(JCS)・日本心不全学会: 心不全治療ガイドラインにおけるSGLT2阻害薬の扱いは近年劇的に変化しました。2017年改訂の「急性・慢性心不全治療ガイドライン」では、EMPA-REG等の結果を踏まえ**「心血管疾患ハイリスクの2型糖尿病患者では心不全予防目的でSGLT2阻害薬を使用推奨(クラスI, エビデンスA)」と初めて記載されました 。さらに2021年のFocus Update版では「心不全を合併した2型糖尿病患者の血糖管理でSGLT2阻害薬を使用推奨(クラスI, エビデンスA)」と拡充され 、糖尿病がある心不全患者では積極的に使うよう推奨されています。その後、HFrEFに対する有効性が確立し適応取得されたことを受け、現行(2022年改訂版)ガイドラインでは「症候性HFrEF患者の標準的治療薬の一つ」としてダパグリフロジンおよびエンパグリフロジンの投与がクラスIに位置付けられました 。HFpEFについても有効性示唆の新知見を受け適応が認められたため、ガイドライン上での記載更新が予定されています 。このように循環器領域では、SGLT2阻害薬はACE阻害薬等と並ぶ心不全の基本治療薬**との位置づけになっており、実際の処方現場でもHFrEF患者への投与が標準的実践となっています。2023年にはJCSと心不全学会の合同で「心不全治療におけるSGLT2阻害薬の適正使用に関するRecommendation」も発出され、安全な併用や休薬基準(例:利尿作用による脱水リスクに留意し、手術時は3日前から休薬等)について詳述されています 。心不全診療に携わる薬剤師も、これら学会資料に目を通し適正使用に貢献することが望まれます。
- 日本腎臓学会(JSN): 腎領域では、2022年11月に「CKD治療におけるSGLT2阻害薬の適正使用に関するRecommendation」が公開されました 。この背景には前述のCKD適応追加があり、「2型糖尿病の有無を問わずCKD患者にSGLT2阻害薬が使用可能となった」現状を受けた対応です 。同Recommendationでは、腎臓内科医のみならずプライマリケア医にも向けて、SGLT2阻害薬投与を推奨するCKD患者像(例:顕性蛋白尿を伴う糖尿病性腎症、eGFRが一定以上で維持期にあるCKD患者 など)や、投与時の留意点(例:利尿作用による脱水リスク管理、急性腎障害発症時の一時休薬判断 など)が示されています 。また日本糖尿病学会のRecommendationとも連携し、最新エビデンスに応じ随時改訂するとされています 。腎臓病領域では長らくRAA系阻害薬以外に有効な進行抑制策が乏しかったため、SGLT2阻害薬への期待は大きく、ガイドライン等でも「ステージ3~4の糖尿病性CKDに強く推奨」といった文言が近年追加されています。薬剤師は、糖尿病治療のみならずCKDの観点からもSGLT2阻害薬の役割を理解し、腎機能に応じた投与量管理やフォローアップ(定期的なeGFR・尿検査モニタリング等)について助言できることが理想です。
おわりに
SGLT2阻害薬は、その発見から実用化まで1世紀以上を要したともいえるユニークな薬剤です。19世紀のフロリジン研究に始まり、分子標的SGLT2の解明と創薬研究の結実によって21世紀に登場したこのクラスは、わずか数年で糖尿病治療の枠を超え、心不全や腎臓病領域へと適応を広げました。これはエビデンスに支えられた正当な展開であり、現在では多職種チーム医療の中で「糖尿病専門医だけでなく循環器内科医・腎臓内科医とも共有する薬剤」となっています。
薬剤師としては、SGLT2阻害薬の作用機序やエビデンス、適応症の範囲を正確に把握することはもちろん、副作用リスクや適正使用上の注意点についても十分に理解しておく必要があります。例えば脱水や尿路感染症の予防指導、低血糖リスク(他薬併用時)への配慮、そして緊急時のケトアシドーシス徴候の説明など、患者さんへの細やかなフォローが求められます。また、今後も新たなエビデンス創出によりガイドラインが更新される可能性がありますので、常に最新情報をアップデートしていく姿勢が大切です。
まとめると、SGLT2阻害薬の歴史は「古くて新しい」物語です。古くはフロリジンに端を発し、新しい科学的知見と技術によって現代医療に蘇ったこのクラスは、糖尿病治療に革命をもたらすとともに、心不全・CKDといった疾患領域で患者予後を改善する一筋の光となりました。その歩みを正しく理解し、安全かつ効果的に患者ケアへ活かすことが、我々医療従事者に課せられた使命と言えるでしょう。


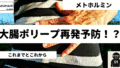
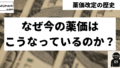
コメント