心筋梗塞が「運命」だった時代背景
1960年代まで、心筋梗塞や高コレステロール血症は多くの患者にとってほぼ「運命」と見なされていました。当時、コレステロールが動脈硬化に関与する可能性は指摘されていたものの、動脈硬化症は加齢に伴う避けられない現象と考えられ、予防できるという発想は一般的ではなかったのです 。実際、冠動脈疾患(心臓病)は20世紀中頃には米国などで死亡原因の上位を占めていましたが、それを防ぐ決定打はありませんでした 。コレステロール低下薬としては、1950年代に開発されたニコチン酸(ナイアシン)やクロフィブラート、コレスチラミンなどがありましたが、効果は限定的で副作用や使いにくさもあり、必ずしも理想的な治療薬とは言えませんでした 。
その結果、遺伝的にコレステロール値が高い家族性高コレステロール血症の患者や、中年以降にコレステロールが高くなってきた一般の人々に対して、医師ができることは食事療法や生活指導程度でした。例えば、生まれつきコレステロール値が非常に高い家族性高コレステロール血症の子どもは幼い頃から動脈硬化が進行し、若年で心筋梗塞を起こすこともありました。しかし当時は、有効な薬がなく、これらの患者の多くは若くして命を落としていたのです。そのため、「高コレステロール血症で心臓発作になるのは仕方がない」「心筋梗塞は防げない運命だ」という諦めが、医療現場や社会に蔓延していたのです。
ところが1950年代後半から1960年代にかけて、状況は徐々に変わり始めます。米国フラミンガム研究やAncel Keysによる七カ国研究によって、血中コレステロール値が高い人ほど冠動脈疾患のリスクが高いことが統計的に明らかにされました 。これにより、「脂質仮説」(コレステロールを下げれば心筋梗塞リスクを減らせる)が提唱され、コレステロール低下が冠動脈疾患予防に重要と考えられるようになっていきます。それでもなお、決定的な治療薬が存在しない時代、人々は依然として高コレステロール血症に不安を抱きながら日々を過ごしていました。そんな中、「運命」を覆そうと立ち上がった一人の科学者が現れます。
“青カビ”からの閃き – 遠藤章とメバスタチンの発見
1970年代初頭、日本の若き研究者・遠藤章博士は、コレステロールを下げる画期的な物質を探し出すことに人生を賭けました。遠藤博士は秋田県の農家に生まれ、幼少期からキノコやカビに親しみ、将来は科学者になることを夢見ていました 。大学卒業後に三共株式会社(現:第一三共)に入社し、発酵研究所で微生物を用いた研究に携わります 。ちょうどその頃、遠藤博士はアレクサンダー・フレミングが1928年に青カビ(Penicillium)からペニシリンを発見し、人類に抗生物質という恩恵をもたらした物語に強い感銘を受けていました 。彼は「微生物は人類の病を治す物質を生み出し得る」という信念を抱き、次第にある大胆な仮説へと思い至ります。
その仮説とは、「微生物の中には、自らを守るためにコレステロール合成を阻害する物質を作るものがいるのではないか」というものでした 。コレステロールはヒトを含む動物に必須の分子ですが、菌類(真菌類)は細胞膜にエルゴステロールという別のステロールを用いるため、自身は困らずに周囲の生物のコレステロール合成を妨害できるはずだ、という着想です 。コレステロール合成経路の鍵酵素であるHMG-CoA還元酵素を狙い撃ちする「抗コレステロール物質」が微生物由来で見つかれば、感染症におけるペニシリンのように、動脈硬化や心筋梗塞を防ぐ薬になるかもしれない——遠藤博士はそう確信し、1971年春からカビやキノコなど微生物が作る物質の大規模スクリーニングを開始しました 。
遠藤博士のチームは、微生物培養液からHMG-CoA還元酵素の活性を阻害するものを探し出すべく、工夫を凝らした実験系で臨みました 。数千におよぶ培養抽出液を少しずつ調べる地道な作業です。そうした中、1972年、ついに最初の手がかりが現れました。培養液の一つが強力な活性を示したのです。これから単離された物質は「シトリニン」と判明しました 。シトリニンは実は以前から知られた抗生物質でしたが、HMG-CoA還元酵素を強く阻害し、ラットに投与するとコレステロール低下効果も示したのです 。しかし喜びも束の間、シトリニンには腎毒性があり高用量で腎臓障害を起こすことが判明しました 。チームはシトリニンの研究を断念せざるを得ませんでしたが、「微生物が作る物質でコレステロールを下げられる」という確かな希望を得ることができました 。
そして1973年、運命の発見が訪れます。京都の穀物店で採取された米のカビから分離された青カビ(Penicillium citrinum)の培養液に、強力なHMG-CoA還元酵素阻害活性が見出されたのです 。前回の反省を活かし、チームはこの活性物質の精製に総力を挙げました。生産量がごくわずかで困難を極めましたが、それから約1年をかけて活性物質の結晶化に成功します 。抽出・精製された3種の物質のうち、特に強い作用を示したものが「ML-236B」と名付けられました 。この物質こそ、後にメバスタチン(一般名)、あるいはコンパクチンとも呼ばれる、世界初のスタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)です 。メバスタチンの構造は、HMG-CoA還元酵素の基質であるHMG-CoAに酷似しており、まさに狙い通り酵素を競合的に阻害する働きを持つことが判明しました 。自然界からの贈り物のようなその構造を目にし、遠藤博士は「これこそ待ち望んでいた物質だ」と胸を高鳴らせたといいます 。
開発の苦難 – 三共における試練と中止
メバスタチン(コンパクチン)の発見に成功した遠藤博士らでしたが、ここから実用化への道のりは平坦ではありませんでした。まず直面したのは動物実験での壁でした。培養細胞レベルでは驚異的なコレステロール合成阻害効果を示したメバスタチンですが、最初に試みたラットへの投与試験では全く血中コレステロールが低下しなかったのです 。この結果に、社内の生物試験担当者たちは落胆し、「ラットで効かない薬など開発できない」とプロジェクト中止の声も上がりました 。しかし遠藤博士は容易に諦めません。なぜラットで効かないのか、その理由を突き止める研究に乗り出しました。実験を重ねるうち、ラットではメバスタチンを繰り返し投与すると肝臓がHMG-CoA還元酵素を大量に作り出して薬の効果を打ち消してしまうことが判明しました 。一方で、単回投与では一時的にコレステロール値が下がること、そしてラット以外の動物では状況が異なる可能性も示唆されました 。
そんな折、幸運な偶然が遠藤博士に訪れます。1976年、研究を細々と続けていた遠藤博士は、行きつけの飲み屋でたまたま居合わせた同僚の獣医師から「実験に産卵鶏を使っている」という話を耳にしました 。産卵鶏は毎日卵を産むためコレステロールの需要が高く、血中コレステロール値も高めです。その話にヒントを得た遠藤博士は、「ニワトリになら効果が出るかもしれない」と早速メバスタチンの鶏への投与試験を企画します 。結果は期待以上でした。産卵鶏にメバスタチンを1ヶ月与えると、血清コレステロール値が50%近くも低下したのです 。さらにイヌやサルといった哺乳類でも顕著なコレステロール低下効果が確認されました。ラットでは得られなかった効果が他の動物種で証明され、これによりメバスタチンは新しいタイプの治療薬候補として一気に脚光を浴びることになります 。
1976年8月、三共社内に「コンパクチン開発プロジェクト」が正式に発足し、薬理学・毒性学・有機化学など各分野の専門家チームが結成されました 。しかし、喜びも束の間、再び試練が襲います。開発プロジェクト開始からわずか8ヶ月後の1977年4月、コンパクチンを高用量(なんと体重1kgあたり500mg以上!)で5週間もラットに投与するという過酷な長期毒性試験で、ラットの肝細胞内に不気味な微小結晶の沈着が認められたのです 。毒性検査担当の研究者たちは「何らかの有害物質が蓄積している」と強く懸念しました。プロジェクトチームは原因究明に9ヶ月を費やし、この結晶の正体がコレステロールそのものであることをようやく突き止めます 。要するに、極端な高容量投与により肝臓にコレステロールの結晶が溜まっていただけで、未知の有毒物質ができたわけではなかったのです。誤解が解けるとチームは開発を再開しました。
こうして困難を克服しつつ、ついに人への投与に踏み切る段階が訪れます。しかし当時、三共社内で慎重論が強かったため、遠藤博士は公式な承認を得ないまま極秘の臨床試験を決行することにしました 。協力者は大阪大学病院の山本章医師(後に大阪大学教授)です。1978年2月、心筋梗塞を繰り返していた家族性高コレステロール血症の18歳女性にコンパクチンの投与が開始されました 。結果は劇的でした――治療開始時1000mg/dL近くあった血清コレステロール値が700mg/dL程度まで低下し、患者の肌にあったコレステロール沈着による瘤(結節性黄色腫)が目に見えて縮小していったのです 。投与から2週間後、一時的に肝酵素上昇や筋力低下といった副作用も見られましたが、投与中止で速やかに回復し、その後は減量した200mg/日の投与で5ヶ月間治療を続けたところ、患者の重症な症状は明らかに改善しました 。
この成功に勇気づけられ、山本医師と遠藤博士はその後半年間で家族性高コレステロール血症のヘテロ接合体患者5名や重症高脂血症患者3名にコンパクチンを投与し、平均で約30%ものコレステロール低下効果を確認しました 。深刻な副作用もなく、これらの成果は1980年に医学誌で報告されています 。この「極秘臨床」の成功は社内の姿勢も前向きに転換させ、三共は1978年11月に正式な臨床試験(フェーズ1)を開始、翌1979年夏からは全国12病院で重症高コレステロール血症患者を対象にフェーズ2試験を行いました 。参加各施設からは「驚くほどコレステロールが下がる」「安全性も高い」と好評な報告が相次ぎ、コンパクチンは極めて有望な新薬候補として順調に開発が進んでいるかに思われました 。
ところが——ここで誰も予想しなかった悲劇的な決定が下されます。1980年8月、三共は突如コンパクチンの開発中止を宣言したのです 。社内外に大きな衝撃が走りました。その理由は公には「犬の長期毒性試験で腫瘍(リンパ腫)が見られた可能性があるため」と説明されました 。実際、犬に2年間という非常に長期間、高用量(体重1kgあたり100~200mg)のコンパクチンを与えた群でわずかにリンパ腫様の症例があったといいます 。しかし、低用量(20mg/kg)では何の異常もなく、そもそも人間に換算すれば治療に必要な用量の200倍にも及ぶ極端な投与量でした 。遠藤博士らの治験では1mg/kg未満で十分な効果が出ていたのですから、本来は問題視すべきでない所見でした 。後に三共が開発した第2のスタチン(プラバスタチン)ではこの轍を踏まえ、犬への投与量を意図的に制限して毒性試験を行ったほどです 。開発中止の判断は過剰に慎重すぎるもので、「幻の新薬」となったコンパクチンを惜しむ声は社内外から上がりました。しかし、企業としてのリスク回避やタイミングなど様々な事情もあったのでしょう。遠藤博士自身も失意の中、1978年末には三共を退職して東京農工大学の教授職に移り、以後は大学で還元酵素阻害剤の研究を続けていくことになります 。
米国メルク社による世界初のスタチン「ロバスタチン」
一方、日本でコンパクチン開発がドラマティックな展開を見せていたのと並行して、アメリカでも静かにスタチン開発の火が灯っていました。米国の製薬大手メルク社は、遠藤博士らのコンパクチンの成果に早くから注目していました。メルク研究所所長だった**ペプロスキー・R・ヴァゲロス(Roy Vagelos)**博士は1976年7月、三共との間に秘密保持契約を結び、コンパクチンのサンプルと試験データの提供を受けています 。メルクの研究者たちはその強力な作用に驚嘆し、独自に同様の物質を探すプロジェクトを立ち上げました 。指揮を執ったのはアルフレッド・アルバーツ(Alfred Alberts)博士で、彼らは膨大な微生物株の中から自前のスタチンを見つけ出そうと躍起になりました 。
そして1978年11月、メルクのチームはついにカビの一種アスペルギルス・テレウス(Aspergillus terreus)の培養から、新たなスタチン化合物を発見します 。この物質はメバスタチン(コンパクチン)と化学構造が非常に近かったため、当初「メビノリン(Mevinolin)」と命名されました 。後に一般名ロバスタチン(Lovastatin)と改められることになる化合物です。そのころ遠藤博士も大学に移ってすぐ、自ら分離した紅麹菌(Monascus ruber)から似たような構造を持つモナコリンKという物質を1979年2月に発見しており、これはメルクのメビノリンと同一の化合物だと判明しました 。しかし特許上はメルク側が「1978年には発見していた」と先発明の権利を主張し、ロバスタチンの発明はメルクのものと認められました 。遠藤博士はスタチンの生みの親でありながら、経済的な恩恵はほとんど得られなかったのです。このような裏話もありますが、いずれにせよロバスタチンは世界で初めて実用化されたスタチンとして歴史に刻まれることになります 。
メルク社内ではロバスタチンの開発が急ピッチで進められました。コンパクチンが日本で中止となったという知らせを受け、一時はメルクも臨床試験の継続に慎重になります 。実際、1980年4月から開始したロバスタチンの人への予備的臨床試験は、同年9月に「コンパクチンに発がん疑惑あり」との噂を受けて中断されました 。しかしその後、状況は好転します。1981年初頭、アメリカのブラウン博士とゴールドスタイン博士(コレステロール代謝研究の第一人者で、後に1985年ノーベル賞受賞)がロバスタチンによって犬の肝臓のLDL受容体が増加し、LDLコレステロールが劇的に低下することを実証しました 。さらに同年、前述の金沢大学・馬渕義夫教授のグループがコンパクチンの臨床効果を欧州の学会で発表し、重症高コレステロール血症患者で平均30%のLDLコレステロール低下と安全性を示す成果を報告しました 。これらのエビデンスは「スタチンは人でも有効で安全らしい」という確信を世界にもたらし、メルク社内の雰囲気も一気に前向きに変わります。
1982年7月には、アメリカの臨床医たち(オレゴン健康科学大学のIllingworth博士、テキサス大学のGrundy博士とBilheimer博士ら)が重症の高コレステロール血症患者にロバスタチンを投与する治験を開始し、LDLコレステロールが驚くほど下がり副作用もごく僅かであるという目覚ましい結果が得られました 。これを受けてメルク社は本格的な大規模臨床試験と長期毒性試験を再開し、1984年には高リスク患者を対象にした試験でロバスタチンの劇的なコレステロール低下効果と安全性を確認しました 。懸念されたイヌでの腫瘍発生も、適正用量の範囲内では全く認められませんでした 。こうして十分なデータを蓄積したメルク社は1986年11月に米国FDAへロバスタチンの承認申請を行い、翌1987年9月にスタチンとして世界初の医薬品承認を取得します 。商品名**「Mevacor(メバコール)」**として発売されたロバスタチンは、医療現場に革命を起こしました 。これまで食事療法くらいしか手がなかった高コレステロール血症に対し、初めて手にした強力な薬剤だったのです。
ロバスタチンは投与によりLDLコレステロールを20~30%以上低下させることが可能で、患者の血管リスクを大幅に下げる潜在力を持っていました 。その効果の源は、遠藤博士が探し求めたHMG-CoA還元酵素阻害というメカニズムそのものです。ロバスタチンはメバスタチンにごく小さな修飾を加えただけの類似構造でしたが、そのおかげか毒性の問題もクリアし、「心筋梗塞を運命から解き放つ薬」として大きな期待を背負うことになったのです 。こうして、日本で生まれかけて一度は消えた光は、海を渡った地で形を変えて甦りました。
新薬への期待と医学界の懐疑
1987年に世界初のスタチン・ロバスタチンが登場すると、臨床医や患者から大きな期待が寄せられました。長年「どうにもならない」と思われていた高コレステロール血症に対し、劇的な効果を示す新薬が現れたからです。しかし同時に、一部の医学者や医師たちはこの新しい薬剤を慎重に見守りました。初期のスタチンに対する医学界の反応は、決して手放しの称賛ばかりではなかったのです。
まず、当時行われた臨床試験の限界が指摘されました。ロバスタチン発売前後に得られていた臨床データの多くは、中年の男性患者を主な対象としていました 。そのため「この薬の有効性は高齢者や女性にも当てはまるのか?」という疑問が投げかけられました 。また、ロバスタチンによって確かに狭心症や心筋梗塞の発症は減る傾向が報告されていたものの、当初の試験規模では**明確な寿命延長効果(総死亡率の低下)**までは示されていなかったのです 。一部の専門家は「コレステロール値を下げても、本当に命を救えると証明されたわけではない」と懐疑的でした。
さらに、スタチンが登場したばかりの頃には長期的な安全性への不安も残っていました。動物実験での高用量投与による発がん性疑惑のエピソードは関係者の間で知られており、「人で長期間使って大丈夫なのか?」という心配はゼロではなかったのです 。また、かつてコレステロール低下薬クロフィブラートの大規模臨床試験(WHO研究)で総死亡に悪影響が出たとの報告が1970年代にあったことも、医師たちの記憶に残っていました。このため「コレステロールを無理に下げると他の病気が増えるのではないか」「極端に下げすぎると細胞膜やホルモン合成に悪影響が出るのでは?」といった声も少なからず聞かれたのです。
こうした懐疑的な見解もあり、スタチンの普及は発売当初、思ったほど急速には進みませんでした 。1988年にはロバスタチンの改良型であるシンバスタチン(商品名リポバス)が、続いて1989年には日本でも遠藤博士の発見したコンパクチンをもとに開発されたプラバスタチン(メバロチン)が発売されます 。処方できる薬剤が増えていく中でも、「本当にこの薬で患者の寿命を延ばせるのか?」という問いは現場の医師たちが抱え続けた課題でした。しかし、この疑念は1990年代前半に転機を迎えます。1994年4月、北欧で行われた4S試験(スカンジナビアシンバスタチン生存率試験)の結果が発表され、スタチン治療群で全死亡率が30%も減少するという驚くべきデータが示されたのです 。この報告により、スタチンが心筋梗塞の発症を減らすだけでなく寿命を延ばし得ることが明白になり、初期の懐疑は雪解けを迎えました。
こうしてスタチンは医療界に確固たる地位を築いていきます。その後も次々と新たなスタチン(フルバスタチン、アトルバスタチン、ピタバスタチン、ロスバスタチン等)が開発され、スタチン療法は冠動脈疾患予防の標準となりました 。しかし、その「礎」となったのは紛れもなく遠藤章博士によるメバスタチンの発見と、それを引き継いだロバスタチンの成功でした。「運命」を覆す執念が形となり、現在では世界中で数千万人もの人々がスタチンにより命を救われています 。
第1部ではスタチン誕生までの物語を綴りましたが、第2部ではその後の発展や現代における位置づけについてさらに掘り下げていきたいと思います。

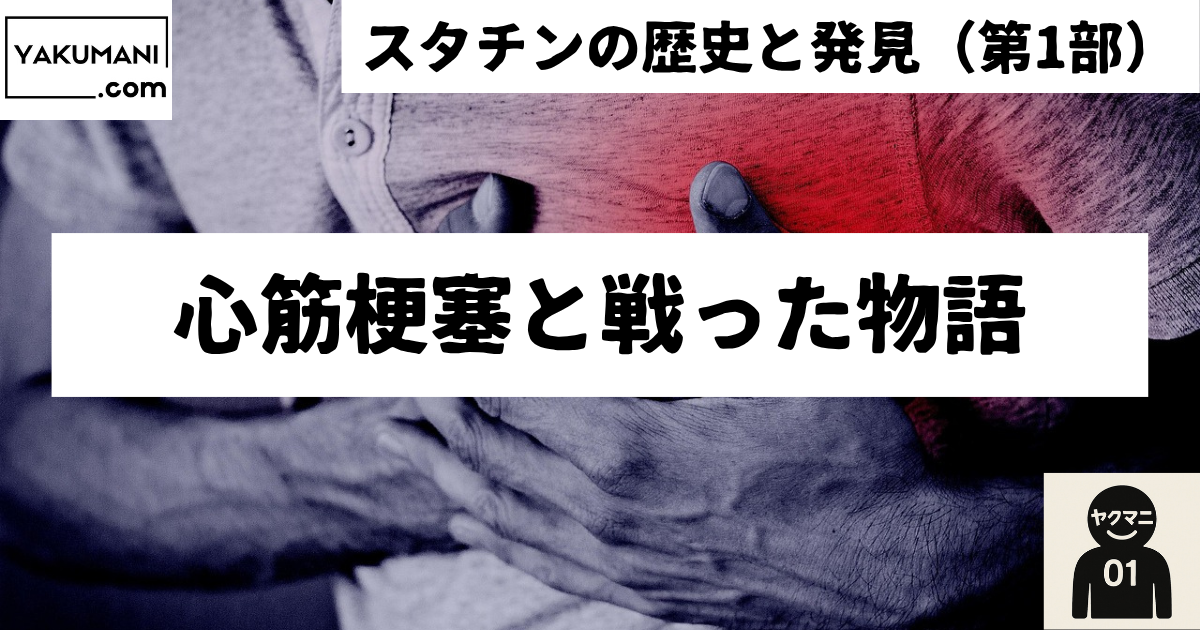
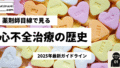
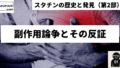
コメント