はじめに ― この記事で分かること
-
なぜLDLコレステロールが治療の中心となったのか
-
中性脂肪(TG)の位置づけが後回しにされてきた理由
-
フィブラートが今も臨床で活用されている背景と適応症例のイメージ
読者への問いかけ
「LDLを下げるだけで、すべて解決したと言える?」
「TGを下げる薬が今も使われている理由、説明できますか?」
なぜTGは“主役”になれなかったのか?
脂質異常症の治療目標は、時代とともに変遷してきました。
1970年代までは総コレステロール(TC)がリスク指標とされていましたが、
その後、LDL-Cが動脈硬化の中心的因子と認識されるようになり、
1980年代以降はスタチンによるLDL-C低下が心血管イベント予防の中心戦略として確立しました。
一方、**中性脂肪(トリグリセリド, TG)**は、
-
食事や時間帯による変動が大きい
-
心血管疾患との因果関係が明確でない
とされ、“治療優先度が低い”と位置づけられてきました。
TGを下げると意味があるのか?
TGを低下させる薬剤の代表がフィブラート系薬です。
1960年代に登場したクロフィブラートを皮切りに、
PPARα(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体α)を活性化する
ベザフィブラートやフェノフィブラートが実用化されました。
2000年代には、スタチンに追加することでアウトカムを改善できるかを検証する試験が行われました。
-
FIELD試験(2005, フェノフィブラート)
-
ACCORD-Lipid試験(2010, スタチン+フェノフィブラート vs スタチン単独)
結果として、主要心血管イベントの全体抑制効果は統計的に有意ではありませんでした。
しかしながら、TGが高くHDL-Cが低い患者群においては、
有意なアウトカム改善が示唆されるサブ解析結果が報告され、
「適切な患者選択があれば効果を示す薬剤である」と評価されるようになりました。
フィブラートはどんな患者に“刺さる”のか?
● TGが500mg/dL以上の患者(急性膵炎の予防)
TGが高度に上昇している場合は、急性膵炎のリスクが現実的となり、
TG低下を目的とした薬物治療が検討されます。
● TG高値+HDL低値の「残余リスクが高い」群
糖尿病、肥満、メタボリック症候群など、LDL-Cが十分に管理されているにもかかわらず
心筋梗塞や脳梗塞などのイベントを起こす患者群に対し、
非LDL-Cの異常(TG・HDL-C)に対する介入が補完的な選択肢となります。
補足:そもそも“残余リスク”って何?
スタチンが普及し、LDL-C管理が当たり前となった今も、
「LDLは目標値内なのに、イベントを繰り返す」という症例が存在します。
このような、LDL-Cを十分に管理してもなお残る動脈硬化性疾患リスクが、いわゆる**残余リスク(Residual Risk)**です。
この残余リスクの一因として、近年注目されているのが:
-
TGの高値(中性脂肪)
-
HDL-Cの低値(善玉コレステロール)
です。
TG高値・HDL低値に着目した治療戦略は、今も進化の途中にありますが、
フィブラートはこの領域で**エビデンスと経験のある“数少ない選択肢”**として位置づけられています。
なぜ今も処方されるのか?
フィブラートは、現行ガイドラインでも以下のように記載されています。
-
日本動脈硬化学会(JAS2022):
「まずはLDL-C管理を優先。そのうえでTG異常があれば、フィブラートなどを検討」 -
米国AHA/ACCガイドライン(2018):
「TGが500mg/dL以上であれば、膵炎予防の観点からフィブラートを含む薬物療法を推奨」
「TG 200〜499mg/dLの場合は、スタチンを基本としつつ、必要に応じて追加療法を検討」
こうした推奨に基づき、現場では以下のような処方が行われています:
-
TG600以上で膵炎が懸念されるケース
-
LDL-Cは良好でもTG高値が持続する糖尿病合併症例
-
尿酸・肝酵素・脂肪肝など複数の代謝異常が絡むケース
結論 ― フィブラートの価値はここにある
-
脂質治療はLDL-Cだけでは不十分
-
TGやHDL-Cが異常を示す“残余リスク群”が、確かに存在している
-
フィブラートは、そうした患者に“最適化された治療”を目指す際の選択肢となりうる
“もう古い薬”と思われがちなフィブラートですが、
スタチン時代の“その先”を見据える治療薬として、今なお臨床現場で活躍しています。

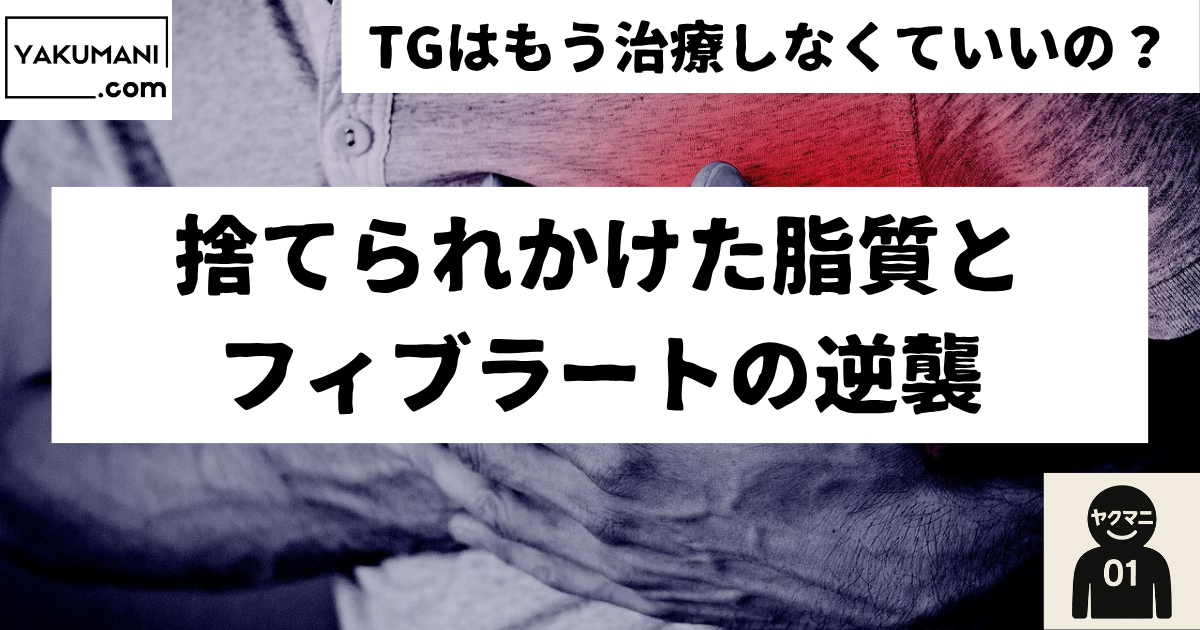
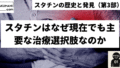
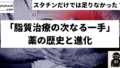
コメント