背景・問題の重要性
大腸ポリープ(特に腺腫性ポリープ)は大腸癌の前駆病変であり、内視鏡的切除後もしばしば新たなポリープが再発(異時性発生)します 。ポリープの再発予防は大腸癌の発症抑制につながる可能性があり、従来から食事・生活習慣の改善やアスピリン・NSAIDs(非ステロイド抗炎症薬)の投与などが検討されてきました 。しかし、COX-2阻害薬などNSAIDsの長期使用は心血管イベント等の重篤な副作用リスクが問題となり 、安全かつ有効な新たな化学予防戦略が求められていました 。
一方、メトホルミンは2型糖尿病治療薬として古くから広く用いられているビグアナイド系薬剤です 。近年、糖尿病患者での疫学研究から「メトホルミンを服用している糖尿病患者では癌の罹患率や死亡率が低い」と示唆する報告が相次ぎ、既存薬の適応外使用による癌予防効果に注目が集まりました 。特に大腸癌については、糖尿病はリスク因子となる一方で、メトホルミン使用が大腸癌および腺腫の発生リスク低下と関連するとの観察報告が蓄積され、メトホルミンを大腸ポリープ再発予防に応用できる可能性が研究されるようになりました 。
本稿では、メトホルミンによる大腸ポリープ再発予防に関する治療の歴史と進展について、前臨床(基礎研究)から臨床試験までの歩みを概説し、最新の知見と今後の展望を考察します。なお、メトホルミンのポリープ予防目的での使用は現時点で適応外であり、エビデンスに基づく慎重な評価が必要です。
メトホルミンの抗腫瘍作用メカニズムと着目された理由
メトホルミンが注目された背景には、その抗腫瘍作用のメカニズムに関する知見があります。メトホルミンは肝臓でのAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)の活性化を介しインスリン抵抗性を改善し、血中インスリンやIGF-1(インスリン様成長因子)の低下をもたらします 。高インスリン・高IGF状態は上皮細胞の増殖促進や発がんを助長することが知られており、糖尿病患者で大腸癌リスクが上昇する一因とも考えられます 。メトホルミンによりインスリン/IGF経路が抑制されれば、腫瘍形成が抑えられる可能性があります。
さらにメトホルミンは細胞レベルでAMPKを直接活性化し、下流のmTOR経路(細胞増殖やタンパク質合成を司る経路)を抑制します 。mTORは多くの癌で活性化している経路であり、AMPKの活性化によりこれを抑えることで細胞増殖抑制・アポトーシス誘導など抗腫瘍効果が生じると考えられています 。実際、メトホルミンは大腸癌細胞株の増殖を抑制し、細胞周期を停止させる作用が報告されています 。
こうした作用機序上の合理性に加え、疫学データもメトホルミンへの期待を高めました。前述のように、糖尿病患者での後ろ向き研究ではメトホルミン使用者は非使用者に比べ大腸癌の発生率が有意に低下したとの報告があり(例:メトホルミン使用で大腸癌リスクが22%低下、OR=0.78 )、**腺腫(ポリープ)発生も25%減少(OR=0.75)**したとのメタ解析結果も発表されています 。こうした知見から、「メトホルミンを内服することで大腸ポリープの再発を抑制し、ひいては大腸癌の二次予防につながるのではないか」という仮説が生まれ、前臨床および臨床研究が開始されました。
前臨床研究:細胞・動物モデルでの検証
メトホルミンの大腸ポリープ抑制効果は、まず**基礎研究(細胞・動物実験)**において検証されました。
細胞培養系での作用
in vitro(培養細胞)研究では、メトホルミンが大腸癌細胞の増殖を抑制する報告が複数あります 。例えばメトホルミン処理により癌細胞のAMPKが活性化され、下流のmTORやS6K(リボソームタンパク質S6キナーゼ)のリン酸化低下を伴ってタンパク質合成が減少し、細胞増殖が鈍化することが示されています 。また細胞周期がG1期で停止しアポトーシス(細胞死)が誘導されるなど、抗増殖・抗腫瘍効果を示すデータが蓄積しています 。これらはメトホルミンの機序的裏付けを与える結果で、動物モデルでの検証が次に行われました。
動物モデルでの検証
マウスを用いた研究では、2008年に日本のグループが発表したAPCMin/+マウス(家族性大腸腺腫症のモデルマウスで小腸・大腸に多数のポリープができる)を使った試験が嚆矢となりました 。この研究では、メトホルミンをマウスに経口投与したところ大きなサイズの腸ポリープの発生が有意に抑制されました(※総ポリープ数は減らないものの、直径2mm超の大きなポリープ数が有意に減少) 。メトホルミン投与群ではポリープ組織中でAMPKのリン酸化上昇とmTORシグナルの抑制が確認され、ポリープ増殖抑制効果はこれらの分子機序によると考察されています 。興味深いことに、メトホルミン投与によりマウスのインスリン抵抗性や血中脂質に大きな変化は認められず、ポリープ抑制効果は全身代謝改善による二次的作用ではなく、腫瘍組織への直接作用であろうと推察されています 。この結果は、「メトホルミンは大腸ポリープの成長を抑える新たな化学予防薬となり得る」ことを示唆するものでした 。
さらに化学発癌モデルでも有望な結果が得られています。ラットに発癌物質を投与して大腸前がん病変である異常陰窩巣(ACF)を誘発するモデルでは、メトホルミン投与によりACFの数が減少し、その機序にAMPKの活性化が関与することが示されました 。これら動物実験の成果により、メトホルミンの抗ポリープ効果が前臨床段階で支持され、人への応用可能性が高まったのです。
初期の臨床研究:パイロット試験と観察研究による証拠
前臨床で有望だったメトホルミンの効果を実際の人に応用するべく、2010年前後から臨床研究が開始されました。当初は小規模の予備的試験や後ろ向きの観察研究が中心でしたが、これらは仮説検証に重要な役割を果たしました。
パイロット臨床試験(ACF試験)
世界初の人での検証は日本で行われたパイロット臨床試験(無作為化比較試験)でした 。2010年、Hosonoらは内視鏡で確認できる直腸の異常陰窩巣(ACF)数をエンドポイントとして、メトホルミン短期投与の効果を評価しました 。対象は非糖尿病の成人26名で、メトホルミン250mg/日を1ヶ月間投与する群(12名)と非投与対照群(14名)にランダムに割り付けられました 。1ヶ月後に再度内視鏡で直腸ACF数を計測した結果、メトホルミン群ではACF数が投与前平均8.78個から5.11個へと有意に減少しました(約42%減少, P = 0.007) 。対照群ではACF数に有意な変化はなく(7.23個→7.56個, P = 0.61)、群間比較でもメトホルミン群の顕著なACF抑制効果が示されました 。加えて、生検組織の解析で細胞増殖マーカー(PCNA指数)の低下も認められ、メトホルミンがヒト大腸粘膜上皮の増殖を抑えることが示唆されました 。これは「メトホルミンがヒト大腸発癌過程を抑制し得る」ことを示す初のエビデンスであり、著者らも本試験を「メトホルミンの大腸癌化学予防効果を示した初めての臨床試験」と位置付けています 。もっとも、この試験は期間も短く最終的な臨床アウトカム(ポリープ発生抑制)ではなく代理マーカー評価でしたが、その有望性から以後の研究展開を促す重要な役割を果たしました。
観察研究からの示唆
パイロット試験と並行して、疫学的な観察研究でもメトホルミンの大腸ポリープ・腫瘍抑制効果が検証されました。特に糖尿病患者を対象とした後ろ向きコホート研究や症例対照研究から、有用性を支持するデータが蓄積しています。
- Leeら(韓国, 2012年)は既往に大腸癌を持つ糖尿病患者を対象に検討を行い、メトホルミン使用者では非使用者に比べ新たな大腸腺腫発生が少ないことを報告しました 。具体的には、結腸直腸癌既往の糖尿病患者において5年近くの追跡で、メトホルミン服用群の約29%に再発腺腫が見つかったのに対し、非服用群では約46%に腺腫が認められたとの結果です 。これは観察研究であり因果関係の証明ではないものの、糖尿病治療中のメトホルミンが腺腫再発リスクを低減し得ることを示す示唆的なデータです。
- Choら(韓国, 2014年)は糖尿病患者で初回大腸内視鏡検査を受けた3,105例のデータを解析し、メトホルミン使用の有無による大腸ポリープ検出率の差を調べました 。その結果、メトホルミンを>1ヶ月以上使用していた群では使用していない群に比べ、ポリープ検出率(PDR)が39.4%対62.4%と有意に低く、腺腫検出率(ADR)も15.2%対20.5%と低下していました(いずれも P < 0.01) 。多変量ロジスティック解析でもメトホルミン使用は独立して腺腫発見オッズを約26%減少させる関連因子とされました(調整OR = 0.74, 95%CI 0.55–0.98) 。このように、日常診療データの解析からもメトホルミン使用群で有意にポリープ・腺腫が少ないことが示され、予防効果の可能性が支持されています。
- Kimら(韓国, 2015年)は糖尿病患者における進行腺腫(サイズ1cm超や高度異型などの高リスク腺腫)の発生に着目し、メトホルミンの影響を検討しました。その結果、メトホルミン使用は糖尿病患者の進行大腸腺腫の発生リスクを有意に低下させ、特に長期追跡でメトホルミン群の進行腺腫発生率が非使用群より低いことが報告されています 。この知見は、「メトホルミンは単なる小さなポリープだけでなく、癌化リスクの高い進行腺腫の発生を抑える可能性がある」ことを示すもので、臨床的意義が大きいといえます。
以上のような複数の観察研究は総じて、「糖尿病患者においてメトホルミン使用が大腸ポリープ・腺腫の発生リスク低減と関連する」ことを示唆しました。ただし、観察研究ゆえに交絡因子の影響を完全には除外できず、一部には異なる結論もあります。例えばKowallら(独・英, 2015年)は約4,769人の糖尿病患者を解析し、メトホルミンと癌リスクの関連に時間依存バイアスの補正を加えたところ、大腸癌リスクに有意な低減効果は認められなかったと報告しています 。また米国・北カリフォルニアの大規模コホート研究(1997–2012年, n=47,351例)でも、平均4.6年の追跡中にメトホルミン使用の有無で大腸癌発生率に明確な差はなく、総投与量や期間との用量反応関係も一貫しなかったとされています 。ただし同研究では5年以上の長期使用例では男性でリスク低下の傾向が見られるなど(一部サブグループではHR=0.65, 95%CI 0.45–0.94) 、結果は一様ではありません。このように観察研究の結果は多少のばらつきがありますが、全体的にはメトホルミンの大腸腫瘍抑制効果を支持する報告が多く、次第に前向き臨床試験による検証が求められるようになりました。
観察研究のメタ解析
個々の観察研究を統合したメタ解析もいくつか実施され、より包括的な知見が得られています。その中でも重要なものを紹介します。
- **Jungら(2017年)**による系統的レビュー・メタ解析(コホート研究12件・症例対照研究7件・RCT1件を統合, 対象数合計約2万名)では、メトホルミン使用が大腸腺腫リスクを約24%有意に減少させ、大腸癌リスクも約22%低下するとの結果が示されました(腺腫のオッズ比OR=0.75, 95%CI 0.59–0.97;大腸癌OR=0.78, 95%CI 0.70–0.87) 。特に大腸腫瘍の既往があるハイリスク集団や糖尿病患者において効果が大きい可能性が示唆されています (※例えば腫瘍既往者サブグループでは腺腫発生OR=0.61と低下傾向)。この解析は観察研究主体ながら、メトホルミンの予防的効果を裏付けるエビデンスといえます。
- 一方で**Mansourianら(2018年)の解析では、メトホルミンの一次予防(新規腺腫抑制)と二次予防(再発抑制)**の効果を区別して評価しています。その結果、総腺腫発生や再発に対する効果は統計的に有意でないものの(再発予防のOR=0.89, P = 0.137)、進行腺腫(高リスク腺腫)に対しては有意なリスク低減効果があると報告されました 。具体的には、メトホルミン使用者で進行腺腫の発生オッズが約半分に低下しており(OR=0.51, P < 0.001)、臨床的に重要ながん化リスクの高い病変に対して予防効果を発揮している点が注目されます 。
このようにメタ解析からは、メトホルミンが大腸ポリープ・腺腫の発生リスクを全体としておよそ20–30%低減し、とりわけ進行病変の抑制に有望であることが示唆されています。ただし、完全に一貫した結果ではなく、一部に有意差が出ない項目も存在するため、さらなる前向き試験での検証が不可欠といえます。
大規模臨床試験の展開:RCTから得られたエビデンス
観察研究やパイロット試験での有望な結果を受け、2010年代半ば以降には**前向きのランダム化比較試験(RCT)**が実施され、メトホルミンの大腸ポリープ再発予防効果がより厳密に検証されました。その中でも代表的な試験と知見を紹介します。
日本におけるPhase III試験(非糖尿病者対象)
最もエビデンスレベルが高い試験として知られるのが、樋曽崎らによる日本国内第III相比較試験です 。このRCTは、糖尿病ではないが腺腫の内視鏡切除歴がある高リスク患者151名を対象に、低用量メトホルミン(250mg/日)またはプラセボを1年間投与し、大腸内視鏡でのポリープ再発状況を比較した多施設二重盲検試験です 。主要評価項目は1年後の異時性ポリープ再発の有無および本数で、結果は2016年にLancet Oncology誌に報告されました。
試験の結果、メトホルミン群ではプラセボ群に比べ有意にポリープ再発率が低下しました 。具体的には、1年後の大腸内視鏡でポリープ(腺腫+過形成ポリープ)の検出率はメトホルミン群38.0%に対しプラセボ群56.5%と有意差をもって低く(RR=0.67, P = 0.034)、腺腫の再発率もメトホルミン群30.6% vs プラセボ群51.6%と顕著に低減していました(RR=0.60, P = 0.016) 。さらに再発ポリープの数についても、メトホルミン群の中央値は0個(四分位範囲0–1)でプラセボ群の中央値1個(0–1)より少なく、有意差が認められました 。このように低容量メトホルミン1年間投与は非糖尿病のポリープ高リスク患者においてポリープ再発リスクを約30–40%減少させたことになります 。
安全性の面でも重要な所見が得られています。1年間の試験期間中、両群で重篤な有害事象は報告されず、メトホルミン群で副作用が見られた患者は15名(11%)でしたが、その全てが**グレード1(軽度)**のものでした 。具体的には消化器症状(軽い下痢や吐き気など)が中心で重篤な障害はなく、非糖尿病者に低用量メトホルミンを投与しても概ね安全であったと結論されています 。
本試験は信頼性の高いエビデンスとして、「メトホルミンには大腸腺腫・ポリープの化学予防効果があり得る」ことを初めて明確に示しました 。著者らは**「メトホルミンは大腸癌の化学予防に有望な役割を果たす可能性がある」**とまとめています 。もっとも追記すれば、追跡期間が1年と比較的短かったこと、症例数がやや限られることから、今後さらなる大規模・長期試験での検証が必要である点も指摘されています 。
その他のRCTと特殊状況での検証
上記日本のRCT以降、世界的にもメトホルミンのポリープ予防効果を検証する動きが進みました。ただ、現時点(2025年)で大腸ポリープ再発抑制を主要エンドポイントとした大規模RCTは日本の試験が突出しており、他には中小規模の試験や特殊な集団を対象とした試験が散見される程度です。そのいくつかを紹介します。
- 米国におけるPhase II試験(Zellら, 2020年):肥満傾向にある腺腫既往患者を対象に、メトホルミンの短期投与が直腸粘膜のバイオマーカーに与える影響を調べた試験があります 。対象はBMI 30超の非糖尿病者で過去3年以内に大腸腺腫を切除した患者で、メトホルミン最大1000mg/日を12週間投与し、生検組織内のmTOR経路活性(リン酸化S6タンパク質量)などを指標にしました 。結果、短期間のメトホルミン投与は安全ではあったものの、体重や空腹時血糖に有意な変化はなく、肝心の直腸粘膜におけるp-S6発現レベルにも明確な低下効果は示されませんでした 。著者らは「非糖尿病・肥満患者に対するメトホルミンの大腸組織への直接効果は、この期間・条件では顕著に示せなかった」とし、実組織への作用検証にはより大規模・長期間の研究が必要と結論づけています 。この試験はバイオマーカー評価が中心で臨床アウトカム(ポリープ再発)は見ていませんが、西洋人集団でのエビデンスとして興味深いものです。
- 家族性大腸腺腫症(FAP)患者への適用可能性:FAPは多数のポリープを生じる遺伝性疾患で、大腸癌リスクが極めて高いため、ポリープ抑制療法の文脈でメトホルミンも検討されています。ただ、この特殊集団でのエビデンスは一致しておらず、現時点では結論に至っていません。韓国のRCT(Parkら, 2021年)では、FAP患者34名をプラセボ、メトホルミン500mg、同1500mgの3群に割付け7ヶ月間投与しましたが、大腸および十二指腸のポリープ数・サイズの変化に群間差は認められませんでした 。投与によるポリープ退縮効果は見られなかった一方、メトホルミン投与群から切除したポリープ組織ではmTOR経路のマーカー(リン酸化S6)の発現低下が確認されており、分子的作用はあっても臨床効果に結びつかなかった可能性が示唆されています 。著者らは「7ヶ月間のメトホルミン投与ではFAP患者の消化管ポリープ負荷を減らす効果はなく、現時点でその使用を支持できない」と結論づけています 。
一方、中国からの報告(Zhouら, 2024年)では、FAP患者を対象にした二重盲検RCTにおいて1年間のメトホルミン療法がポリープ数・ポリープ荷重の増加抑制に有効だったとする結果が発表されています 。この研究では症例数は26名と小規模ながら、メトホルミン群で治療前に比べポリープ数およびポリープ総径(荷重)の増加が有意に抑えられ、さらに腸内細菌叢の多様性が増加するといった変化も認められました 。著者らは「1年間のメトホルミン療法はFAPにおいて安全で効果的であり、その一部は腸内フローラの変化によって媒介される可能性がある」と述べ、腫瘍予防効果発現に腸内環境の役割にも言及しています 。この結果は先行する韓国の試験と矛盾するため、今後検証が必要ですが、新たな観点(マイクロバイオームとの関連)を提示した点で注目されます。
- 併用療法の模索:メトホルミン単独だけでなく、他の予防薬との併用による相乗効果も研究されています。その一つがアスピリンとの併用です。アスピリンも大腸癌・ポリープ予防効果が知られる薬剤ですが、メトホルミンとの併用でさらに効果増強が期待されています。日本のグループはACFを指標に、アスピリンとメトホルミンを組み合わせた予防効果を検証するRCT(2020年発表)を行い、併用療法が有望であることを示唆する結果を報告しています 。また欧州でもASAMET試験と呼ばれるアスピリン+メトホルミンの2×2因子無作為比較試験が企画され、術後大腸癌患者160名を対象にアスピリン単独、メトホルミン単独、併用、およびプラセボの4群比較で1年後の再発腫瘍(腺腫や異型上皮の発生)に対する効果と分子マーカー変化を調べる試みが進行中です 。最終結果はまだ出ていませんが、中間報告では安全性に大きな問題なく治療介入が行えていることが示されています(併用群でも忍容性は良好)。このように併用による相乗効果の検証は今後の重要な研究領域であり、最適な予防戦略確立に寄与すると期待されています。
最新の知見と今後の展望
以上のように、メトホルミンによる大腸ポリープ再発予防については基礎から臨床まで多くの研究が積み重ねられてきました。観察研究の段階では糖尿病患者を中心にリスク低減効果が示唆され、RCTによって非糖尿病の高リスク者でも低用量メトホルミンがポリープ再発を抑制し得ることが証明されました 。特に日本の試験結果は画期的であり、**「糖尿病治療薬メトホルミンを新たな癌予防薬として転用できる可能性」**を示したと評価されています。
他方、全ての研究が一貫した成果を示しているわけではなく、効果が見られなかったという報告も一部には存在します 。また、効果があったとしてもそれがどの程度の期間・投与量で持続するのか、投与中止後も予防効果が残るのか、そして最終的に大腸癌の発症や死亡を減少させるかといった長期的・臨床的に最も重要な疑問は未だ明確ではありません。現在進行中または計画中の臨床試験も複数あり、それらでは再発予防のみならず大腸癌サバイバーに対する再発リスク低減や、化学療法中の非糖尿病患者に対する**補助療法(アジュバント)**としての効果検証など、幅広い視点からメトホルミンの有用性が探られています 。今後これらの結果が出揃えば、メトホルミンの位置づけがさらに明確になるでしょう。
現時点では、メトホルミンは大腸ポリープ再発予防の目的で公式に承認された薬剤ではなく、使用する場合は適応外処方となります。したがって臨床現場での使用にあたっては最新エビデンスの動向を注視しつつ、患者ごとのリスク・ベネフィットを慎重に判断する必要があります。特に糖尿病を有しない集団に漫然と投与することは推奨されず、エビデンスが確立するまでは臨床試験の枠組みで検討すべき段階といえます。幸いこれまでの試験では概ね安全性は高く重篤な副作用は報告されていないものの 、長期投与での影響や希少な有害事象の有無についても今後検証が必要です。
最後に、メトホルミンの作用メカニズムに関する新たな知見として、腸内細菌叢への影響が大腸腫瘍抑制に関与し得ることが示唆されてきました 。メトホルミンは腸内細菌の組成を変化させ、短鎖脂肪酸産生菌の増加や粘液分解菌の増加など、有益な菌叢変化をもたらす報告があります 。腸内環境と大腸癌の関連は近年注目されるテーマであり、メトホルミンの予防効果を腸内フローラの視点から再評価する研究も今後進展すると考えられます。
おわりに
メトホルミンによる大腸ポリープ再発予防の研究は、この10年以上で飛躍的に進みました。前臨床段階で示された抗腫瘍作用メカニズムは臨床研究によって一定の裏付けを得ており、従来の治療薬を新たな用途で活用するドラッグリポジショニングの好例として期待されています。とりわけ大腸癌は罹患数の多い癌であり、その前段階であるポリープ再発を抑制できれば公衆衛生上のインパクトも大きいでしょう。
しかしながら、現状はまだ研究段階の知見であり、直ちに日常診療に導入されているわけではありません。薬機法や医療広告ガイドラインの観点からも、エビデンスに基づかない安易な適応外使用を煽ることは厳に慎む必要があります。本稿で述べたような科学的根拠にもとづきつつ、今後さらなる大規模臨床試験や検証結果を待って、エビデンスが確立した段階でガイドライン等に位置づけられることが望まれます。
メトホルミンは比較的安価で安全性プロファイルも良好な薬剤であり、仮に大腸ポリープ・癌の予防に有効と正式に証明されれば、医療経済的にも有用な戦略となる可能性があります。今後の研究の進展とエビデンス集積により、**「メトホルミンで大腸癌を予防する」**というコンセプトが現実の医療として定着するか注視していきたいと思います。

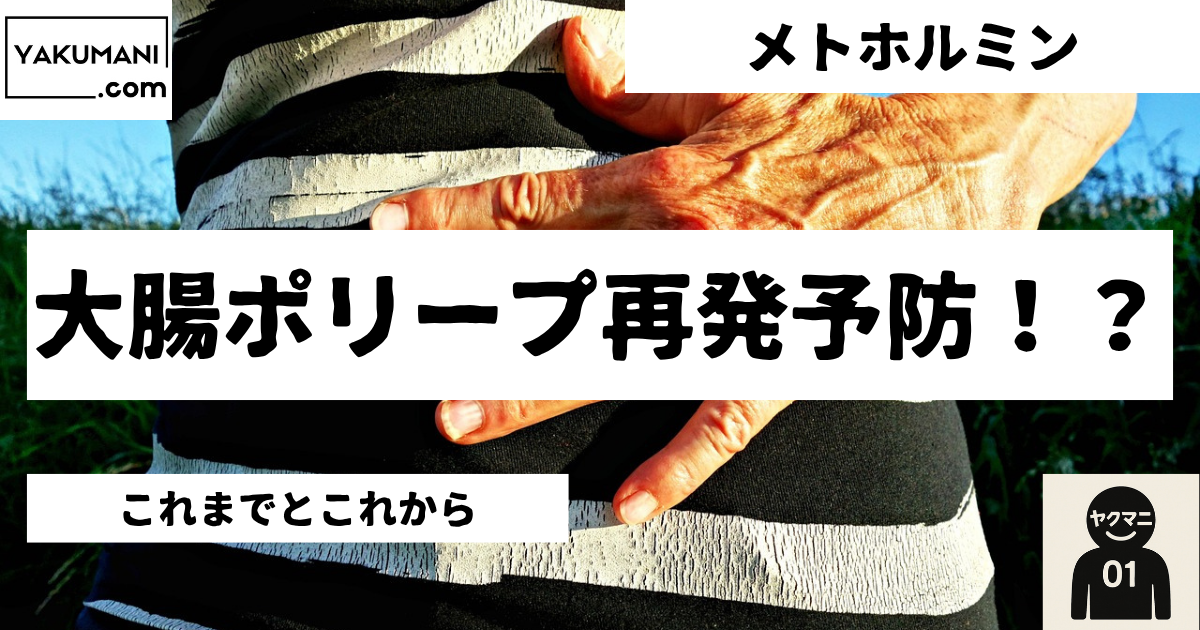
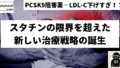
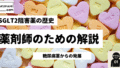
コメント