薬価制度とは
「薬価」とは、保険医療機関や保険薬局で使用される医療用医薬品に国が公定価格として定めた価格のことです 。国民皆保険制度の下では、この薬価基準に収載された医薬品しか保険で使えず、医療機関・薬局は薬価を基に保険請求を行います 。2020年現在、薬価基準に収載されている品目数は約1万4千品目にも及びます 。薬剤の剤形やメーカーごとにそれぞれ価格が定められており、薬価基準は医薬品の品目リストであると同時に価格表という二つの意義を持っています 。
しかし一方で、医薬品の市場での取引価格(卸売業者が医療機関や薬局に販売する価格)は自由競争で決まるため、公定価格である薬価との差額が生じます。この差額こそがかつて医療機関や薬局の大きな利益源となった「薬価差益」です 。薬価制度は、この薬価差益による弊害を是正しつつ、医薬品の安定供給や新薬開発のインセンティブも損ねないように、時代とともに何度も改革が行われてきました。この記事では、戦後から現代に至る薬価制度の変遷を時代ごとに辿り、**「なぜ今の薬価はこうなっているのか?」**という問いに答えていきます。薬価改定の歴史、かつての薬価差益の時代、ジェネリック医薬品(後発医薬品)推進政策、「イノベーション薬価」と呼ばれる新薬評価の仕組み、高額薬剤への対応(費用対効果評価導入)、さらには薬価改定の毎年化と今後の展望までを包括的に解説します。
戦後における薬価制度の発足
日本の公定薬価制度は、戦後間もない**1950年(昭和25年)**に始まりました 。それ以前の混乱期には「統制価格」によって国が医薬品価格を固定していましたが、インフレ抑制策として統制が徐々に解除され、医薬品も統制価格の対象から外れます 。そこで全国共通の公定価格が必要となり、1950年9月に厚生省告示により医薬品の基準価格が初めて定められました 。当初は物価庁の所管で制度がスタートし、1953年に所管が厚生省に移管されています 。さらに1955年には保険診療の「基準価格表」に医薬品価格が組み込まれ、1957年には日本医師会が策定した診療報酬点数表の改定で現在の薬価基準の形が確立しました 。
制度導入当初、薬価算定方式として採用されたのは**「バルクライン方式」でした 。これは医薬品の市場取引価格を安い方から並べ、累積購入量の一定割合(例えば90%)に達する価格を薬価とする方法で、できるだけ多くの流通量をカバーして安定供給を図る狙いがありました 。一方でこの方式では、公定薬価と市場実勢価格の乖離(ギャップ)が大きくなりがちです。その結果、生まれた差額は医療機関等の薬価差益となり、多くの批判を招くことになります 。高度経済成長期には医薬品の使用量・市場も拡大し、この差益を背景に「薬漬け医療」**(必要以上の多剤投与)も問題視されました。実際、1980年代初頭には医療費に占める薬剤費の比率が非常に高く、1982年には薬剤費が医療費の約38.7%を占めていたとの報告があります 。公定価格による償還(レセプト請求)と市場での仕入れ価格との差で大きな利益が得られる状況が続き、「薬価基準制度=医療機関の収入源」と揶揄されるほどでした(いわゆる「薬価差益の時代」)。
薬価差益の時代とその収束
医療機関が薬を出せば出すほど儲かる構造は、医療費膨張や過剰投薬を招く恐れがありました。そのため国は1970年代以降、薬価差益を縮小させる様々な施策を講じます。まず**医薬分業(処方と調剤の分離)**の推進です。1974年の診療報酬改定では、院外処方せんを発行した場合の処方料を60円から500円へ大幅増額し、医師が患者を院外の保険薬局に紹介するインセンティブを作りました 。しかし当時は処方せんを発行せず自院で調剤した方が薬価差益による収益が大きかったため、診療所・病院とも依然として院内処方が圧倒的多数でした 。実際、1990年になっても外来患者の約80%は院内で調剤されており、薬の差益が病院収入の約7%、診療所収入の約12%を占めていました 。
薬価差益そのものを縮小するため、薬価改定ルールの改革も行われました。先述のバルクライン方式は利益幅を許容しすぎるとの批判から、1992年の薬価改定で市場実勢価格の加重平均値に一定の調整幅を加える方式(Rゾーン方式)に変更されています 。当初調整幅(公定価格に上乗せする許容差)は15%でしたが、段階的に縮小され1998年には5%まで引き下げられました 。さらに2000年の改定で調整幅は2%となり 、ほぼ市場価格と乖離のない水準まで来ています(調整幅2%は「流通に必要な費用」として残されています)。この間、同じ効能の医薬品グループごとに一定の参照価格を定め、それを超える分は患者負担にする「参照価格制」の導入提案もありましたが、日本医師会などの反対で実現しませんでした 。とはいえ、90年代を通じた薬価算定ルールの透明化・適正化により薬価差をめぐる問題は大幅に改善され、医療費に占める薬剤費割合も1990年代後半には30%以下に低下しました 。
医薬分業も、薬価差益縮小策と相まって徐々に進展しました。1990年時点でわずか12%だった院外処方率(処方せん発行率)は、その後の制度誘導により2013年には69%にまで上昇しました 。つまり現在では外来患者の約7割が院外薬局で調剤を受けている計算です。薬剤の調剤主体が医療機関から保険薬局へ移行したことで、かつて病院・診療所にとっての「おいしい収入源」だった薬価差益の時代は終焉を迎えました。 現に、「これまでのような薬価差益が計上できる時代は終わり」を迎えたと評されます。
もっとも、薬価差益による利益が医療機関から消えたわけではなく、一部は薬局側に移りました。とりわけ病院門前に店舗を構えるチェーン調剤薬局(門前薬局)は、特定病院からの処方せんを一手に引き受けることで高い利益率を上げ、大きく成長しました。このことが新たな問題となり、近年では1つの薬局が特定医療機関の処方せんに過度に依存する場合に調剤報酬を引き下げる仕組みが導入されています 。さらに患者がかかりつけの薬局・薬剤師のもとで継続的に薬学管理を受けられるよう、「かかりつけ薬剤師・薬局」制度を設けて一定の条件を満たす薬局には報酬上の加算を認めるなど、質の高い薬局サービスへの転換も図られています 。
後発医薬品(ジェネリック)政策の展開
薬価差益の縮小と医薬分業の進展により、医療費に占める薬剤費比率は一時低下傾向を辿りました。しかし医療費全体は高齢化に伴い増加を続けており、政府は引き続き薬剤費適正化の方策を模索します。その柱の一つが後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進政策です。ジェネリック医薬品は先発医薬品と有効成分・効果が同等で、特許切れ後に低価格で供給される医薬品ですが、日本では長らく医師・患者の不信感や情報不足もあって普及が進みませんでした。2000年代に入り、国は後発品普及に本腰を入れ始めます。例えば2007年には「後発医薬品安心使用促進アクションプログラム」を策定し、処方せん様式における「変更不可」欄の新設(医師が特に先発品に限定したい場合のみ記載)など処方現場での後発品使用を妨げない工夫を行いました。また診療報酬上も後発品調剤体制加算を設け、薬局がジェネリック調剤を一定割合以上行えば評価する仕組みを導入しています 。
こうした政策の成果もあり、後発医薬品のシェアは急速に上昇しました。政府は数年ごとに数値目標を設定しており、2013年には「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定して2018年(平成30年)9月までに数量シェア※70%以上を目標に掲げ 、その後**「2020年9月までに80%以上」へと目標を引き上げました 。この80%という水準は欧米諸国並みであり、実際に日本でも2020年前後に数量ベース目標をほぼ達成しています 。ただし注意すべきは、この「80%」という数値は後発品が存在する医薬品についての数量割合である点です 。医療用医薬品全体の薬剤費に占める後発品の金額割合で見れば、たとえ数量で80%に達しても金額ベースでは約20%程度に留まる**との推計もあります 。すなわち、ジェネリックの普及は一定の薬剤費削減効果を持つものの、それだけで医療費問題を解決する万能策ではないことも事実です。
ジェネリック普及策の一環として、先発品(長期収載品)の価格を強制的に引き下げるルールも導入されました。2018年の薬価制度改革では、後発品への置き換えを促すための新ルールとしてG1ルール・G2ルールが設けられています 。これは一定期間が経過した先発医薬品について、後発品の普及状況に応じて薬価を大幅に追加引き下げる仕組みです(後発品への置換率が低い場合でもG2ルールで15%程度、置換率が高い場合はG1ルールで最大25%もの引き下げ )。このように先発品の価格を下げることで、経済的誘因からも後発品への切り替えを後押ししました。
近年では、ジェネリック医薬品そのものの安定供給と品質確保も重要な課題となっています。2020~2021年頃には大手後発品メーカーで相次いだ不祥事・生産停止により流通が混乱し、「ジェネリック薬品不足」が社会問題化しました。これを受け政府は2021年6月の閣議決定で「2023年度末までに全ての都道府県で後発品使用率80%以上」とする新目標を掲げ、同時に業界の構造改革や品質管理の強化策に乗り出しています 。さらに2024年にはロードマップを改訂し、「安定供給の確保を基本として後発医薬品を適切に使用していく」ことを強調するとともに、2029年度末までに全国平均80%以上維持、金額ベースシェア65%以上といった中長期目標も示されました 。ジェネリック医薬品は今や薬剤費適正化に欠かせない基盤ですが、その基盤を支える産業自体の持続性も問われる段階に来ており、引き続き国主導でのテコ入れが行われている状況です。
新薬のイノベーション評価と薬価算定
一方、医療の質向上や製薬産業の発展のためには、新薬の開発インセンティブを損なわないことも薬価制度の重要な役割です。日本の薬価算定方式は大きく新規収載医薬品(新薬)と既収載医薬品で異なります。新薬の薬価は、原則として**「類似薬効比較方式」で算定されます 。これはその新薬と効能・効果が近い既存薬がある場合、その1日あたり治療費(薬価)をベースに価格を決める方法です 。ただし新薬の内容が画期的であれば、単純に既存薬と同じ価格にはしません。例えば「画期性加算」「有用性加算」「市場性加算」「小児加算」など、革新的新薬の価値を評価して薬価に上乗せ(補正加算)する仕組みがあります 。加算率はその新薬の革新性・有用性の程度に応じて5%から最大120%もの幅まで設定されており、高い治療効果や新機序を持つ薬ほど高いプレミアムが付く設計です 。一方で新薬に比較対象となる類似薬が無い場合は「原価計算方式」**が用いられ、開発コストや製造原価に一定の営業利益や流通経費等を加えて価格算定されます 。いずれの方式でも、最後に欧米4か国(米英独仏)の価格との比較調整や、剤形・規格間の調整を行い、公正かつ国際的にも妥当な水準の薬価が付けられます 。
また、日本独自の制度として2010年度に試行導入された**「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」があります 。これは製薬企業が新薬創出や未承認薬の適応拡大に積極的に取り組むことを条件に、対象となる新薬について薬価改定時の引き下げを免除または緩和する制度です 。通常、新薬も収載後一定期間が経てば他の既収載品と同様に市場実勢価格に合わせて薬価引き下げが行われます。しかしこの加算の対象に指定された革新的新薬は、特許期間中ある程度価格が維持されるため、企業は売上を研究開発費に再投資しやすくなります。新薬創出加算の導入背景には、かつて日本で新薬の発売が欧米より遅れるドラッグラグ問題**や、国内で開発が敬遠されていた難治疾患の薬(未承認薬問題)を改善したいという政策目的がありました 。実際、この制度が導入された2010年前後から、日本での新薬承認件数は増加傾向を示し、2005年には年30品目程度だった新薬収載が近年では年100品目超となるなど開発意欲の向上に一定の効果を上げたとされています 。
とはいえ近年、財政面からの圧力で新薬創出加算の適用要件は徐々に厳格化されています。2018年度の薬価制度抜本改革では、同加算の対象品目を「真に医療上必要な医薬品」に限定する見直しが行われました 。具体的には、売上規模が大きく利益も十分見込める新薬は加算の対象から外し、本当に政策的支援が必要な画期的新薬のみ価格維持を図る方向に舵が切られています 。「イノベーション薬価」とはこのように創薬イノベーションの価値を適切に薬価へ反映する考え方を指し、近年の改革のキーワードになっています。2022年度・2024年度の薬価制度改革でも「イノベーションの評価の充実」が掲げられ、承認後に追加適応が認められた場合でも新薬創出加算の対象を継続するなど企業の開発意欲を削がない配慮が強化されました 。他方で、新薬に高い薬価を付け続けることは医療保険財政への負担増にも直結するため、**国民皆保険の維持(財政健全化)**とのバランスをどう取るかが常に問われています 。この点については次の高額薬剤の項で、費用対効果評価などの仕組みと併せて説明します。
高額薬と費用対効果評価の導入
2010年代後半になると、医学の進歩により極めて高額な新薬が次々と登場するようになりました。代表例が抗癌剤のオプジーボ(ニボルマブ)で、2014年の発売時に1瓶約73万円という驚くべき薬価が設定されました 。当初は対象患者が少ない皮膚がん向けでしたが、その後適応拡大で肺がんなどにも使われ患者数が激増したため、年間医療費が数千億円規模に膨らむ恐れが生じました。このままでは「薬剤費の高騰で皆保険体制が維持できなくなる」との危機感から、オプジーボの薬価は発売からわずか2年で緊急に半額に引き下げられる事態となりました 。また、C型肝炎治療薬ソバルディやハーボニーも1人当たり数百万円の治療費ですが患者多数に及ぶため、同様に大きな財政インパクトが問題視されました。こうした「予想外に市場が拡大した高額新薬」への対応策として、**2000年に導入されていた「市場拡大再算定」**ルールがあります 。市場拡大再算定では、新薬の年間売上が当初予測の2倍超かつ150億円超の場合などに次回改定で一定割合(最大25%)の薬価引き下げを行う決まりでした 。しかし近年の高額薬は桁違いの売上規模となるケースが出てきたため、**2016年度改定で「市場拡大再算定の特例」**が新設されました 。この特例では、年間売上1000億円超かつ予想比1.3倍超の場合は最大50%引き下げといったより厳しい基準を適用し、実際にソバルディやハーボニーが大幅な薬価引き下げとなっています 。以降、この特例は適応追加等で市場拡大した場合にも適用されるよう拡充され、超高額薬剤による急激な保険財政悪化を防ぐセーフティネットとして機能しています。
さらに、費用対効果評価(経済的価値評価)の制度も導入されました。日本では試行的な導入期間を経て2019年4月から費用対効果評価が本格運用されています 。これはいわゆるHTA(ヘルス・テクノロジー・アセスメント)の一種で、新薬の1品質調整生存年(QALY)あたりのコストを分析し、その結果に基づいて薬価を調整する仕組みです 。具体的には、前述の薬価算定時に付与された有用性加算など価格の加算部分を主な対象として、治療効果に対する価格が高すぎると判断された場合に加算率を引き下げる、といった調整を行います 。重要なのは、日本の費用対効果評価はイギリスのNICEのように薬剤の採否(保険収載可否)を決めるものではなく、あくまで**薬価制度の一部(補完)**として位置付けられている点です 。保険収載はまず行い、その後に経済評価を実施して価格を見直すため、患者が新薬を使える機会を大幅に遅らせることなくコストと価値のバランス調整ができます。2019年以降、オプジーボを含む高額薬剤や対象品目に選定された医薬品について順次この評価が行われ、実際にいくつかの薬剤で価格調整(引き下げ)が実施されています 。費用対効果評価の導入は、超高額な医療技術が今後増えても科学的根拠に基づき「支払う価値のある価格」に調整していく枠組みであり、国民皆保険を持続可能にする切り札の一つと期待されています。政府は2022年以降、この制度の運用改善にも継続的に取り組んでおり、評価プロセスの迅速化や企業からのコスト情報開示の徹底などが議論されています。
薬価改定の頻回化(毎年改定制度)
上述のように薬価は市場価格との乖離是正のため定期的に引き下げられますが、2010年代までは原則2年に1度、診療報酬(医師の治療行為の報酬)改定と同じサイクルで実施されてきました 。しかし近年、薬価差が縮小したとはいえ完全になくなったわけではなく、2年間の間にどうしても実勢価格との乖離が積み上がります。また高額薬剤の出現で薬剤費抑制の緊急性が増したこともあり、政府は薬価改定の頻度を上げる決断をしました。2016年末、関係閣僚合意により「薬価改定の毎年実施」方針が打ち出され 、2018~2020年に試行的な全品目改定を経て、2021年度から本格的に診療報酬改定の無い中間年度にも薬価改定を行う制度がスタートしました 。つまり現在では、医療用医薬品の公定価格である薬価は毎年見直されることが原則となっています 。
毎年改定の仕組みでは、毎年行われる薬価調査に基づき、市場実勢価格に合わせて薬価が引き下げられます。基本的な算定式自体は従来と同じ**「市場実勢価格加重平均値+消費税分+調整幅2%」**ですが 、改定頻度が2年に1回から毎年に倍増したことで、薬価下落のスピードが上がりました。たとえばこれまで改定までに平均10%の乖離が生じていたものが、年1回改定なら約半分の5%程度の乖離で都度修正されるイメージです 。これにより医療機関や薬局が薬価差益を蓄積する余地はさらに減り、薬剤費の無駄な支出を抑制できると期待されています。もっとも、薬局経営などの現場からは「毎年薬価が下がっては経営が不安定になる」との声もあります。実際、2021年度に初めて中間年改定が実施された際には新型コロナ対応で一時見送り論も出ました 。2022年度・2023年度と連続して改定が行われた後、2025年度の中間年改定を巡っては実施の要否も含め議論が続いています 。毎年改定の定着にあたって、例外的に改定を休止する状況(例えばパンデミックや物価高騰など)をどう扱うか、今まさに中医協で検討が行われているところです。
とはいえ大局的には、少なくとも当面は**「薬価は毎年下がるもの」と見ておく必要があります。実際、近年の薬価改定は引き下げが顕著であり 、政府も社会保障費伸びの抑制策として薬価毎年改定を今後も継続する姿勢です 。医療現場・企業側にとっては厳しい環境ですが、裏を返せば医薬品の公定価格が毎年更新されるほど日本の財政状況は逼迫している**ということでもあります 。この点を踏まえ、次章で日本の薬価制度の今後の展望について考察します。
今後の展望(持続可能性と展開)
日本の薬価制度は戦後から現在まで、その時々の課題に対応する形で変革を遂げてきました。現在直面している最大の課題は医療費の持続可能性です。少子高齢化による社会保障費の膨張で国家財政は厳しさを増しており、薬剤費も例外ではありません。2019年度の国民医療費は約44.4兆円、そのうち薬剤費は約9.6兆円(全歳出約100兆円の約1割)にのぼります 。防衛費や他の政策予算と比べても薬剤費の占める規模は非常に大きく、今後も薬価抑制は避けられない見通しとされています 。実際、政府は毎年改定の運用によって一定の薬剤費削減効果を上げており、2022年度までの累積で数千億円規模の国庫負担軽減につながったとの試算もあります(※令和4年度薬価改定の概要より)。
しかし、医療の進歩に伴い画期的新薬が登場し続ける限り、単純な引き下げ一辺倒では将来の医療イノベーションが停滞しかねないとの懸念もあります。そこで重要になるのが**「メリハリの効いた薬価政策」です。今後は、真に有用な医薬品には適正な評価を与えつつ、そうでない部分には大胆な削減を行う方向性が一段と強まるでしょう。具体的には、費用対効果評価のさらなる活用やプレミアム加算の精緻化により、高い医療価値を提供する薬は一定の価格を維持し、効果に乏しい薬や古い薬は一層の価格引き下げで対応する戦略です 。2025年度以降の薬価制度改革でも、「ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消とイノベーション評価の適切な実施」「特許期間中の薬価の在り方」などが議題に上っています 。製薬企業側からは「特許期間中は薬価を下げないでほしい」といった要望も根強いですが 、国民皆保険を守る立場からは国民負担の軽減**とのバランスを取らねばなりません 。今後も中医協の場で激しい議論が続くと予想されます。
ジェネリック医薬品についても、将来の課題があります。数量シェア80%達成後は伸び代が小さくなっており、金額ベースでのシェア拡大や品質・安定供給の確保がテーマになります 。前述のように業界再編や国による生産管理監督の強化が進んでおり、信頼性向上によってジェネリック普及を定着させる取り組みが続くでしょう。またバイオ医薬品の特許切れに伴うバイオ後続品(バイオシミラー)の活用も、費用対効果の面から重要になります。バイオ後続品は開発コストが高いため普及率はまだ低いですが、政府は2029年度までに主要バイオ薬品の60%以上でバイオシミラーが80%以上使われるという目標を掲げています 。高額なバイオ新薬への支出を抑えるには欠かせない要素であり、今後の課題です。
最後に、超高額な先進医療への対応も見据える必要があります。遺伝子治療や細胞治療など一度の投与で劇的な効果を発揮するが数千万円に及ぶ治療法が既に登場しており、薬価制度も新たな枠組みを考える段階に来ています。例えば「結果に連動した支払い」(アウトカムに応じて費用を支払う)や分割払い・リースのような形で高額費用を平準化する制度設計など、海外で模索されているモデルを日本に導入することも検討課題になるでしょう。厚生労働省も2023年に「高額薬剤に関する専門部会」を設置し、これらの問題について議論を始めています(※厚労省審議会資料より)。国民皆保険を次世代に繋ぐため、薬価制度は今後も進化を続けると考えられます。
まとめ
日本の薬価制度は、戦後の統制価格から始まり、公定価格による全国一律の価格設定と保険給付の基盤を築きました。その後、医療機関による薬価差益の問題が顕在化すると、薬価差の縮小と医薬分業の推進によって「薬漬け医療」の是正が図られました 。2000年代以降は後発医薬品の普及が加速し、ジェネリックの活用が医療費適正化の柱となりました 。一方で、新薬のイノベーション価値をどう評価し価格に反映するかも大きなテーマとなり、各種プレミアム加算や新薬創出加算で革新的新薬を優遇しつつ 、費用対効果評価の導入や市場拡大再算定で高額薬剤による財政リスクに備える仕組みも整えています 。近年はついに薬価改定が毎年行われるようになり 、常態的な薬価引き下げの中でいかに医療の質と持続可能性のバランスを取るかが問われています 。
「なぜ今の薬価はこうなっているのか?」——それは、一言でいえば過去から積み重ねられた制度改革の結果です。医療提供者の行動を歪めないように、また患者が必要な薬を適正に入手できるように、制度は試行錯誤を繰り返してきました。その過程で薬価は単なる「薬の値段」ではなく、医療政策の調整弁として機能しています。薬局・病院・製薬企業と立場は違えど、薬剤師にとって薬価制度の理解は必要不可欠です。薬価改定の動向一つで経営も業務も影響を受けますし、新薬の価値評価に薬学的見地から関与していく余地もあります。幸い、日本の薬価制度は今後も公開の場で議論され、改良が続けられるでしょう。本記事で辿った歴史と現状を踏まえ、読者の皆様が薬価制度への理解を深め、日々の業務や将来展望に役立てていただければ幸いです。

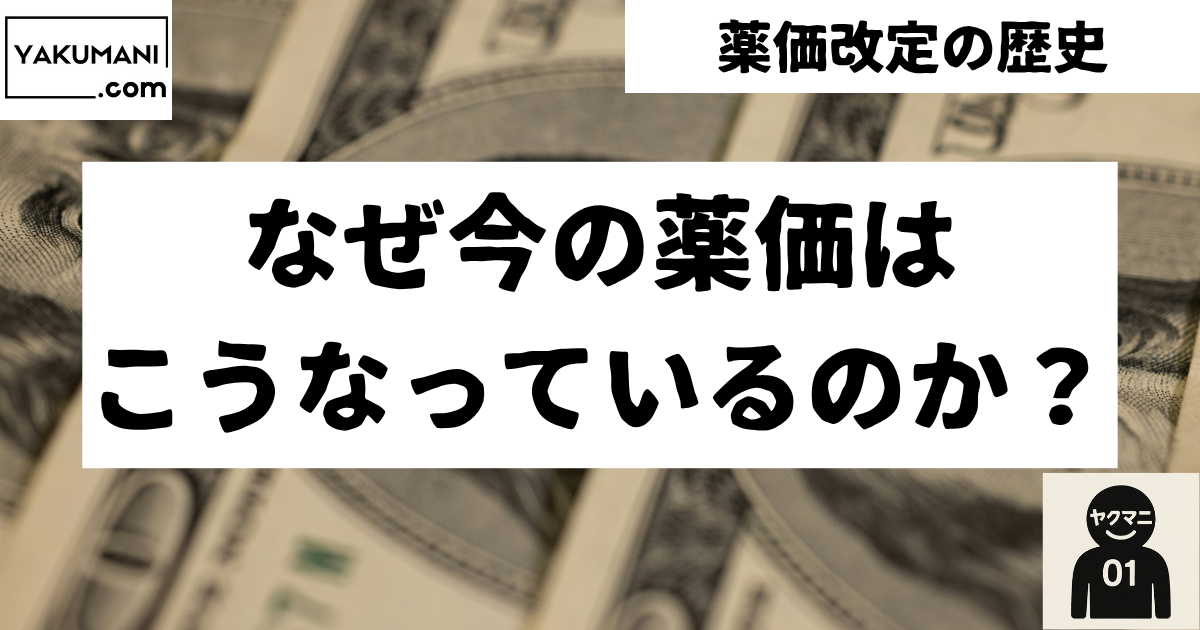
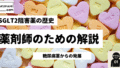
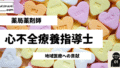
コメント